M&Aスケジュール|基本から実践まで!失敗しないための工程表と注意点
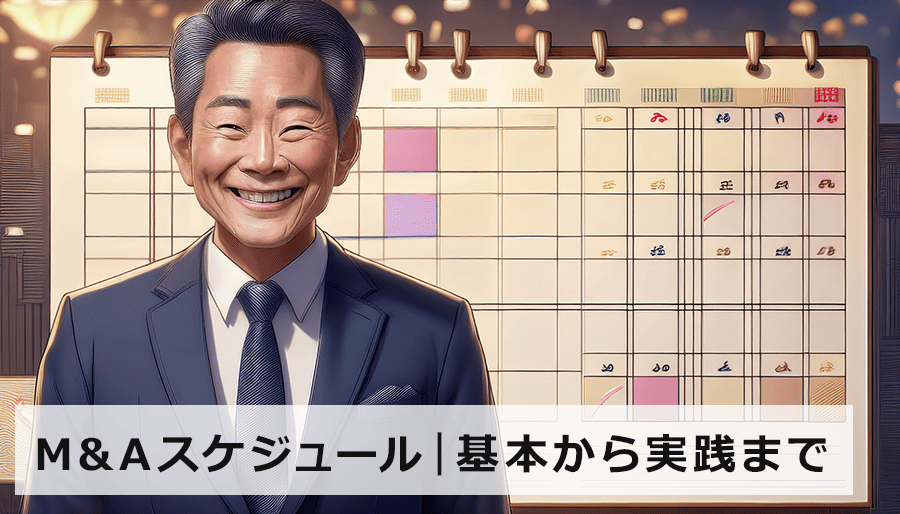
M&Aスケジュールは、M&Aを成功させるための重要な要素です。このページでは、M&Aの基本プロセスと、それぞれの段階におけるスケジュール、そしてM&Aスケジュール作成のポイントを解説します。買収側・売却側それぞれのスケジュール、さらにM&Aにおけるスケジュールの重要性や種類、予期せぬ事態への対応策まで網羅的に理解することで、M&Aをスムーズに進めるための全体像を把握できます。
M&Aの検討段階からクロージング、PMIまで、各段階での具体的なスケジュール感や注意点を知ることで、M&Aプロセスを効率的に管理し、成功確率を高めるための実践的な知識が得られます。本記事で紹介する工程表サンプルも活用し、スムーズなM&Aを実現しましょう。
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. M&Aスケジュールとは
M&Aスケジュールとは、M&A(合併・買収)のプロセス全体を時系列に沿って計画したものです。M&Aは複雑な手続きを伴うため、円滑かつ効率的に進めるためには綿密なスケジューリングが不可欠です。適切なスケジュールを策定することで、取引の遅延やコスト増加を防ぎ、成功確率を高めることができます。
M&Aスケジュールは、買収側と売却側それぞれで作成され、それぞれの立場や戦略によって内容が異なります。また、M&Aの規模や種類、業界の特性などによってもスケジュールは大きく変動します。そのため、個々のM&A案件に最適なスケジュールを柔軟に設計することが重要です。
1.1 M&Aにおけるスケジュールの重要性
M&Aにおいて、スケジュール管理はプロジェクトの成否を左右する重要な要素です。適切なスケジュールを策定し、それを遵守することで、以下のメリットが期待できます。
- 取引の円滑化:各段階におけるタスクや責任分担を明確にすることで、M&Aプロセスをスムーズに進めることができます。
- コスト管理:スケジュール通りにプロセスを進めることで、時間的ロスや無駄なコストを削減できます。
- リスク管理:潜在的なリスクを早期に特定し、適切な対策を講じることで、M&Aに伴うリスクを最小限に抑えることができます。
- 関係者間の連携強化:スケジュールを共有することで、関係者間の情報共有と連携を強化し、スムーズな意思決定を促進できます。
- 成功確率の向上:綿密な計画と適切なスケジュール管理は、M&Aの成功確率を高めるための重要な要素です。
M&Aスケジュールは、主に買収側と売却側で作成されます。それぞれの立場によって目的や重点が異なるため、スケジュール内容も異なります。
1.2.1 買収側スケジュール買収側のスケジュールは、ターゲット企業の価値評価、デューデリジェンス、交渉、契約締結、PMI(Post Merger Integration)といったプロセスを網羅します。買収戦略に基づき、迅速かつ効率的にM&Aを完了させることを目的とします。
例えば、シナジー効果の早期実現を重視する場合、PMIのスケジュールを詳細に計画する必要があります。また、競合他社との買収合戦に備えて、迅速な意思決定と実行を可能にするスケジュールが求められます。
【関連】M&Aの買収準備とは?内容・スケジュールと成功のためのポイントを徹底解説!1.2.2 売却側スケジュール
売却側のスケジュールは、企業価値の最大化、円滑な事業譲渡、従業員への配慮などを重視した内容となります。事業の引継ぎや従業員への説明、株主総会などの手続きを適切なタイミングで実施するためのスケジュールが重要です。
例えば、従業員の雇用維持を重視する売却企業は、買収後の従業員への影響を最小限に抑えるためのスケジュールを策定する必要があります。また、株主への説明責任を果たすため、株主総会や情報開示に関するスケジュールも重要となります。
| 項目 | 買収側 | 売却側 |
|---|---|---|
| 目的 | ターゲット企業の買収、シナジー効果の最大化 | 企業価値の最大化、円滑な事業譲渡 |
| 重視する点 | デューデリジェンス、価格交渉、PMI | 企業価値評価、情報開示、従業員への配慮 |
| リスク | 過大評価、PMIの失敗 | 売却価格の低下、従業員の流出 |
M&Aのプロセスは、大きく分けて準備段階、交渉段階、実行段階、統合段階の4つの段階に分けることができます。それぞれの段階におけるスケジュール感と具体的な内容は以下の通りです。
【関連】事業売却プロセス|準備から成約までの流れと費用を徹底解説!2.1 準備段階(1~3ヶ月)
M&Aを実行するにあたり、まずは綿密な準備が必要です。この段階でしっかりと準備を行うことで、その後のプロセスをスムーズに進めることができます。
2.1.1 M&Aの目的明確化M&Aを行う目的を明確にすることは非常に重要です。市場シェアの拡大、技術力の向上、事業の多角化など、目的を明確にすることで、適切なターゲットを選定し、効果的な戦略を立てることができます。自社の経営資源や強み・弱みを分析し、M&Aによってどのようなシナジー効果を生み出したいのかを明確にしましょう。M&A後のビジョンを具体的に描くことが、成功への第一歩です。
2.1.2 アドバイザー選定M&Aは複雑なプロセスであるため、専門的な知識を持つアドバイザーの選定が不可欠です。M&Aアドバイザリー会社、法律事務所、会計事務所、税理士法人など、それぞれの専門家に相談し、適切なチームを編成しましょう。アドバイザーは、M&Aの戦略立案、ターゲット選定、デューデリジェンス、契約交渉、PMIなど、様々な局面でサポートを提供してくれます。実績や専門性、費用などを考慮し、自社に最適なアドバイザーを選びましょう。
【関連】M&Aアドバイザーの選び方|中小企業経営者が知っておくべきポイント2.1.3 ターゲット選定
明確にしたM&Aの目的に基づき、適切なターゲット企業を選定します。業界動向、競合状況、財務状況、技術力、経営陣などを分析し、自社とのシナジー効果が見込める企業を選びましょう。データベースや業界紙、M&Aアドバイザーからの情報などを活用し、候補となる企業をリストアップします。その上で、それぞれの企業について詳細な調査を行い、最終的なターゲットを絞り込みます。
【関連】事業売却の買い手探し、徹底ガイド!最適な相手を見つけるための7つのステップ2.2 交渉段階(3~6ヶ月)
ターゲット企業を選定したら、交渉段階に進みます。この段階では、秘密保持契約を締結し、相互に情報を開示しながら、条件を調整していきます。
2.2.1 基本合意契約締結ターゲット企業との交渉が一定の段階まで進んだら、基本合意契約(LOI:Letter of Intent)を締結します。LOIには、買収価格、買収方法、デューデリジェンスの実施、独占交渉権の付与など、M&Aの基本的な条件が記載されます。LOIは法的拘束力がない場合もありますが、双方の合意内容を明確にする上で重要な役割を果たします。
2.2.2 デューデリジェンス基本合意契約締結後、買収対象企業の財務状況、法務状況、事業状況などを詳細に調査するデューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスは、買収価格の算定やリスクの把握、M&A後の統合計画策定に不可欠なプロセスです。財務デューデリジェンス、法務デューデリジェンス、事業デューデリジェンスなど、様々な専門家が関与し、多角的な視点から調査を行います。
【関連】M&Aで失敗しないデューデリジェンス!目的・種類・費用は?【前編】2.2.3 最終契約交渉
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な買収条件を交渉します。買収価格、買収方法、契約締結日、クロージング日など、詳細な条件を決定し、最終契約書を作成します。この段階では、弁護士などの専門家のサポートを受けながら、綿密な交渉を行うことが重要です。
2.3 実行段階(1~3ヶ月)最終契約交渉が完了したら、契約を締結し、クロージングを行います。この段階では、資金の決済や株式の譲渡などが行われます。
2.3.1 契約締結最終契約書の内容に合意したら、正式に契約を締結します。契約締結により、買収者は買収対象企業の株式を取得し、経営権を移転します。
2.3.2 クロージング契約締結後、クロージング手続きを行います。クロージングでは、買収資金の支払い、株式の譲渡、登記変更などの手続きが行われ、M&Aが正式に完了します。
2.4 統合段階(3ヶ月~数年)M&A成立後は、買収企業と買収対象企業の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)が始まります。PMIは、M&Aの成否を左右する重要なプロセスであり、綿密な計画と実行が必要です。
2.4.1 PMI(Post Merger Integration)PMIでは、組織、人事、システム、文化など、様々な側面を統合していきます。統合プロセスは、事前に策定したPMI計画に基づき、段階的に進められます。統合を進める際には、従業員の不安や混乱を最小限に抑え、早期にシナジー効果を実現することが重要です。文化の違いや従業員のモチベーションに配慮しながら、統合を進めていくことが、M&A成功の鍵となります。
| 段階 | 期間 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 準備段階 | 1~3ヶ月 | 目的明確化、アドバイザー選定、ターゲット選定 |
| 交渉段階 | 3~6ヶ月 | 基本合意契約締結、デューデリジェンス、最終契約交渉 |
| 実行段階 | 1~3ヶ月 | 契約締結、クロージング |
| 統合段階 | 3ヶ月~数年 | PMI (Post Merger Integration) |
上記は一般的なM&Aのプロセスとスケジュールであり、個々の案件によって期間や内容は異なります。M&Aを成功させるためには、各段階において綿密な計画と準備を行い、専門家のアドバイスを適切に活用することが重要です。
【関連】PMI支援の専門サービス「PMIエージェント」3. M&Aスケジュールにおける注意点
M&Aを進めるにあたっては、綿密なスケジュール管理が不可欠です。しかし、計画通りに進まないことも想定し、柔軟な対応が求められます。ここでは、M&Aスケジュールにおける注意点を解説します。
3.1 スケジュールの柔軟性M&Aのスケジュールは、当初の予定通りに進むとは限りません。デューデリジェンスで予期せぬ問題が発覚したり、交渉が難航したりする可能性も考慮しておく必要があります。そのため、スケジュールにはある程度のバッファを持たせ、状況に応じて柔軟に変更できる体制を整えておくことが重要です。例えば、デューデリジェンスの期間を長めに設定したり、予備日を設けたりするなどの工夫が有効です。
また、市場環境や競合他社の動向など、外部要因によってスケジュールが影響を受ける場合もあります。常に最新の情報を入手し、必要に応じてスケジュールを調整していく柔軟性が求められます。
3.2 予期せぬ事態への対応M&Aプロセスでは、様々な予期せぬ事態が発生する可能性があります。例えば、以下の事態を想定し、事前に対応策を検討しておくことが重要です。
| 事態 | 対応策 |
|---|---|
| デューデリジェンスで重大な問題が発覚 | 契約条件の見直し、価格交渉、場合によってはM&Aの中止 |
| 競合他社による対抗買収 | 買収価格の引き上げ、ホワイトナイトとの提携 |
| 従業員の反発 | 丁寧な説明、適切な処遇、早期の不安解消 |
| 景気の悪化 | 資金調達の見直し、M&Aの延期 |
| 法規制の変更 | 専門家への相談、契約内容の変更 |
予期せぬ事態が発生した場合には、速やかに関係者間で情報共有を行い、適切な対応策を迅速に実行することが重要です。そのため、危機管理体制を事前に構築しておくことが不可欠です。
3.3 関係者とのコミュニケーションM&Aは、買収企業と売却企業だけでなく、従業員、株主、顧客、取引先など、多くの関係者が関わる複雑なプロセスです。円滑なM&Aを実現するためには、関係者との密なコミュニケーションが不可欠です。例えば、以下の点に注意する必要があります。
3.3.1 情報共有の徹底M&Aの進捗状況や重要な決定事項については、関係者に対して透明性高く情報共有を行うことが重要です。憶測や誤解を防ぎ、M&Aに対する理解と協力を得るために、適切なタイミングで適切な情報を提供する必要があります。社内報や説明会などを活用し、積極的に情報発信を行うことが重要です。
3.3.2 意見交換の場の設定関係者からの意見や質問を受け付ける場を設けることも重要です。M&Aに対する不安や疑問を解消し、円滑なプロセスを進めるために、双方向のコミュニケーションを積極的に図る必要があります。
3.3.3 迅速な対応関係者からの問い合わせや要望に対しては、迅速かつ丁寧に対応することが重要です。対応が遅れると、不信感や不満につながる可能性があります。専用窓口を設置するなど、迅速な対応ができる体制を整えておくことが重要です。
これらの注意点に留意し、適切なスケジュール管理と柔軟な対応、そして関係者との良好なコミュニケーションを図ることで、M&Aを成功に導く可能性を高めることができます。M&Aは企業にとって大きな転換期となるため、慎重かつ計画的に進めることが重要です。
4. M&Aに失敗しないための工程表M&Aを成功させるためには、綿密な計画と適切なスケジュール管理が不可欠です。工程表を作成することで、各段階のタスクと期限を明確化し、プロジェクト全体をスムーズに進めることができます。ここでは、M&Aにおける工程表作成のポイントとサンプル、そして工程管理ツールについても解説します。
4.1 工程表作成のポイント効果的な工程表を作成するためには、以下のポイントに留意しましょう。
- M&Aの目的と戦略の明確化:M&Aの目的、戦略、目標とする成果を明確に定義し、工程表に反映させることで、関係者全員が共通の認識を持つことができます。
- 現実的なスケジュール設定:各タスクに必要な時間とリソースを正確に見積もり、無理のないスケジュールを設定することが重要です。余裕を持ったスケジュールとすることで、予期せぬ事態にも対応できます。
- 主要なマイルストーンの設定:デューデリジェンス完了、基本合意契約締結、最終契約締結、クロージングといった主要なマイルストーンを設定することで、進捗状況を把握しやすくなります。
- 関係者間の情報共有:工程表は関係者間で共有し、定期的に進捗状況を確認することで、問題発生時の迅速な対応が可能となります。また、クラウド型の工程管理ツールを活用することで、リアルタイムな情報共有とスムーズなコミュニケーションを実現できます。
- 柔軟性の確保:M&Aプロセスは予期せぬ事態が発生しやすいものです。状況の変化に応じて工程表を修正できる柔軟性を確保しておくことが重要です。例えば、デューデリジェンスで想定外の課題が見つかった場合、スケジュールを調整する必要があるかもしれません。
以下は、M&Aにおける工程表のサンプルです。自社の状況に合わせて適宜修正してください。
| 段階 | タスク | 期間 | 担当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 準備段階 | M&Aの目的明確化 | 1週間 | 経営企画部 | M&Aの目的、戦略、目標を明確にする |
| 準備段階 | アドバイザー選定 | 2週間 | 経営企画部 | M&Aアドバイザー(金融機関、コンサルティング会社等)を選定する |
| ターゲット選定 | 4週間 | 経営企画部、事業部 | 買収または売却の対象となる企業を選定する | |
| 交渉段階 | 基本合意契約締結 | 2週間 | 法務部、アドバイザー | 基本的な合意事項を定めた契約を締結する |
| デューデリジェンス | 4週間 | アドバイザー、各部門 | 対象企業の財務、法務、事業等の状況を調査する | |
| 最終契約交渉 | 4週間 | 法務部、アドバイザー | 最終的な契約条件を交渉する | |
| 実行段階 | 契約締結 | 1週間 | 法務部 | 正式な契約を締結する |
| クロージング | 1週間 | 財務部、法務部 | 株式譲渡や事業譲渡等の手続きを行う | |
| 統合段階 | PMI (Post Merger Integration) | 3ヶ月~ | PMI推進チーム | 買収後の統合プロセスを円滑に進めるための活動を行う |
M&Aの工程管理には、専用のツールを活用することも有効です。以下のようなツールがあります。
- Microsoft Project:プロジェクト管理の定番ツール。ガントチャートを用いた視覚的なスケジュール管理が可能です。
- Backlog:プロジェクト管理ツール。タスク管理、ファイル共有、コミュニケーション機能などを備えています。
- Trello:カンバン方式でタスクを管理するツール。視覚的に進捗状況を把握しやすいのが特徴です。
- Asana:チームコラボレーションツール。タスク管理、進捗管理、コミュニケーション機能などを備えています。
これらのツールを活用することで、M&Aの工程を効率的に管理し、成功確率を高めることができます。自社のニーズに合ったツールを選び、適切に活用しましょう。また、M&Aアドバイザーに相談することで、最適なツールや工程管理方法についてのアドバイスを受けることができます。
5. まとめM&Aのスケジュールは、成功の鍵を握る重要な要素です。本記事では、M&Aの基本プロセスを準備、交渉、実行、統合の4段階に分け、それぞれの期間と具体的な内容を解説しました。買収側と売却側それぞれのスケジュール、そして全体的なスケジュール管理の重要性を理解することで、M&Aをスムーズに進めることができます。
スケジュール作成においては、柔軟性を持たせつつ、予期せぬ事態への対応策も考慮することが大切です。工程表を活用し、関係者間で密にコミュニケーションを取りながら、計画的にM&Aを進めることで、成功の可能性を高められるでしょう。本記事が、M&Aを検討している企業にとって、円滑なプロセス実現の一助となれば幸いです。


