M&Aの地位承継とは?メリット・デメリットも徹底解説
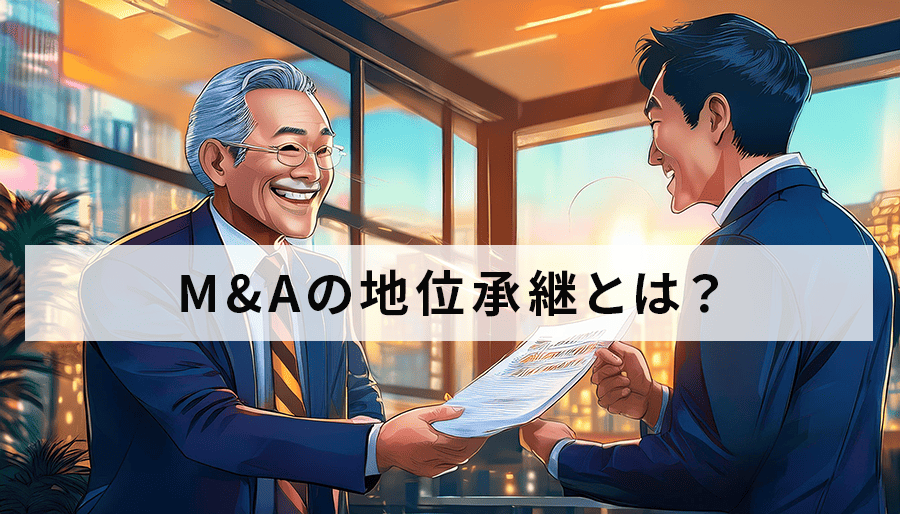
後継者不足に悩む経営者の方、M&Aによる地位承継をご存知ですか? M&Aは、事業をスムーズに次世代へ引き継ぐ有効な手段です。本記事では、M&Aによる地位承継の全体像を分かりやすく解説します。
メリット・デメリット、成功・失敗事例、事業承継との違いなど、M&Aによる地位承継のすべてを網羅的に理解することで、最適な事業承継戦略を構築できます。円滑な事業承継を実現し、企業の永続的な成長を促すためのヒントが満載です。ぜひ最後までお読みください。
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. M&Aによる地位承継の概要
この章では、M&Aによる地位承継の全体像を理解するために、地位承継そのものの意味、M&Aを用いた地位承継の具体的な内容、そしてM&Aと事業承継の違いについて解説します。
1.1 地位承継とは何か地位承継とは、経営者の地位、つまり会社経営における意思決定権や経営責任といった役割、およびそれに付随する権利義務を後継者に引き継ぐことを指します。後継者は親族に限らず、社内外の第三者でも構いません。地位承継は、企業の持続的な成長と発展のために欠かせない重要なプロセスです。スムーズな地位承継が行われなければ、企業の業績悪化や倒産といったリスクも考えられます。
地位承継には、親族内承継、従業員承継、M&Aによる承継といった様々な方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、企業の規模や状況、経営者の意向によって最適な方法を選択する必要があります。
1.2 M&Aによる地位承継とはM&Aによる地位承継とは、合併や買収といったM&Aの手法を活用して、経営権を後継者に引き継ぐ方法です。後継者問題を抱える企業にとって、事業を円滑に継続するための有効な手段として注目されています。特に後継者不在の企業にとっては、事業を売却することで、従業員の雇用を守り、取引先との関係を維持しながら、経営から退くことができるというメリットがあります。
M&Aによる地位承継は、株式譲渡、事業譲渡、合併といった形態で行われます。株式譲渡は会社の株式を売却することで経営権を移転する方法、事業譲渡は事業の一部または全部を売却する方法、合併は自社を他の会社に吸収合併または新設合併させる方法です。どの方法を選択するかは、企業の状況や経営者の意向によって異なります。
1.3 M&Aと事業承継の違いM&Aと事業承継は混同されがちですが、明確な違いがあります。事業承継は、広義には事業を次の世代に引き継ぐことを指し、後継者への経営権の移譲だけでなく、経営理念や技術、ノウハウ、顧客との関係といった事業基盤全体を継承することを含みます。一方、M&Aはあくまでも企業の合併や買収を指す言葉であり、事業承継はその目的の一つに過ぎません。
| 項目 | M&A | 事業承継 |
|---|---|---|
| 定義 | 企業の合併・買収 | 事業を次の世代に引き継ぐこと |
| 目的 | 企業の成長戦略、事業再編、地位承継など | 事業の継続・発展、経営理念の継承など |
| 対象 | 企業全体または事業の一部 | 事業全体、経営理念、技術、ノウハウなど |
| 関係性 | 事業承継はM&Aの目的の一つとなりうる | M&Aは事業承継の手段の一つとなりうる |
M&Aは事業承継の手段の一つとして活用できますが、M&A=事業承継ではありません。事業承継を考える際には、M&A以外の選択肢も検討し、自社にとって最適な方法を選択することが重要です。例えば、親族内承継や従業員承継といった方法も、M&Aと同様に有効な選択肢となり得ます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、総合的に判断することが重要です。
【関連】事業承継とM&Aの違いとは?メリット・デメリット、最適な仲介会社の見極め方を解説2. M&Aによる地位承継のメリット
M&Aによる地位承継には、従来の親族内承継や従業員への承継とは異なる様々なメリットが存在します。事業の安定性、成長性、従業員や取引先への配慮など、多角的な視点からメリットを理解することで、M&Aという選択肢の有効性を認識できるでしょう。
2.1 経営者の高齢化対策日本の経営者の高齢化は深刻な問題となっており、スムーズな事業承継が喫緊の課題です。M&Aは、年齢に関わらず優秀な経営人材を外部から確保できるため、経営者の高齢化による事業の停滞リスクを回避し、持続的な成長を可能にします。後継者探しに時間を費やすことなく、迅速に承継を進められる点も大きなメリットです。
2.2 後継者不足の解消親族や社内に適切な後継者候補がいない場合、事業承継は困難を極めます。M&Aを活用すれば、経営能力があり、事業への理解も深い外部人材を後継者として迎え入れることができます。これにより、後継者不足という深刻な問題を解消し、事業の継続性を確保できます。特に、高度な専門知識や技術が必要な事業においては、M&Aによる外部人材の登用は大きなメリットとなります。
【関連】後継者がいない...と悩む前に!事業承継の選択肢を広げ、企業の未来を創造しよう2.3 事業の継続と発展
M&Aは、単なる事業の承継だけでなく、更なる発展を目指すための有効な手段です。買収企業の経営資源やノウハウを活用することで、新たな市場への進出や事業の多角化を実現できます。シナジー効果による売上増加やコスト削減も期待でき、企業価値の向上に繋がります。また、M&Aによる事業拡大は、従業員のモチベーション向上にも寄与するでしょう。
2.4 従業員の雇用維持後継者不足による廃業は、従業員の雇用喪失に直結します。M&Aは、事業を継続させることで従業員の雇用を守り、彼らの生活基盤を維持することに貢献します。また、買収企業の経営資源を活用することで、従業員にとってより良い労働環境やキャリアアップの機会を提供できる可能性も高まります。従業員の雇用を守ることは、企業の社会的責任を果たす上でも重要な要素です。
【関連】会社売却で従業員の雇用を守る方法とは?中小企業のM&A成功の虎の巻2.5 取引先の安心感
事業承継がスムーズに行われない場合、取引先は今後の取引継続に不安を抱く可能性があります。M&Aによって事業の継続性が確保されれば、取引先との信頼関係を維持し、安定した取引を継続できます。特に、長年の取引実績がある企業にとっては、取引先の安心感は非常に重要です。M&Aによる事業承継は、取引先との良好な関係を維持する上で大きなメリットとなります。
2.6 節税効果M&Aには、一定の条件を満たすことで、相続税や贈与税の節税効果が期待できる場合があります。例えば、株式交換や株式移転といった手法を用いることで、相続税評価額を抑えることが可能です。ただし、節税対策のみを目的としたM&Aは、税務当局から否認されるリスクもあるため、専門家への相談が不可欠です。
【関連】M&Aにおける税金対策の全て!節税効果を高める戦略と注意点
| 手法 | 概要 | 節税効果 |
|---|---|---|
| 株式交換 | 自社の株式を相手会社の株主へ交付し、相手会社を完全子会社化する方法 | 相続税評価額の抑制 |
| 株式移転 | 新たに設立する持株会社に自社の株式を移転し、持株会社の子会社となる方法 | 相続税評価額の抑制 |
M&Aによる地位承継は、メリットだけでなくデメリットも存在します。M&Aを進める前に、デメリットについても十分に理解し、対策を講じる必要があります。デメリットを軽視すると、M&A後に想定外の困難に直面する可能性があります。
【関連】事業承継で会社を従業員に引き継ぐ際の注意点|円滑な移行のための10個のポイント3.1 経営権の喪失
M&Aによって、経営権を完全に、あるいは部分的に喪失する可能性があります。買収企業の意向が強く反映されるようになり、従来の経営方針や意思決定プロセスが変更される可能性も高いでしょう。創業家一族や既存経営陣にとっては、影響力の低下を受け入れる必要があるかもしれません。特に、株式譲渡によるM&Aの場合、支配権の移動に伴い経営権も移転するため、この点は十分に留意が必要です。
3.2 企業文化の変化買収企業と被買収企業の企業文化が異なる場合、統合プロセスにおいて摩擦が生じる可能性があります。従業員の価値観、行動規範、社風などの違いが、コミュニケーションの齟齬や組織内の対立につながる可能性も懸念されます。人事制度や評価システムの変更も、従業員のモチベーションに影響を与える可能性があります。例えば、成果主義の導入や年功序列制度の廃止などは、従業員の不安や反発を招く可能性があるため、慎重な対応が必要です。
3.3 従業員の反発M&Aは、従業員にとって大きな変化であり、将来への不安につながる可能性があります。雇用条件の変更、配置転換、人員削減などの可能性は、従業員のモチベーション低下や反発を招く可能性があります。特に、買収企業の待遇が悪かったり、企業文化が大きく異なったりする場合は、優秀な人材の流出につながるリスクも高まります。そのため、M&Aのプロセスにおいては、従業員への丁寧な説明とコミュニケーションが不可欠です。
3.4 デューデリジェンスの負担M&Aを行う際には、デューデリジェンス(買収監査)と呼ばれる、買収対象企業の財務状況、法務状況、事業状況などを詳細に調査するプロセスが必要です。このプロセスは、被買収企業にとって大きな負担となります。膨大な資料の準備や担当者への対応が必要となり、通常業務に支障が出る可能性もあります。また、デューデリジェンスの結果によっては、M&Aの条件が変更されたり、M&A自体が中止になったりする可能性もあります。
【関連】M&Aで失敗しないデューデリジェンス!目的・種類・費用は?【前編】3.5 M&Aコストの発生
M&Aには、様々なコストが発生します。M&Aアドバイザーへの手数料、弁護士費用、デューデリジェンス費用、株主総会開催費用など、多額の費用が必要となる場合もあります。規模の小さい企業にとっては、これらのコストが大きな負担となる可能性があります。また、M&A後の統合プロセスにも費用が発生するため、資金計画を綿密に立てる必要があります。
【関連】M&A費用の相場と内訳を分かりやすく解説!成功事例から学ぶ賢いコスト管理3.6 価格交渉の難しさ
M&Aにおける価格交渉は、非常に難しいプロセスです。買収企業と被買収企業の間で、企業価値に対する評価が異なる場合、交渉が難航する可能性があります。また、感情的な対立が生じることもあり、M&A自体が破談になるケースも少なくありません。客観的なデータに基づいた評価を行い、双方が納得できる価格で合意することが重要です。
| デメリット | 詳細 | 対策 |
|---|---|---|
| 経営権の喪失 | 買収企業の意向が優先され、既存経営陣の影響力が低下する。 | M&A後の経営体制について事前に協議し、合意形成を図る。 |
| 企業文化の変化 | 企業文化の衝突により、従業員のモチベーション低下や離職につながる可能性がある。 | 統合後の企業文化を明確化し、従業員への丁寧な説明と理解促進に努める。 |
| 従業員の反発 | 雇用不安や待遇の変化に対する反発が生じる可能性がある。 | 従業員とのコミュニケーションを密にし、不安解消に努める。M&A後の雇用条件を明確に提示する。 |
| デューデリジェンスの負担 | 膨大な資料の準備や対応に時間と労力がかかる。 | デューデリジェンスの範囲とスケジュールを事前に明確にし、効率的な対応を図る。 |
| M&Aコストの発生 | アドバイザー費用、弁護士費用など、多額の費用が発生する。 | M&Aコストを事前に見積もり、資金計画を綿密に立てる。 |
| 価格交渉の難しさ | 企業価値の評価をめぐり、交渉が難航する可能性がある。 | 客観的な評価に基づき、双方が納得できる価格で合意形成を目指す。専門家の助言を得る。 |
4. M&Aによる地位承継の成功事例
M&Aによる地位承継を成功させた事例を、業種や規模の異なる企業を例に紹介します。成功のポイントは、事前の綿密な計画、双方の企業文化の理解、そして従業員との丁寧なコミュニケーションです。これらの事例を参考に、M&Aによる地位承継の可能性を探ってみましょう。
4.1 中小企業A社の事例:ニッチ市場でのシェア拡大と後継者問題の同時解決地方都市で精密部品加工業を営む中小企業A社は、高い技術力を持つものの、後継者不在に悩んでいました。創業社長の高齢化に伴い、事業継続が危ぶまれる中、M&Aによる地位承継を決断しました。A社は、同業の大手企業B社にM&Aを打診。B社はA社の技術力とニッチ市場でのシェアに着目し、M&Aに合意しました。
M&A後、A社はB社の傘下に入り、資金力と販売網を活用することで、事業を拡大することに成功しました。また、B社から派遣された経営陣は、A社の企業文化を尊重し、従業員との信頼関係を構築することに尽力しました。結果として、従業員の雇用は維持され、A社の技術はB社の製品開発に活かされるなど、双方にとってWin-WinのM&Aとなりました。
4.1.1 A社M&A成功のポイント- ニッチ市場での高い技術力という強み
- 大手企業とのシナジー効果
- 従業員への丁寧な説明と雇用維持への配慮
- 買収後の円滑な経営統合
創業100年の老舗和菓子メーカーB社は、伝統的な製法を守りつつも、近年は売上減少に悩んでいました。後継者も不在であったため、事業の継続が困難な状況でした。そこでB社は、異業種である食品商社C社とのM&Aによる地位承継を選択しました。
C社はB社のブランド力と伝統的な製法に魅力を感じ、M&Aを決断。C社の持つ販売網とマーケティング力を活用することで、B社の和菓子は新たな顧客層を獲得することに成功しました。また、C社はB社の伝統的な製法を尊重し、職人の育成にも力を入れています。M&Aにより、B社は伝統を守りつつ新たな市場に挑戦する機会を得ることができました。
4.2.1 B社M&A成功のポイント- 老舗ブランドと伝統技術という強み
- 異業種とのシナジー効果による新たな市場開拓
- 伝統継承と革新のバランス
- 従業員のモチベーション維持と技能継承
地方で運送業を営むC社は、地域経済の活性化に貢献したいという強い思いを持っていました。しかし、経営者の高齢化と後継者不足により、事業継続が難しくなっていました。そこでC社は、同業で規模の大きいD社とのM&Aによる地位承継を検討しました。
D社はC社の地域密着型の経営姿勢と従業員の熱意を高く評価し、M&Aに合意しました。M&A後、C社はD社のネットワークと経営ノウハウを活用することで、事業を拡大することに成功しました。同時に、D社はC社の地域貢献活動を支援し、地元雇用の維持にも尽力しました。M&Aにより、C社は事業拡大と地域貢献の両立を実現しました。
4.3.1 C社M&A成功のポイント- 地域密着型の経営
- 従業員の地域貢献への意識の高さ
- M&A後の地域貢献活動の継続
- 大企業の経営資源を活用した事業拡大
| 企業 | 業種 | M&A相手 | 成功のポイント |
|---|---|---|---|
| A社 | 精密部品加工 | 同業大手企業B社 | 技術力、シナジー効果、雇用維持 |
| B社 | 和菓子製造 | 食品商社C社 | ブランド力、異業種シナジー、伝統継承 |
| C社 | 運送業 | 同業大規模企業D社 | 地域密着、地域貢献、事業拡大 |
これらの事例は、M&Aによる地位承継が、後継者不足の解消だけでなく、事業の成長や地域貢献にも繋がる可能性を示しています。それぞれの企業の状況に合わせた適切なM&A戦略を立てることが、成功への鍵となります。
5. M&Aによる地位承継の失敗事例M&Aによる地位承継は、後継者問題の解決や事業の成長といったメリットがある一方で、綿密な計画と実行が不可欠です。準備不足や認識の甘さから、M&Aが失敗に終わるケースも少なくありません。ここでは、M&Aによる地位承継の失敗事例を具体的に見ていき、失敗の要因と回避策を探ります。
5.1 事業統合の失敗M&A後の事業統合は、企業文化の違いや経営方針の相違、システム統合の難しさなど、様々な課題が潜んでいます。統合プロセスがスムーズに進まないと、シナジー効果の発揮はおろか、業績悪化や従業員のモチベーション低下に繋がる可能性があります。
【関連】PMIで失敗しないためのポイント|企業文化やシステム統合の落とし穴を解説5.1.1 事例:老舗和菓子メーカーC社と洋菓子メーカーD社の合併
老舗和菓子メーカーC社は、後継者不在の問題を解決するために、成長著しい洋菓子メーカーD社との合併を選びました。しかし、C社は伝統を重んじる職人気質、D社はデータに基づいたマーケティング重視という、全く異なる企業文化を持っていました。この違いを埋めることができず、意思決定の遅延、ブランドイメージの混乱、従業員間の対立などが発生。結果として、合併によるシナジー効果は生まれず、業績は低迷しました。
失敗要因:企業文化の相違、統合プロセスの不備、相互理解の不足
回避策:M&A前の綿密なデューデリジェンス、統合計画の策定、文化融合のための研修実施、相互理解を深めるためのコミュニケーション促進
5.1.2 事例:地方スーパーE社と全国チェーンF社の合併地方スーパーE社は、競争激化による業績悪化を打開するため、全国チェーンF社にM&Aを申し入れ、承諾されました。F社はE社の物流網と地域密着のノウハウを取り込み、地方展開を強化しようとしましたが、E社の古いシステムとF社の最新システムとの統合に膨大なコストと時間がかかりました。また、E社の従業員はF社のシステムに馴染めず、業務効率が低下。結果として、想定していたコスト削減効果は得られず、E社の店舗は次々と閉鎖に追い込まれました。
失敗要因:システム統合の困難さ、コストの見積もり不足、従業員への研修不足
回避策:システム統合の事前検証、費用対効果の綿密な分析、従業員への十分な研修、段階的なシステム統合
5.2 従業員との軋轢M&Aは、従業員の雇用や待遇に大きな影響を与える可能性があります。そのため、M&Aプロセスにおける情報共有やコミュニケーション不足は、従業員の不安や不信感を増幅させ、反発や退職に繋がる可能性があります。
5.2.1 事例:IT企業G社によるベンチャー企業H社の買収成長を続けるIT企業G社は、革新的な技術を持つベンチャー企業H社を買収しました。しかし、G社はH社の自由な企業文化を尊重せず、自社のルールや制度を一方的に押し付けました。結果として、H社の優秀なエンジニアは次々と退職し、買収の目的であった技術革新は実現しませんでした。
失敗要因:企業文化の軽視、コミュニケーション不足、従業員のモチベーション低下
回避策:買収後の企業文化のすり合わせ、従業員への丁寧な説明、適切な人事制度の構築
5.2.2 事例:老舗旅館I社による同業J社の買収老舗旅館I社は、事業拡大を目的として同業のJ社を買収しました。しかし、I社はJ社の従業員の処遇を軽視し、賃金カットや配置転換を一方的に通達。これにより、J社の従業員のモチベーションは大きく低下し、サービスの質が低下。顧客離れを引き起こし、業績は悪化しました。
失敗要因:従業員軽視、一方的な処遇変更、従業員のモチベーション低下
回避策:従業員との丁寧な交渉、公正な処遇、従業員のモチベーション維持のための施策実施
| 失敗事例 | 失敗要因 | 回避策 |
|---|---|---|
| 和菓子メーカーC社と洋菓子メーカーD社の合併 | 企業文化の相違、統合プロセスの不備 | デューデリジェンス、文化融合のための研修 |
| 地方スーパーE社と全国チェーンF社の合併 | システム統合の困難さ、コストの見積もり不足 | システム統合の事前検証、費用対効果の分析 |
| IT企業G社によるベンチャー企業H社の買収 | 企業文化の軽視、コミュニケーション不足 | 企業文化のすり合わせ、従業員への丁寧な説明 |
| 老舗旅館I社による同業J社の買収 | 従業員軽視、一方的な処遇変更 | 従業員との丁寧な交渉、公正な処遇 |
これらの事例からわかるように、M&Aによる地位承継を成功させるためには、事前の綿密な計画と、買収後の丁寧な統合プロセスが不可欠です。企業文化の違いや従業員への影響を考慮し、適切な対策を講じることで、M&Aによる地位承継の失敗リスクを軽減することができます。
6. まとめM&Aによる地位承継は、後継者不足や経営者の高齢化といった課題を抱える企業にとって、事業継続の有効な手段となり得ます。メリットとしては、事業の永続性確保、従業員の雇用維持、取引先の安心感などが挙げられます。一方で、経営権の喪失や企業文化の変化といったデメリットも存在します。
サントリーホールディングスによる寿屋(現サントリースピリッツ)買収のように、シナジー効果で成功を収める事例もあれば、経営方針の違いから統合に失敗するケースもあるため、綿密な計画と双方の理解が不可欠です。M&Aによる地位承継は、メリット・デメリットを理解した上で、慎重に進めるべきと言えるでしょう。


