事業承継で会社を従業員に引き継ぐ際の注意点|円滑な移行のための10個のポイント
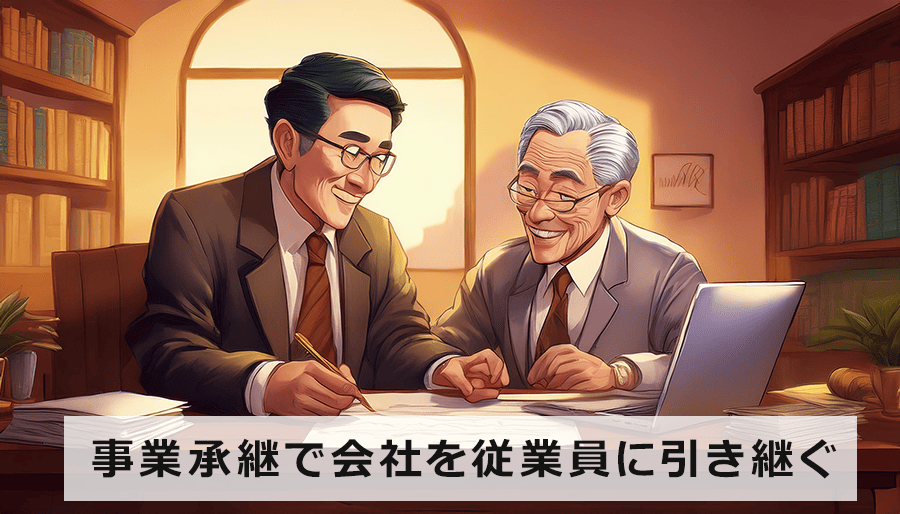
事業承継を従業員に引き継ぐことを検討しているが、何から始めたら良いのか分からない、スムーズな引き継ぎのために必要な手続きや注意点を理解したい、といった悩みを抱えていませんか?この記事では、従業員承継のメリット・デメリット、他の承継方法との比較、具体的な手順、発生するコスト、そして円滑な移行のための10個のポイントを解説します。
さらに、事業承継後に起こりうるトラブルと対策についても言及することで、安心して事業承継を進められるようサポートします。この記事を読むことで、従業員承継に関する全体像を把握し、成功へと導くための具体的な方法を理解することができます。結果として、円滑な事業承継を実現し、企業の永続的な発展と従業員の雇用を守ることができるでしょう。
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月のPMIにて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. 従業員への事業承継とは
従業員への事業承継とは、経営者が後継者として従業員を選び、会社経営の全権を譲渡する事業承継の方法です。後継者不足に悩む中小企業にとって、事業を継続し、雇用を守る有効な手段として注目されています。親族や社外への承継とは異なり、会社の文化や理念を理解している従業員が承継することで、社内への混乱を最小限に抑え、スムーズな移行を実現できる可能性が高まります。具体的には、株式譲渡、事業譲渡、合併などの手法を用いて、経営権と事業資産を従業員に引き継ぎます。
1.1 従業員承継のメリット・デメリット
従業員承継には、他の承継方法と比較して独自のメリット・デメリットが存在します。承継方法を検討する際には、これらの点を十分に理解しておくことが重要です。
1.1.1 メリット| 社内事情に精通した人材による承継で、スムーズな事業の継続が可能 | |
| 社風が維持されやすく、従業員の雇用維持にも繋がる | |
| 親族外承継に比べて、承継コストを抑えられる可能性がある | |
| M&Aに比べて、経営理念や企業文化を守りやすい | |
| 後継者候補の育成期間を長く取ることができ、じっくりと経営ノウハウを伝授できる | |
| 従業員のモチベーション向上や、優秀な人材の確保に繋がる可能性がある |
| 後継者候補となる従業員に、経営能力や資金力が不足している場合がある | |
| 承継後に、経営方針の変更に伴う社内調整が必要となるケースもある | |
| 後継者候補の選定において、社内での不公平感や対立が生じる可能性がある | |
| 親族内承継と比較して、経営の安定性に欠けるリスクがある場合もある | |
| 後継者候補の育成に時間がかかり、その間に経営環境が変化する可能性がある | |
| 資金調達に苦労する場合があり、金融機関からの融資を受けにくくなるケースもある |
1.2 他の事業承継方法との比較(親族内承継、M&Aなど)
事業承継には、従業員承継以外にも様々な方法があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社に最適な方法を選択することが重要です。
| 承継方法 | メリット | デメリット | 向いている企業 |
|---|---|---|---|
| 親族内承継 | スムーズな承継、経営理念の継承 | 後継者候補の能力不足、親族間の紛争リスク | 後継者となる親族に経営能力があり、円満な関係を築けている企業 |
| M&A | 事業の早期売却、高額な売却益、従業員の雇用維持 | 企業文化の変化、従業員の反発、デューデリジェンスの負担 | 早期に事業を売却したい、事業拡大を目指す企業とのシナジー効果を期待する企業 |
| 従業員承継 | 社内事情の理解、円滑な事業継続、従業員のモチベーション向上 | 後継者候補の経営能力不足、資金調達の難しさ、社内調整の必要性 | 後継者候補となる優秀な従業員がおり、社内での協力体制が整っている企業 |
上記の表は代表的な例であり、それぞれの状況によってメリット・デメリットは変化します。例えば、M&Aにおいては、事業の拡大や新たな市場への進出を目的とする場合もあります。また、親族内承継においても、経営ノウハウの継承や、一族経営による迅速な意思決定といったメリットが挙げられます。
自社の状況、経営理念、将来展望などを総合的に考慮し、最適な承継方法を選択することが重要です。中小企業庁や商工会議所、地域の金融機関など、事業承継に関する相談窓口を活用することも有効です。
2. 事業承継を従業員に引き継ぐ際の手順
従業員への事業承継は、複雑なプロセスであり、綿密な計画と実行が必要です。円滑な承継を実現するためには、以下の手順を踏むことが重要です。
2.1 1. 後継者候補の選定
事業を承継できる適切な人材を選定します。経営能力、事業への理解、人望などを考慮し、将来の経営者としてふさわしい人物を選びましょう。単なる人気投票ではなく、客観的な評価基準を設けることが重要です。
2.2 2. 承継スキームの決定
株式譲渡、事業譲渡など、様々な承継スキームが存在します。会社の規模、後継者の資金力、将来のビジョンなどを考慮し、最適な方法を選択します。税理士や弁護士などの専門家と相談しながら決定することが重要です。
| スキーム | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 事業の継続性が保たれる | 後継者の資金負担が大きい |
| 事業譲渡 | 必要な事業のみを引き継げる | 取引先との契約変更が必要な場合がある |
2.3 3. 事業計画の策定
後継者主導で、将来の事業計画を策定します。現状分析、目標設定、具体的な施策などを明確にし、実現可能な計画を立てましょう。既存事業の継続だけでなく、新規事業展開の可能性も検討することが重要です。
2.4 4. 資金調達の準備
事業承継には、株式取得費用、設備投資費用など、多額の資金が必要となる場合があります。日本政策金融公庫や信用金庫などからの融資、自己資金などを活用し、資金調達計画を立てましょう。資金調達方法によっては、事業計画の妥当性が問われるため、綿密な準備が必要です。
【関連】【M&A専門家解説】資金調達の方法・種類とは?|最適な選択肢を徹底解説2.5 5. 従業員への周知と合意形成
事業承継について、従業員に丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要です。承継後の経営方針、雇用条件などを明確に伝え、不安を取り除きましょう。従業員のモチベーション維持は、事業の継続に不可欠です。
2.6 6. 引継ぎの実施
経営ノウハウ、顧客情報、取引先との関係など、事業に関するあらゆる情報を後継者に引き継ぎます。一定期間、現経営者と後継者が共に業務を行い、スムーズな移行を図ることが重要です。引継ぎ期間中は、後継者の判断を尊重しつつ、適切なアドバイスを行うようにしましょう。
2.6.1 引継ぎ項目の例| 経営理念、ビジョン | |
| 事業計画、財務状況 | |
| 顧客情報、取引先との関係 | |
| 社内規定、業務フロー | |
| 技術、ノウハウ |
2.7 7. 関係機関への手続き
税務署、都道府県、社会保険事務所など、関係機関への必要な手続きを行います。手続きの種類や方法は、承継スキームによって異なるため、事前に確認しておきましょう。専門家のサポートを受けることで、手続きの漏れやミスを防ぐことができます。
2.8 8. 事業承継後のサポート
事業承継後も、一定期間は現経営者が後継者をサポートすることが重要です。経営上の相談に乗ったり、取引先との関係構築を支援したりすることで、後継者の経営基盤を強化しましょう。また、必要に応じて、経営コンサルタントなどの外部専門家の活用も検討しましょう。
これらの手順を踏むことで、円滑な事業承継を実現し、企業の持続的な成長を図ることができます。常に状況の変化に対応しながら、柔軟な対応を心がけましょう。
3. 事業承継における従業員への引き継ぎで発生するコスト
従業員への事業承継は、他の承継方法と比較してコスト面で有利な点が多い一方で、特有のコストが発生することもあります。スムーズな事業承継のためには、事前に発生するコストの種類や相場を把握し、適切な資金計画を立てることが重要です。
3.1 主なコストの種類と相場
従業員承継における主なコストは以下の通りです。それぞれの相場は、事業規模や後継者の状況、専門家への依頼内容などによって大きく変動します。
| コストの種類 | 内容 | 相場 |
|---|---|---|
| 後継者育成費用 | 経営に関する研修、資格取得費用、外部セミナー参加費用など | 数十万円~数百万円 |
| コンサルティング費用 | 事業承継計画策定支援、事業デューデリジェンス、バリュエーション評価など | 数十万円~数百万円 |
| 株式取得費用(MBOの場合) | 後継者が株式を取得するための費用。自己資金、金融機関からの融資、投資ファンドからの出資など様々な方法があります。 | 事業規模による |
| 融資関連費用 | 保証料、事務手数料など | 融資額に応じて変動 |
| 専門家費用 | 税理士、弁護士、司法書士などへの報酬 | 数十万円~数百万円 |
| 登記費用 | 代表者変更、株式譲渡などに関する登記費用 | 数万円~数十万円 |
| 従業員への周知費用 | 説明会開催費用、資料作成費用など | 数万円~数十万円 |
| 事業承継後の設備投資費用 | 事業承継後に、老朽化した設備の更新や新規設備の導入が必要になる場合があります。 | 事業規模による |
| 運転資金 | 事業承継後、円滑に事業を運営するための運転資金。仕入代金、人件費、販管費などに充当されます。 | 事業規模による |
3.2 コストを抑えるための方法
事業承継にかかるコストを抑えるためには、以下の方法が考えられます。
| 後継者育成を早期に開始することで、外部研修の必要性を減らす | |
| 補助金や助成金を活用する(事業承継補助金、経営革新計画承認による税制優遇など) | |
| 複数の専門家に相見積もりを取る | |
| 日本政策金融公庫や信用金庫など、公的金融機関の低利融資制度を活用する | |
| 自力でできる手続きは自身で行う | |
| 段階的に事業承継を進めることで、一度にかかるコストを軽減する |
これらの方法を組み合わせることで、コスト負担を軽減しながら、スムーズな事業承継を実現することが可能になります。綿密な計画と準備が成功の鍵となります。
4. 円滑な事業承継のための従業員への引き継ぎの注意点10個
従業員への事業承継を成功させるためには、綿密な計画と適切な実行が必要です。円滑な事業承継を実現するための10個の注意点を詳しく解説します。
4.1 後継者候補の選定と育成を早期に開始する
後継者候補の選定は事業承継の成否を大きく左右します。単に能力が高いだけでなく、経営理念への共感、リーダーシップ、コミュニケーション能力、変化への対応力などを総合的に評価し、適切な人材を選びましょう。選定後は、経営ノウハウの伝授、研修、OJTなどを通じて計画的に育成していくことが重要です。後継者候補の育成には時間を要するため、5年以上前から準備を始めると良いでしょう。
4.2 経営理念、ビジョン、ノウハウの明確化と共有
承継される側が事業を滞りなく継続していくためには、経営理念、ビジョン、事業ノウハウなどを明確化し、文書化、共有することが不可欠です。暗黙知となっているノウハウは、可能な限り形式知に変換し、後継者を含む従業員に共有することで、スムーズな事業承継を実現できます。社内Wikiやマニュアルなどを活用し、情報共有の仕組みを構築しましょう。
4.3 事業計画、財務状況などの情報開示
後継者候補や従業員に、会社の現状と将来展望を理解してもらうためには、事業計画、財務状況、取引先情報などを適切に開示する必要があります。透明性の高い情報開示は、従業員の不安解消と、事業承継への協力姿勢を促すことに繋がります。情報開示の範囲や時期については、専門家のアドバイスを受けることも有効です。
4.4 従業員とのコミュニケーションと合意形成
事業承継は、経営者や後継者だけでなく、従業員全体にとって大きな変化です。従業員の不安や疑問に真摯に向き合い、丁寧な説明とコミュニケーションを図ることで、円滑な事業承継を実現できます。従業員代表との定期的な面談や、説明会の開催なども有効です。
4.5 引継ぎ期間の設定とスケジュール管理
円滑な引継ぎのためには、十分な期間を設け、綿密なスケジュールを立てて進める必要があります。業務内容の複雑さや後継者の経験値などを考慮し、適切な引継ぎ期間を設定しましょう。引継ぎ項目ごとに責任者と期限を明確にし、進捗状況を定期的に確認することで、漏れや遅延を防ぎます。
4.6 従業員向け研修の実施とスキルの向上
後継者だけでなく、従業員全体のスキルアップも事業承継の成功には不可欠です。後継者育成のための研修プログラムに加え、従業員向けの研修制度を導入し、スキルアップを支援することで、組織全体の能力向上を図りましょう。外部機関の研修や資格取得支援制度などを活用することも有効です。
4.7 資金調達方法の検討と準備(日本政策金融公庫、信用金庫など)
事業承継には、株式取得費用や設備投資など、多額の資金が必要となる場合があります。日本政策金融公庫や信用金庫、民間金融機関など、様々な資金調達方法を検討し、事前に準備しておくことが重要です。それぞれの金融機関の融資条件やメリット・デメリットを比較し、自社に最適な方法を選びましょう。
4.8 専門家(税理士、弁護士など)の活用
事業承継は複雑な手続きを伴うため、税理士、弁護士、M&Aアドバイザーなど、専門家のサポートを受けることが重要です。専門家は、税務・法務・財務などの専門知識に基づいたアドバイスを提供し、手続きをスムーズに進めるサポートをしてくれます。費用対効果を考慮しながら、必要な専門家を選びましょう。
4.9 関係機関(税務署、都道府県など)への手続き
事業承継には、税務署、都道府県、市町村など、関係機関への様々な手続きが必要です。手続きの種類や必要書類、提出期限などを事前に確認し、漏れなく対応することで、後々のトラブルを回避できます。専門家に依頼することで、手続きの負担を軽減することも可能です。
4.10 事業承継後のサポート体制の構築
事業承継は、引継ぎが完了した時点がゴールではありません。後継者がスムーズに経営を引き継ぎ、事業を成長させていくためには、事業承継後のサポート体制が重要です。前経営者や専門家による継続的なアドバイスや、従業員に対するフォローアップ体制を構築することで、新体制への移行を支援しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 後継者育成 | 経営ノウハウの伝授、研修、OJT、メンタリング |
| 従業員支援 | スキルアップ研修、キャリア相談、メンタルヘルスサポート |
| 専門家支援 | 税務・法務・財務相談、経営コンサルティング |
5. 事業承継後に起こりうるトラブルと対策
事業承継は、後継者に経営の舵取りをバトンタッチする重要なプロセスですが、承継後にも様々なトラブルが発生する可能性があります。事前に想定されるトラブルと対応策を理解しておくことで、スムーズな事業の継続と発展を実現できるでしょう。
5.1 想定されるトラブル事例
事業承継後に起こりうるトラブルは多岐にわたります。代表的な事例を以下に示します。
| トラブルの種類 | 内容 | 発生要因 |
|---|---|---|
| 経営方針の対立 | 後継者と先代経営者、あるいは従業員との間で経営方針に関する意見の相違が生じる。 | 承継前の十分なコミュニケーション不足、経営理念の共有不足、後継者への権限委譲の遅れ |
| 業績悪化 | 市場環境の変化、競争激化、後継者の経営手腕不足などにより、売上が減少、利益が低下する。 | 事業環境分析の不足、後継者への適切な経営指導の不足、事業計画の策定不備 |
| 従業員の離職 | 後継者への不信感、経営方針の変化、待遇への不満などから、従業員が退職する。特に、先代経営者と強い信頼関係にあったベテラン従業員の離職は、事業に大きな影響を与える可能性がある。 | 後継者と従業員間のコミュニケーション不足、待遇面での変更、企業文化の変化への対応不足 |
| 顧客の離反 | 後継者への交代による企業イメージの変化、サービス品質の低下などを理由に、顧客が取引を停止する。 | 顧客への丁寧な説明不足、サービス品質の維持・向上への取り組み不足、後継者による顧客関係の構築不足 |
| 資金繰りの悪化 | 売上の減少、設備投資の失敗、借入金の返済負担などにより、資金繰りが悪化する。 | 資金調達計画の不備、財務管理の甘さ、事業計画の実行状況の把握不足 |
| 取引先とのトラブル | 後継者への交代による取引条件の見直し、契約内容の変更などにより、取引先との関係が悪化する。 | 取引先との十分な協議不足、契約内容の理解不足、後継者による取引先との関係構築不足 |
| 親族間の紛争 | 後継者選定や財産分与などを巡り、親族間で対立が生じる。特に、株式の分散などにより経営権が不安定な場合は、紛争が深刻化する可能性がある。 | 承継計画の策定不足、親族間のコミュニケーション不足、公平な財産分与の実施不足 |
5.2 トラブル発生時の対応策
トラブル発生時には、迅速かつ適切な対応が求められます。主な対応策は以下の通りです。
| トラブルの種類 | 対応策 |
|---|---|
| 経営方針の対立 | 関係者間で十分な話し合いを行い、相互理解を深める。経営理念やビジョンを再確認し、共通の目標を設定する。必要に応じて、外部の専門家(コンサルタントなど)の助言を求める。 |
| 業績悪化 | 市場環境や競合状況を改めて分析し、事業計画の見直しを行う。コスト削減や新規事業の開発など、業績回復に向けた施策を迅速に実行する。必要に応じて、金融機関からの融資を受けるなど、資金繰りを安定させる。 |
| 従業員の離職 | 従業員とのコミュニケーションを密にし、後継者への理解と協力を求める。待遇改善やキャリアアップの機会提供など、従業員のモチベーション向上に努める。退職希望者には、誠意をもって対応し、円満な退職を促す。 |
| 顧客の離反 | 顧客への丁寧な説明を行い、後継者体制への理解と信頼を得る。サービス品質の維持・向上に努め、顧客満足度を高める。顧客の声に耳を傾け、ニーズに合わせたサービスを提供する。 |
| 資金繰りの悪化 | 金融機関との交渉を行い、借入金の返済条件の変更や新規融資を検討する。不要な資産の売却や経費削減など、資金繰りの改善に努める。事業計画を見直し、収益性の向上を目指す。 |
| 取引先とのトラブル | 取引先との関係修復に努め、信頼関係を再構築する。契約内容を改めて確認し、相互に納得できる条件で合意形成を図る。後継者による取引先との良好な関係構築を支援する。 |
| 親族間の紛争 | 親族間で話し合いの場を設け、相互理解と歩み寄りを促す。弁護士や税理士などの専門家の仲介により、紛争の解決を図る。家憲や株主間契約などを整備し、紛争の予防策を講じる。 |
これらのトラブルは、事業承継後に発生する可能性のある代表的な例です。事業の規模や業種、後継者の状況などによって、発生するトラブルやその対応策は異なります。事業承継を成功させるためには、事前に想定されるトラブルを洗い出し、適切な対応策を準備しておくことが重要です。また、専門家(弁護士、税理士、コンサルタントなど)のアドバイスを受けることで、よりスムーズな事業承継を実現できるでしょう。
【関連】後継者不足に悩む中小企業必見!M&Aで事業承継を成功させる解決策とは?6. まとめ
従業員への事業承継は、後継者不足の解消、企業文化の継承、従業員のモチベーション向上といったメリットがある一方で、資金調達や経営能力の不足といったデメリットも存在します。親族内承継やM&Aといった他の承継方法と比較検討し、自社に最適な方法を選択することが重要です。
円滑な事業承継を実現するためには、後継者候補の早期選定・育成、経営理念やノウハウの共有、事業計画等の情報開示、従業員とのコミュニケーション、引継ぎ期間の設定、研修の実施、資金調達方法の検討、専門家の活用、関係機関への手続き、事業承継後のサポート体制構築といった10個のポイントに留意する必要があります。これらのポイントを踏まえることで、承継リスクを軽減し、スムーズな事業の移行を実現できるでしょう。
事業承継後には、経営方針の変更に伴う従業員の反発や、想定外の業績悪化といったトラブルが発生する可能性があります。これらのトラブル発生時の対応策を事前に準備しておくことで、迅速かつ適切な対応が可能となり、事業の安定的な継続に繋がります。従業員への事業承継は、入念な準備と計画的な実行によって、企業の持続的な成長を実現するための有効な手段となるでしょう。
【関連】企業の経営者が考えるべき事業承継の準備

