M&A譲渡価格の決め方|中小企業M&Aで成功するための価格交渉戦略
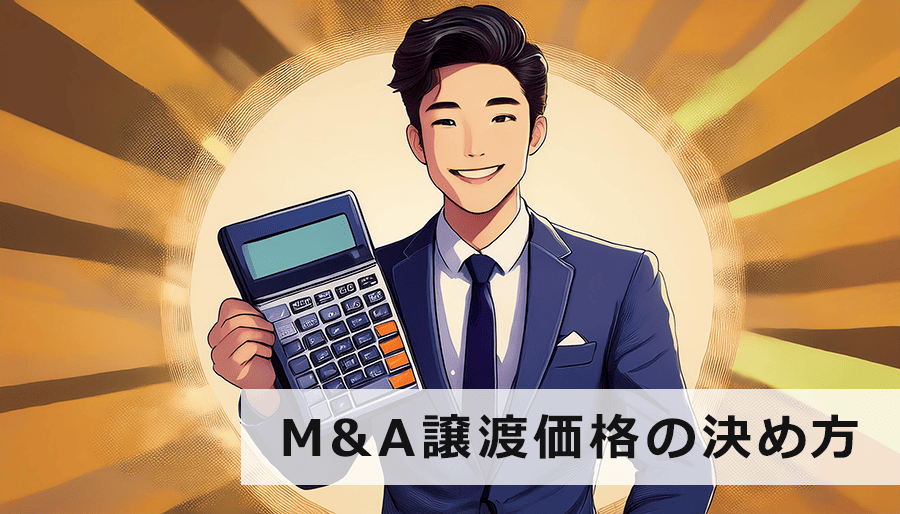
M&Aの譲渡価格ってどうやって決まるの? この記事では、M&A、特に中小企業M&Aにおける譲渡価格の決め方を徹底解説します。DCF法、純資産法、類似会社比較法といった代表的な算定方法はもちろん、中小企業M&Aで実際に使われている方法にも触れ、会社の業績や将来性、市場環境、買い手のニーズといった価格に影響する要因を分かりやすく説明します。
さらに、事業承継や後継者不在といった中小企業特有の事情が価格にどう影響するか、そしてM&Aアドバイザーの活用やデューデリジェンスの重要性といった交渉戦略まで、M&Aを成功に導くための価格交渉の全てを網羅。この記事を読めば、M&A譲渡価格の決定プロセスを理解し、有利な交渉を進めるための知識を得ることができます。
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. M&A譲渡価格の算定方法
M&Aにおける譲渡価格は、会社の価値を適切に評価し、売手と買手の双方が納得できる価格で取引を成立させるために非常に重要です。譲渡価格の算定には様々な方法があり、会社の規模や業種、取引の目的などによって適切な方法を選択する必要があります。ここでは、代表的な算定方法と、中小企業M&Aでよく使われる算定方法について解説します。
【関連】M&AにおけるEBITDAとは?企業価値算定を理解する1.1 代表的なM&A譲渡価格の算定方法3選
M&Aにおいて代表的な譲渡価格の算定方法は、以下の3つです。
1.1.1 DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)DCF法は、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて会社の価値を算定する方法です。将来のキャッシュフローを予測するため、会社の事業計画や財務諸表などを分析する必要があります。割引率は、事業リスクや市場環境などを考慮して決定されます。
DCF法は、会社の将来性を重視した評価方法であり、成長性の高い企業のM&Aでよく用いられます。一方で、将来のキャッシュフローの予測が難しく、割引率の設定に専門的な知識が必要となるため、中小企業のM&Aでは必ずしも最適な方法とは言えません。
純資産法は、会社の資産から負債を差し引いた純資産額を会社の価値とする方法です。貸借対照表に基づいて算定するため、比較的容易に計算できます。しかし、会社の将来性や収益力は考慮されないため、収益性の低い企業や解散を前提としたM&Aで用いられることが多いです。中小企業のM&Aにおいては、簡易的な評価方法として用いられる場合もありますが、会社の真の価値を反映しているとは限りません。
1.1.3 類似会社比較法類似会社比較法は、同業種の上場企業の株価や財務指標を参考に、対象企業の価値を算定する方法です。類似上場会社のPER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、EV/EBITDA倍率などの指標を用いて、対象企業の価値を推定します。
市場における評価を反映した客観的な評価が可能ですが、適切な類似会社を選定することが重要であり、非上場企業の場合は財務情報の入手が難しい場合もあります。中小企業のM&Aでは、類似上場企業が少ない場合や、財務情報が限定的な場合があり、適用が難しいケースもあります。
1.2 中小企業M&Aでよく使われる算定方法
中小企業のM&Aでは、上記の代表的な3つの算定方法に加えて、あるいは組み合わせて、以下の方法もよく用いられます。
| 方法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 粗利益倍率法 | 過去の粗利益の実績に基づき、一定の倍率を掛けて算定する方法 | 簡易で分かりやすい | 将来性や収益構造の変化を反映しにくい |
| EBITDA倍率法 | EBITDA(利払い前・税引き前・減価償却費前利益)に一定の倍率を掛けて算定する方法 | 事業の収益力を反映しやすい | 設備投資の状況などを考慮しにくい |
| 調整純資産法 | 純資産法をベースに、簿価と時価の乖離を調整する方法 | 純資産法よりも実態に即した評価が可能 | 資産評価の専門知識が必要 |
これらの算定方法は、会社の規模や業種、取引の目的などによって使い分けられます。複数の方法を組み合わせて用いることで、より精緻な評価が可能となります。M&Aアドバイザーに相談することで、最適な算定方法を選択し、適切な譲渡価格を決定することができます。
【関連】M&Aで企業価値評価(バリュエーション)3つの算定方法2. M&A譲渡価格を左右する要因
M&Aにおける譲渡価格は、様々な要因が複雑に絡み合って決定されます。ここでは、価格に影響を与える主要な要因を詳しく解説します。
2.1 会社の業績
会社の業績は、譲渡価格を決定する上で最も重要な要素の一つです。過去数年間の売上高、利益、キャッシュフローなどの財務指標は、会社の収益性を示す重要な指標となり、買い手はこれらの指標を基に将来の収益性を予測します。安定した成長を示す企業は、高い評価を受けやすい傾向にあります。
具体的には、以下の指標が重視されます。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| 売上高 | 企業の収益規模を示す指標 |
| 営業利益 | 本業の収益性を示す指標 |
| 経常利益 | 企業の通常の営業活動による収益性を示す指標 |
| 純利益 | 企業の最終的な利益を示す指標 |
| EBITDA | 利払い・税引き・償却前利益。企業の収益力を示す指標 |
| ROA(総資産利益率) | 企業の資産効率を示す指標 |
| ROE(自己資本利益率) | 株主資本に対する収益性を示す指標 |
2.2 会社の将来性
過去の業績だけでなく、将来の成長性も譲渡価格に大きく影響します。市場の成長性、競争優位性、経営陣の能力、新規事業の展開など、将来の収益に繋がる要素は高く評価されます。特に、独自の技術や特許、強力なブランド力、安定した顧客基盤などは、将来の収益を予測する上で重要な要素となります。
将来性を評価する際のポイントは以下の通りです。
| 市場の成長性 | 市場全体の成長が見込まれるか |
|---|---|
| 競争優位性 | 競合他社に対する優位性はあるか |
| 経営陣の能力 | 優秀な経営陣が揃っているか |
| 技術力・開発力 | 将来の成長を支える技術力があるか |
| 事業の多角化 | リスク分散のための多角化戦略 |
2.3 市場環境
M&Aが行われる市場環境も、譲渡価格に影響を与えます。景気動向、業界の成長性、金利水準、競合他社のM&A事例などは、譲渡価格の妥当性を判断する上で重要な要素となります。例えば、業界全体のM&Aが活発な時期は、譲渡価格が上昇する傾向にあります。
市場環境を分析する上での具体的なポイントは下記の通りです。
| マクロ経済指標 | GDP成長率、金利、為替レート |
|---|---|
| 業界動向 | 業界の成長性、競争環境、規制 |
| 競合他社のM&A事例 | 類似企業の買収事例 |
| 株式市場の動向 | 株式市場全体のトレンド |
2.4 買い手のニーズ
買い手のニーズも、譲渡価格に影響を与える重要な要素です。例えば、事業シナジー効果を期待する買い手は、相乗効果による将来的な利益増加を見込んで、高めの価格を提示する可能性があります。
また、事業ポートフォリオの拡充や新規市場への参入を目的とする買い手も、戦略的な重要性に応じて高めの価格を提示することがあります。買収後の経営方針や統合プロセスなども、価格交渉に影響を与えます。
買い手のニーズを分析するポイントは下記の通りです。
| シナジー効果 | 買収による相乗効果 |
|---|---|
| 戦略的適合性 | 買い手の事業戦略との整合性 |
| 財務状況 | 買い手の資金力 |
| 買収後の経営方針 | 統合プロセス、経営陣の交代 |
3. 中小企業M&A特有の譲渡価格決定のポイント
中小企業のM&Aは、大企業のM&Aとは異なる特有の事情を考慮する必要があります。譲渡価格の決定においても、これらの事情が大きく影響します。ここでは、中小企業M&A特有の譲渡価格決定のポイントを解説します。
【関連】スモールM&Aで企業価値を最大化する方法3.1 事業承継におけるM&A譲渡価格の考え方
中小企業のM&Aの多くは、後継者不足による事業承継を目的として行われます。この場合、譲渡価格は単なる会社の資産価値だけでなく、創業者や経営者の想いや従業員の雇用維持といった要素も考慮されるべきです。譲渡価格が低すぎると、これまでの経営努力が正当に評価されなかったり、従業員の雇用が不安定になる可能性があります。
一方で、高すぎると買い手が見つかりにくくなる可能性があります。適切な譲渡価格は、事業の継続性と従業員の雇用を守りつつ、売却後の生活も保障できる水準であるべきです。そのため、M&Aアドバイザーと相談しながら、双方が納得できる価格を模索することが重要です。
事業承継を目的としたM&Aでは、株式の買取だけでなく、事業の一部譲渡や合併といったスキームも検討されます。それぞれのスキームによって譲渡価格の算定方法や考慮すべき点が異なるため、専門家との綿密な協議が必要です。例えば、株式譲渡の場合は会社の純資産価値や将来収益力などが重視される一方、事業譲渡の場合は譲渡対象となる事業部門の収益力や資産価値が評価の対象となります。
3.2 後継者不在問題におけるM&A譲渡価格への影響
後継者不在は、中小企業のM&Aを推進する大きな要因の一つです。後継者が見つからない場合、廃業という選択肢も考えられますが、M&Aによって事業を存続させる道も開けます。
ただし、後継者不在を理由にM&Aを急ぐあまり、譲渡価格を低く設定してしまうと、売却後に後悔する可能性があります。後継者不在という状況を買い手に利用されないよう、冷静に市場価値を分析し、適正な価格で交渉することが大切です。
後継者不在の場合、事業の継続性を重視するあまり、譲渡価格よりも買い手の経営方針や従業員の雇用維持を優先するケースも見られます。譲渡価格だけでなく、自社の理念や文化を理解し、尊重してくれる買い手を選ぶことが、長期的な企業価値の向上につながります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業の将来性 | 成長性が高い事業は、高めの譲渡価格が期待できます。市場動向や競争環境、技術革新などを分析し、将来の収益性を予測することが重要です。 |
| 財務状況 | 健全な財務状況は、買い手にとって魅力的であり、譲渡価格にもプラスに影響します。負債の状況やキャッシュフローなども考慮されます。 |
| 顧客基盤 | 安定した顧客基盤は、事業の継続性を担保する重要な要素です。優良顧客の比率や顧客維持率なども評価の対象となります。 |
| 知的財産 | 特許や商標などの知的財産は、企業の競争優位性を高める重要な資産です。保有する知的財産の価値も譲渡価格に反映されます。 |
| 従業員のスキル | 優秀な従業員は、事業の成長を支える貴重な人材です。従業員のスキルや定着率も評価の対象となります。 |
これらの要素を総合的に考慮し、M&Aアドバイザーのサポートを受けながら、自社にとって最適な譲渡価格を決定することが重要です。焦らず、じっくりと交渉を進めることで、納得のいく結果を得られる可能性が高まります。
4. M&A譲渡価格の交渉戦略
M&Aにおける譲渡価格の交渉は、M&Aプロセスの中でも特に重要な局面です。適切な交渉戦略を立てることで、売主は希望価格に近い金額での譲渡を実現し、買主は適正価格での買収を実現することができます。
ここでは、M&A譲渡価格の交渉戦略について、M&Aアドバイザーの活用、デューデリジェンスの重要性、譲渡価格交渉の進め方、そして交渉における注意点の4つの観点から解説します。
4.1 M&Aアドバイザーの活用
M&Aアドバイザーは、M&Aに関する専門知識と豊富な経験を持つ専門家です。M&Aアドバイザーを活用することで、客観的な視点からの助言を得ることができ、より有利な条件での交渉を進めることができます。具体的には、以下のサポートが期待できます。
| 企業価値の算定 | |
| 最適な相手先の選定 | |
| 交渉戦略の立案・実行 | |
| 契約書作成・締結サポート | |
| デューデリジェンス支援 |
M&Aアドバイザーには、投資銀行、会計事務所、コンサルティングファームなどが挙げられます。それぞれの専門分野や得意とする業種・規模などが異なるため、自社の状況に合ったアドバイザーを選ぶことが重要です。
【関連】M&Aアドバイザーの選び方|中小企業経営者が知っておくべきポイント4.2 デューデリジェンスの重要性
デューデリジェンスとは、買収対象企業の財務状況、事業内容、法務状況などを詳細に調査するプロセスです。デューデリジェンスの結果は、譲渡価格の算定に大きな影響を与えます。売主は、デューデリジェンスで指摘される可能性のある問題点を事前に把握し、対策を講じておくことで、交渉を有利に進めることができます。
買主は、デューデリジェンスを通じて対象企業の価値を正確に評価し、適正な価格での買収を実現することができます。
デューデリジェンスの主な調査項目は以下の通りです。
| 調査項目 | 内容 |
|---|---|
| 財務デューデリジェンス | 財務諸表の分析、収益性・安全性・成長性の評価 |
| 事業デューデリジェンス | 事業内容、競争環境、市場シェア、将来性などの分析 |
| 法務デューデリジェンス | 契約書、許認可、訴訟リスクなどの調査 |
| 税務デューデリジェンス | 税務リスク、税務申告の正確性などの調査 |
| 人事デューデリジェンス | 従業員の状況、労務管理、退職金制度などの調査 |
4.3 譲渡価格交渉の進め方
譲渡価格の交渉は、売主と買主の間で行われます。M&Aアドバイザーが間に入る場合もあります。交渉は、双方が納得できる価格で合意することを目指して行われます。交渉の進め方としては、以下の点が重要です。
| 自社の希望価格を明確にする | |
| 相手方のニーズを理解する | |
| 根拠に基づいた価格提示を行う | |
| 柔軟な姿勢で交渉に臨む | |
| Win-Winの関係を築く |
4.4 交渉における注意点
譲渡価格の交渉においては、以下の点に注意する必要があります。
| 感情的にならない | |
| 契約内容をしっかりと確認する | |
| 専門家のアドバイスを仰ぐ | |
| 秘密保持契約を締結する | |
| 期限を設定する |
M&Aにおける譲渡価格の交渉は、複雑で時間のかかるプロセスです。しかし、適切な戦略と準備を行うことで、成功の可能性を高めることができます。M&Aアドバイザーの活用やデューデリジェンスの実施、そして交渉における注意点への配慮は、M&Aを成功させるための重要な要素となります。
5. M&A譲渡価格決定後の手続き
M&A譲渡価格が決定した後も、最終的な取引完了まではいくつかの重要な手続きが残されています。スムーズな事業承継・統合のためにも、これらの手続きをしっかりと理解し、適切に進めることが重要です。ここでは、価格決定後の主要な手続きと、その際に注意すべき点について解説します。
5.1 最終契約締結
譲渡価格をはじめとするM&Aの主要条件に合意したら、最終契約書を締結します。この契約書は、M&A取引における最終的な合意内容を網羅した法的拘束力のある文書です。内容に誤りや漏れがあると、後々大きなトラブルに発展する可能性があるため、細心の注意を払う必要があります。M&Aアドバイザーのサポートを受けながら、内容を慎重に確認することが重要です。
5.1.1 最終契約書の内容最終契約書には、以下のような項目が記載されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡価格 | 決定した譲渡価格 |
| 譲渡対象 | 譲渡する事業、資産、負債など |
| 譲渡日 | 事業の譲渡が行われる日付 |
| 表明保証 | 売主が買主に対して行う、会社の財務状況や事業内容に関する表明 |
| 契約解除条件 | 一定の条件下で契約を解除できる条項 |
| 競業避止義務 | 売主が一定期間、買主と競合する事業を行わない義務 |
| 従業員の処遇 | M&A後の従業員の雇用に関する取り決め |
最終契約締結時には、以下の点に注意が必要です。
| 契約書の内容を完全に理解すること | |
| 不明点があれば、M&Aアドバイザーに確認すること | |
| 将来のリスクを想定し、必要な条項を盛り込むこと |
5.2 クロージング
クロージングとは、最終契約に基づき、実際に事業や株式の譲渡が行われる最終段階のことです。譲渡代金の支払い、株式の移転、事業の引継ぎなどが行われます。クロージングをもって、M&A取引は完了となります。
5.2.1 クロージングの手続きクロージングでは、以下のような手続きが行われます。
| 譲渡代金の支払い | |
| 株式の移転登記 | |
| 事業の引継ぎ | |
| 従業員への説明 | |
| 取引先への通知 |
クロージング時には、以下のような点に注意が必要です。
| 最終契約書の内容に沿って手続きが行われているか確認すること | |
| 予期せぬ問題が発生した場合の対応策を事前に検討しておくこと | |
| 関係者への連絡を密に行い、スムーズな引継ぎを実現すること |
M&A譲渡価格決定後の手続きは、M&Aプロセスにおける最終段階であり、非常に重要なステップです。専門家であるM&Aアドバイザーの支援を受けながら、手続きを適切に進めることで、M&Aを成功裏に完了させることができるでしょう。特に、中小企業のM&Aにおいては、事業承継や後継者問題といった背景も考慮しながら、丁寧な手続きを進めることが重要となります。
6. まとめ
M&Aの譲渡価格は、DCF法、純資産法、類似会社比較法といった算定方法を参考に、会社の業績や将来性、市場環境、買い手のニーズなど様々な要因を考慮して決定されます。特に中小企業のM&Aでは、事業承継や後継者不在といった事情も価格に影響します。
M&Aを成功させるためには、M&Aアドバイザーの活用やデューデリジェンスの実施が重要です。譲渡価格の交渉は慎重に進め、最終契約締結、クロージングまでしっかりと手続きを進める必要があります。この記事で解説した内容を参考に、M&Aの譲渡価格について理解を深め、スムーズなM&Aを実現しましょう。


