M&Aの包括承継と個別承継を徹底比較!最適な承継方法の選び方
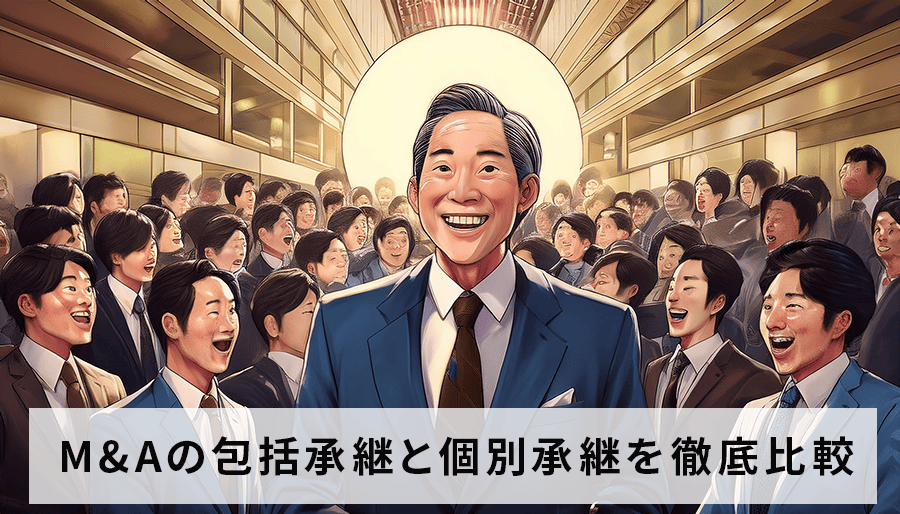
M&Aにおける「包括承継」と「個別承継」、どちらが最適か悩んでいませんか? この記事では、包括承継と個別承継の違いをメリット・デメリット、具体例を交えて徹底比較します。
それぞれの承継方法における注意点や、会社の規模、事業内容、M&Aの目的など、選択基準を明確化することで、最適な承継方法を導き出します。事業承継、合併、買収などM&A戦略を検討中の経営者や担当者必見の内容です。これを読めば、スムーズな事業承継、M&A実現のための道筋が見えてきます。
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. 包括承継とは
M&Aにおいて、対象会社の権利義務の一切を、包括的に承継会社が引き継ぐ方法を「包括承継」といいます。合併、会社分割、事業譲渡のうち合併と会社分割が包括承継の方法となります。対象会社のすべての資産、負債、契約、権利、義務などが、まるで一つのパッケージのようにまとめて承継されます。
これに対し、個別の資産や負債を選択的に承継する方法を「個別承継」といいます。事業譲渡は個別承継に該当します。包括承継では、対象会社の事業を丸ごと引き継ぐため、事業の継続性が保たれやすいというメリットがあります。
包括承継には、主に以下の2つの種類があります。
| 種類 | 説明 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 合併 | A社とB社が一つになり、A社またはB社、あるいは新たにC社を設立して存続会社とする方法です。消滅会社は解散します。 |
手続きが比較的簡素。 |
株主総会の特別決議が必要。 |
| 会社分割 | A社の一部の事業をB社に承継させる方法(吸収分割)と、A社の事業を分割して新たにB社、C社を設立する方法(新設分割)があります。 |
事業の選択と集中が可能。 |
手続きが複雑。 |
包括承継では、以下のものが承継されます。
- 資産:現金、預金、売掛金、有価証券、土地、建物、機械設備など
- 負債:借入金、買掛金、未払金など
- 契約:売買契約、賃貸借契約、雇用契約など
- 権利:特許権、商標権、著作権など
- 義務:債務保証、訴訟など
ただし、法律や契約で定められている場合など、例外的に承継されないものもあります。例えば、個人的な権利義務や、譲渡禁止特約が付された契約などは承継されない場合があります。
1.3 包括承継と個別承継の比較包括承継と個別承継の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 包括承継 | 個別承継 |
|---|---|---|
| 承継の範囲 | 権利義務の一切 | 特定の資産、負債等 |
| 手続き | 合併、会社分割 | 事業譲渡 |
| メリット | 事業の継続性、手続きの簡素さ(合併の場合) | 柔軟な事業再編、不要な資産・負債の排除 |
| デメリット | 不要な資産・負債も承継、手続きの複雑さ(会社分割の場合) | 事業の継続性に課題、個別の契約承継手続きが必要 |
M&Aの際には、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に最適な方法を選択することが重要です。専門家への相談も有効です。
2. 個別承継とはM&Aにおける個別承継とは、対象会社の特定の資産や負債、権利義務などを個別に選択して譲り受ける方法です。包括承継のように会社全体を丸ごと引き継ぐのではなく、必要なものだけを「 cherry-picking(チェリーピッキング)」のように選別して取得します。
これにより、不要な資産や負債、潜在的なリスクを承継することを避け、買収後の経営の効率化やリスク軽減を図ることができます。ただし、個別に契約を締結する必要があるため、手続きが複雑になり、時間も費用もかかる傾向があります。
個別承継には、以下のようなメリットがあります。
- 不要な資産・負債の承継を回避できる
- 潜在的なリスクを限定できる
- 事業の選択と集中が可能になる
- 買収後の経営の効率化を図れる
個別承継には、以下のようなデメリットもあります。
- 手続きが複雑で時間と費用がかかる
- 契約交渉が難航する可能性がある
- 取引先との関係に悪影響を与える可能性がある
- 従業員のモチベーション低下につながる可能性がある
個別承継の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
| 種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 資産の個別承継 | 特定の資産のみを譲り受ける | 工場、機械設備、土地建物、特許権、商標権、ソフトウェア、顧客リストなど |
| 負債の個別承継 | 特定の負債のみを譲り受ける | 金融機関からの借入金、リース債務など |
| 契約の個別承継 | 特定の契約のみを譲り受ける | 重要な取引先との契約、リース契約、ライセンス契約など |
| 事業の個別承継 | 特定の事業部門のみを譲り受ける | 製造部門、販売部門、研究開発部門など |
例えば、ある会社が別の会社の工場と製造設備のみを取得する場合、これは資産の個別承継にあたります。また、特定の事業部門のみを買収する場合も、個別承継となります。さらに、特許権や商標権といった知的財産権のみを譲り受ける場合も、個別承継に該当します。
このように、個別承継は多様な形態を取り得るため、M&Aの目的や対象会社の状況に応じて、適切な方法を選択することが重要です。特に、事業譲渡契約においては、譲渡対象となる資産、負債、権利義務、契約などを明確に特定し、漏れや重複がないように注意深く契約書を作成する必要があります。
また、譲渡価格の算定やデューデリジェンスの実施についても、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
3. M&Aにおける包括承継と個別承継の選択基準
M&Aにおいて、事業を承継する方法は大きく分けて包括承継と個別承継の2種類があります。どちらの方法を選択するかは、M&Aの目的や対象事業の特性、法的・税務的な影響など、様々な要因を考慮して決定する必要があります。この章では、包括承継と個別承継の選択基準について詳しく解説します。
3.1 会社の規模と組織体制会社の規模や組織体制は、承継方法を選択する上で重要な要素となります。大規模な組織を持つ企業のM&Aでは、事業全体を包括的に承継する方が効率的な場合が多いです。一方、小規模な企業や特定の事業部門のみを対象とするM&Aでは、個別承継を選択する方が柔軟に対応できる可能性があります。
3.1.1 従業員の承継包括承継では、原則として従業員もまとめて承継されます。一方、個別承継では、対象事業に関連する従業員のみを選択的に承継することができます。従業員の待遇や雇用維持の観点からも、適切な承継方法を選択する必要があります。
3.2 事業内容と取引先との関係事業内容や取引先との関係も、承継方法の選択に影響を与えます。例えば、許認可が必要な事業を承継する場合、包括承継の方が手続きが簡素化される場合があります。また、既存の取引先との関係を維持したい場合は、包括承継の方が有利に働く可能性があります。個別承継の場合は、契約の移転や取引先の同意が必要となるケースがあり、より慎重な検討が必要です。
3.2.1 取引契約の承継包括承継では、原則として既存の取引契約もまとめて承継されます。ただし、契約内容によっては、取引先の同意が必要となる場合もあります。個別承継では、個別に契約の移転手続きを行う必要があります。契約内容や取引先の状況を踏まえ、最適な方法を選択する必要があります。
3.3 M&Aの目的と戦略M&Aの目的や戦略によっても、最適な承継方法は異なります。例えば、迅速な事業拡大を目指す場合は、包括承継の方が手続きが簡素で、スピード感を持ってM&Aを進めることができます。一方、特定の技術やノウハウの取得を目的とする場合は、個別承継を選択する方が効率的です。M&Aの目的と戦略を明確にし、それに合った承継方法を選択することが重要です。
3.3.1 シナジー効果包括承継では、買収対象企業の事業全体を承継するため、シナジー効果を最大限に発揮できる可能性があります。一方、個別承継では、特定の事業や資産のみを承継するため、シナジー効果は限定的になる場合があります。M&Aによるシナジー効果を最大化するためにも、適切な承継方法を選択する必要があります。
【関連】M&Aのシナジー効果を徹底解説!種類・予測方法からフレームワークまで網羅3.4 税務・法務上のリスクとコスト
包括承継と個別承継では、税務・法務上のリスクとコストが異なります。包括承継では、買収対象企業の全ての権利義務を承継するため、潜在的なリスクも引き継ぐ可能性があります。一方、個別承継では、必要な資産や権利のみを選択的に承継できるため、リスクを限定することができます。また、手続きの複雑さや費用も承継方法によって異なるため、事前に十分な検討が必要です。
| 項目 | 包括承継 | 個別承継 |
|---|---|---|
| 手続きの複雑さ | 比較的簡素 | 複雑な場合が多い |
| 費用 | 比較的安価 | 高額になる場合もある |
| リスク | 潜在的なリスクも承継 | リスクを限定できる |
| スピード | 迅速 | 時間を要する場合もある |
上記のような要素を総合的に考慮し、M&Aの目的に最適な承継方法を選択することが重要です。専門家である弁護士や税理士、M&Aアドバイザーなどに相談しながら、慎重に検討を進めるようにしましょう。
【関連】M&Aのリスク管理:成功へと導く徹底対策と事例|失敗回避のポイント4. M&Aにおける包括承継の注意点
M&Aにおいて包括承継を選択する場合、いくつかの重要な注意点が存在します。これらを事前に理解し適切な対策を講じることで、M&A後の事業運営をスムーズに進めることが可能となります。以下、主要な注意点について詳しく解説します。
4.1 債務超過の場合の対応包括承継では、対象会社の資産だけでなく負債も全て引き継ぎます。そのため、対象会社が債務超過の場合、買収企業はその負債も引き受けることになります。これは買収企業にとって大きな財務リスクとなる可能性があります。債務超過の企業を包括承継する場合には、債務免除や債務圧縮などの対策を事前に検討し、買収後の財務状況を慎重にシミュレーションすることが不可欠です。
4.1.1 債務超過額の確認と評価デューデリジェンスを通じて、対象会社の債務超過額を正確に把握し、その原因を分析することが重要です。隠れた負債や偶発債務がないかどうかも慎重に確認する必要があります。
【関連】M&Aによる債務超過会社の再建:失敗しないためのデューデリジェンスとPMI4.1.2 債権者との交渉
債務超過の企業を承継する場合、債権者との交渉が不可欠となるケースがあります。債務免除や債務圧縮、返済猶予などを交渉することで、買収後の財務負担を軽減できる可能性があります。
4.2 従業員の雇用維持包括承継では、対象会社の従業員も原則としてそのまま引き継ぎます。従業員の雇用維持は、事業継続性や企業文化の維持にとって重要な要素です。買収後に従業員のモチベーションを維持し、円滑な人事統合を進めるためには、事前の丁寧なコミュニケーションと適切な人事制度の設計が重要です。
【関連】会社売却で従業員の雇用を守る方法とは?中小企業のM&A成功の虎の巻4.2.1 雇用契約の承継と変更
包括承継では、従業員の雇用契約もそのまま承継されます。ただし、就業規則や給与体系などを変更する場合は、労働基準法などの関連法令を遵守し、従業員代表との協議が必要となる場合があります。
4.2.2 人事制度の統合買収企業と対象会社の人事制度が異なる場合、人事制度の統合が必要となります。評価制度、昇給制度、福利厚生などをどのように統合していくかを事前に検討し、従業員への説明責任を果たすことが重要です。
4.3 許認可の承継対象会社が特定の事業を行うために必要な許認可を取得している場合、包括承継によってその許認可も引き継げるかどうかを確認する必要があります。許認可によっては、包括承継では承継できず、改めて申請が必要となるケースもあります。事業継続性を確保するため、許認可の承継について事前に関係当局に確認し、必要な手続きを踏むことが重要です。
4.3.1 許認可の種類と承継可能性の確認事業内容に応じて、様々な許認可が存在します。例えば、建設業許可、医療法人許可、金融商品取引業登録などです。それぞれの許認可について、包括承継による承継が可能かどうかを事前に確認する必要があります。
4.3.2 必要に応じた新規申請包括承継で許認可が承継できない場合は、新規に申請する必要があります。新規申請には時間を要する場合があるため、M&Aスケジュールに影響を与えないよう、事前の確認と準備が重要です。
4.3.3 事業への影響の評価許認可の承継がスムーズに行われない場合、事業の継続性に影響が出る可能性があります。許認可の承継に関するリスクを事前に評価し、適切な対応策を検討しておく必要があります。
| 注意点 | 対応策 |
|---|---|
| 債務超過 | デューデリジェンス、債権者との交渉、債務免除・圧縮 |
| 従業員の雇用維持 | 事前のコミュニケーション、人事制度の設計・統合、労働法令の遵守 |
| 許認可の承継 | 関係当局への確認、新規申請手続き、事業への影響評価 |
M&Aにおいて個別承継を選択する場合、包括承継とは異なり、対象となる資産・負債・契約などを個別に選別して承継します。そのため、承継漏れや予期せぬトラブルが発生するリスクがあります。綿密なデューデリジェンスと適切な契約書の作成が不可欠です。以下、個別承継における注意点を詳しく解説します。
5.1 契約書の確認と再締結個別承継では、既存の契約が自動的に承継されるわけではありません。個別に契約内容を確認し、相手方の同意を得て再締結する必要があります。契約書の確認を怠ると、重要な取引関係が失われたり、不利な条件で契約を継続することになる可能性があります。
5.1.1 主な確認事項- 契約の相手方
- 契約期間
- 契約内容(権利義務、料金、解約条項など)
- 譲渡に関する規定
- 相手方への連絡と交渉
- 新契約書の作成
- 契約締結
特に、取引先との契約、リース契約、ライセンス契約などは、事業継続に不可欠な場合が多いため、慎重な対応が必要です。また、秘密保持契約なども見落としがちですが、重要な契約です。再締結が困難な場合、M&A自体が成立しない可能性もあるため、事前に十分な検討が必要です。
5.2 資産評価と譲渡価格の決定個別承継では、承継する資産を個別に評価し、適切な譲渡価格を決定する必要があります。資産評価の方法には、時価、帳簿価格、収益還元法など様々な方法があります。適切な評価方法を選択し、公正な価格で取引を行うことが重要です。評価を誤ると、売買当事者間でトラブルが発生する可能性があります。
| 評価方法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 時価 | 市場で取引される価格 | 客観的な評価が可能 | 市場価格の変動に影響されやすい |
| 帳簿価格 | 会計帳簿に記載されている価格 | 算出が容易 | 実際の価値を反映していない場合がある |
| 収益還元法 | 将来の収益を現在価値に割り引いた価格 | 事業の収益性を反映した評価が可能 | 将来予測の精度に依存する |
特に、不動産、知的財産権、営業権など、評価が難しい資産については、専門家の助言を得ることが重要です。また、譲渡価格の決定においては、税務上の影響も考慮する必要があります。例えば、譲渡益に対する課税や、減価償却費の取扱いに注意が必要です。
5.3 デューデリジェンスの重要性個別承継では、承継対象を個別に選別するため、包括承継以上にデューデリジェンスの重要性が高まります。デューデリジェンスとは、M&Aの対象となる企業の財務状況、事業内容、法務リスクなどを調査するプロセスです。デューデリジェンスを徹底的に行うことで、隠れたリスクを発見し、M&A後のトラブルを未然に防ぐことができます。
5.3.1 デューデリジェンスの主な内容- 財務デューデリジェンス(財務諸表の分析、収益性・安全性・成長性の評価など)
- 事業デューデリジェンス(事業内容、市場環境、競争優位性、将来性などの分析)
- 法務デューデリジェンス(契約書の確認、訴訟リスク、コンプライアンス体制の確認など)
- 税務デューデリジェンス(税務リスク、税務申告の正確性などの確認)
- 労務デューデリジェンス(従業員の雇用契約、労務管理体制の確認など)
- 環境デューデリジェンス(環境規制への compliance 、環境リスクの評価など)
デューデリジェンスは、M&Aの成否を左右する重要なプロセスです。専門家を活用し、時間をかけて綿密な調査を行うことが重要です。特に、個別承継では、承継対象を限定するため、デューデリジェンスの範囲を明確にする必要があります。また、発見されたリスクへの対応策も事前に検討しておく必要があります。例えば、保証条項の挿入、価格交渉、M&Aの中止なども選択肢となります。
【関連】M&Aで失敗しないデューデリジェンス!目的・種類・費用は?【前編】6. まとめ
M&Aにおける事業承継は、包括承継と個別承継の2つの方法があり、それぞれメリット・デメリットが存在します。包括承継は手続きが簡便で事業の全体像を維持しやすい一方、不要な負債も引き継ぐリスクがあります。個別承継は必要な資産・負債のみを選択できるメリットがある一方、手続きが煩雑で取引先との契約変更が必要になるケースもあります。
企業規模、事業内容、M&Aの目的、税務・法務リスクなどを考慮し、最適な方法を選択することが重要です。専門家である弁護士や税理士に相談することで、スムーズかつ安全なM&Aを実現できるでしょう。


