経営再建 とは? 倒産寸前の会社を再生させる方法を徹底解説!
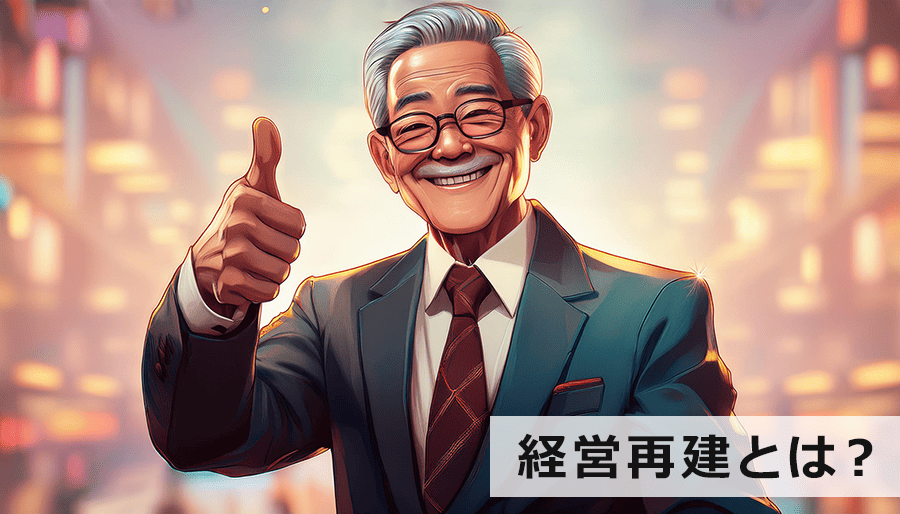
倒産寸前の会社を再生させる「経営再建」とは何か、その方法や成功のポイントを具体的に解説します。業績悪化や資金繰り難に直面し、事業継続に不安を感じている経営者の方、必見です。この記事では、経営再建の定義や目的といった基本から、財務リストラ・事業リストラ・組織リストラといった具体的な方法、そして成功に導くためのポイントまで、網羅的に解説。
売上減少、利益率低下、借入金増加といった兆候を見逃さず、早期に適切な対策を講じることで、企業の再生は可能です。帝国データバンクの調査結果など、信頼できるデータも交えながら、経営再建の全体像を分かりやすく説明します。この記事を読み終えることで、経営再建の進め方や専門家の活用法を理解し、危機的状況を乗り越えるための具体的な行動計画を立てられるようになるでしょう。未来への希望を見出すための第一歩を、今踏み出しましょう。
「赤字解消(経営再建)してからM&Aしたい」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・事業再生などを10年経験。3か月の経営支援サポートで、9か月後には赤字の会社を1億円の利益を計上させるなどの実績を多数持つ専門家。
1. 経営再建とは何か?
経営再建とは、業績が悪化し、倒産の危機に瀕している企業が、事業の継続を図るために行う一連の改革活動のことです。単に倒産を回避するだけでなく、企業の収益性や競争力を回復し、持続的な成長を実現することを目指します。 「再建」という言葉には、一度崩れた組織や仕組みを再び築き上げるという意味が込められており、企業の存続と成長のために、抜本的な改革が必要となる場合に用いられます。
【関連】事業再生とは?基本戦略と成功へのステップ1.1 経営再建の定義
経営再建には明確な法的定義はありませんが、一般的には、企業が倒産の危機に瀕している状況下で、事業の継続を目的として、財務体質の改善、事業構造の改革、組織体制の見直しなど、抜本的な改革を行うことを指します。
日本政策投資銀行の「企業再生ハンドブック」では、経営再建を「企業が経済的または財務的な困難に直面している場合に、企業の事業活動を継続させ、債権者への弁済を図り、雇用を維持し、最終的には企業価値を向上させるために行われる一連の措置」と定義しています。この定義からもわかるように、経営再建は単なる倒産の回避だけでなく、企業価値の向上を目指した、より積極的な取り組みであると言えるでしょう。
1.2 経営再建の目的
経営再建の目的は、企業の存続と成長です。具体的には、以下の項目が挙げられます。
| 倒産の回避 | |
| 収益性の回復 | |
| 財務体質の強化 | |
| 競争力の向上 | |
| 企業価値の向上 | |
| 雇用の維持 | |
| 取引先との関係維持 |
これらの目的を達成するために、企業は自社の状況に合わせて、適切な再建計画を策定し、実行していく必要があります。
1.3 経営再建と倒産の回避
経営再建と倒産の回避は密接に関連していますが、イコールではありません。倒産の回避は経営再建の目的の一つではありますが、経営再建は単に倒産を回避するだけでなく、その後の企業の成長も視野に入れた、より包括的な取り組みです。
倒産を回避するためには、債務超過の解消や資金繰りの改善といった短期的な対策が必要となりますが、経営再建においては、これらの短期的な対策に加えて、中長期的な視点に立った事業構造改革や組織改革なども重要となります。
例えば、民事再生法や会社更生法などの法的手続きを利用せずに、自主的に経営再建を行う場合、債権者との合意形成が不可欠となります。そのため、経営再建計画には、債権者に対する弁済計画や事業計画などが含まれる必要があり、単なる倒産の回避よりも複雑で高度な対応が求められます。
| 項目 | 経営再建 | 倒産の回避 |
|---|---|---|
| 目的 | 企業の存続と成長 | 倒産状態の回避 |
| 期間 | 中長期 | 短期 |
| 内容 | 財務リストラ、事業リストラ、組織リストラなど | 債務超過の解消、資金繰りの改善など |
| 視点 | 将来の成長 | 現状の打開 |
2. 経営再建が必要となる兆候
企業が経営再建を検討しなければならない状況は、様々な兆候によって示されます。これらの兆候を早期に認識し、適切な対策を講じることで、倒産などの深刻な事態を回避できる可能性が高まります。主な兆候は以下の通りです。
2.1 業績の悪化
業績の悪化は、経営再建が必要となる最も顕著な兆候の一つです。売上高の減少や利益率の低下は、企業の収益力を低下させ、資金繰りを圧迫する要因となります。
2.1.1 売上高の減少売上高の減少は、市場の縮小、競合の激化、製品やサービスの陳腐化など、様々な要因によって引き起こされます。継続的な売上高の減少は、企業の存続を脅かす重大な問題です。例えば、消費者の嗜好の変化に対応できず、売上が低迷しているアパレル企業などが挙げられます。具体的な数値目標としては、前年同期比で10%以上の売上減少が続いている場合、危険信号と捉えるべきでしょう。
2.1.2 利益率の低下利益率の低下も、経営悪化の重要な指標です。売上原価の上昇、販売管理費の増加、価格競争の激化などが利益率低下の原因となります。高コスト体質のままでは、利益を確保することが難しくなり、経営を圧迫します。例えば、原材料価格の高騰に対応できず、利益率が低下している製造業などが挙げられます。具体的な数値目標としては、営業利益率が3%を下回っている場合、注意が必要です。
2.2 資金繰りの悪化
資金繰りの悪化は、企業の短期的な支払能力に問題が生じていることを示します。借入金の増加や債務超過は、資金繰りをさらに悪化させる要因となります。
2.2.1 借入金の増加借入金の増加は、資金需要の高まりを示す一方で、返済負担の増加にもつながります。過剰な借入金は、企業の財務体質を悪化させ、経営リスクを高めます。例えば、設備投資のために多額の借入を行い、返済に苦しんでいる企業などが挙げられます。具体的な数値目標としては、借入金依存度が70%を超えている場合、危険水域と言えるでしょう。
2.2.2 債務超過債務超過とは、企業の負債が資産を上回る状態を指します。債務超過は、企業の支払能力が著しく低下していることを示す深刻な兆候です。例えば、業績悪化により累積損失が膨らみ、債務超過に陥っている企業などが挙げられます。債務超過の状態が続くと、倒産の可能性が高まります。
【関連】債務超過で会社売却?それとも倒産?違いを知って企業の危機を乗り越える!2.3 社内体制の問題
社内体制の問題も、経営再建が必要となる兆候の一つです。従業員のモチベーション低下や組織の硬直化は、企業の競争力を低下させ、業績悪化につながる可能性があります。
2.3.1 従業員のモチベーション低下従業員のモチベーション低下は、業績悪化や将来への不安、職場環境の悪化など、様々な要因によって引き起こされます。モチベーションの低い従業員は、生産性や創造性が低下し、企業の成長を阻害する要因となります。例えば、過度なリストラや賃金カットにより、従業員のモチベーションが低下している企業などが挙げられます。
【関連】事業承継での従業員モチベーション管理|重要性と具体的な対策事例2.3.2 組織の硬直化
組織の硬直化は、意思決定の遅延、変化への対応の遅れ、新しいアイデアの創出の阻害など、様々な問題を引き起こします。硬直化した組織は、市場の変化に対応できず、競争力を失う可能性が高まります。例えば、年功序列制度が強く、若手社員の意見が反映されない企業などが挙げられます。
| 兆候 | カテゴリー | 具体的な例 | 危険信号となる数値目標の例 |
|---|---|---|---|
| 売上高の減少 | 業績の悪化 | 消費者の嗜好の変化に対応できないアパレル企業 | 前年同期比10%以上の減少が続く |
| 利益率の低下 | 業績の悪化 | 原材料価格の高騰に対応できない製造業 | 営業利益率3%未満 |
| 借入金の増加 | 資金繰りの悪化 | 設備投資のための過剰な借入 | 借入金依存度70%超 |
| 債務超過 | 資金繰りの悪化 | 累積損失による債務超過 | - |
| 従業員のモチベーション低下 | 社内体制の問題 | 過度なリストラや賃金カット | - |
| 組織の硬直化 | 社内体制の問題 | 年功序列制度の弊害 | - |
これらの兆候は単独で現れることもありますが、複数の兆候が同時に現れる場合もあります。いずれにしても、これらの兆候を早期に発見し、適切な対策を講じることが、経営再建の成功には不可欠です。また、これらの兆候はあくまで一般的なものであり、業種や企業規模などによって異なる場合があることに注意が必要です。具体的な状況に応じて、専門家のアドバイスを受けることも重要です。
3. 経営再建の進め方
経営再建を成功させるためには、綿密な計画と着実な実行が不可欠です。闇雲に施策を実行するのではなく、現状を正確に把握し、適切な計画を策定した上で、進捗状況を逐一確認しながら進めていく必要があります。具体的な進め方としては、以下の3つのステップが重要です。
3.1 現状分析
まずは、企業の現状を客観的に分析することが重要です。財務状況だけでなく、事業環境や社内体制など、多角的な視点から分析を行い、問題点や課題を明確にする必要があります。現状分析を怠ると、的外れの再建計画を立ててしまい、状況を悪化させる可能性があります。
3.1.1 財務状況の分析貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書といった財務諸表を詳細に分析し、企業の財務状況を正確に把握します。売上高の推移、利益率、債務比率、流動比率、自己資本比率など、重要な指標に着目し、問題点を洗い出します。例えば、債務超過に陥っている場合は、その原因を突き止め、負債の構成や返済能力などを詳細に分析する必要があります。また、粉飾決算の有無も注意深く確認する必要があります。
3.1.2 事業環境の分析市場の動向、競合他社の状況、技術革新のスピード、法規制の変更など、企業を取り巻く外部環境を分析します。PEST分析、5フォース分析などのフレームワークを活用することで、客観的な分析が可能になります。市場の縮小や競争の激化など、事業環境の悪化が業績低迷の原因となっている場合は、事業の転換や撤退も検討する必要があります。
3.2 再建計画の策定
現状分析に基づき、具体的な再建計画を策定します。目標設定、具体的な施策、実行スケジュール、必要な資源などを明確に定義し、関係者間で共有することが重要です。計画は具体的かつ現実的で、実行可能なものでなければなりません。また、ステークホルダーの理解と協力を得られるような内容にすることも重要です。
3.2.1 目標設定再建計画の最終的な目標を設定します。例えば、「3年以内に債務超過を解消する」「5年以内に売上高を前年比10%増とする」といった具体的な目標を設定することで、計画の進捗状況を測定しやすくなります。目標は、SMARTの原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限が明確)に基づいて設定することが重要です。
3.2.2 具体的な施策目標を達成するための具体的な施策を立案します。財務リストラ、事業リストラ、組織リストラなど、様々な施策を検討し、最適な組み合わせを選択します。例えば、財務リストラでは、債務免除の交渉、資産売却、新規融資の獲得などを検討します。事業リストラでは、不採算事業の撤退、新規事業の開拓、事業提携などを検討します。組織リストラでは、人員削減、組織改編、人事制度改革などを検討します。それぞれの施策について、実施内容、スケジュール、担当者、費用などを明確に定義します。
| 施策 | 内容 | 効果 | リスク |
|---|---|---|---|
| 債務免除の交渉 | 金融機関と交渉し、債務の一部または全部を免除してもらう | 債務負担の軽減 | 交渉決裂のリスク |
| 資産売却 | 保有資産を売却し、資金を調達する | 資金繰りの改善 | 資産価値の下落リスク |
| 不採算事業の撤退 | 利益を生み出さない事業から撤退する | コスト削減 | 売却損失発生のリスク |
3.3 再建計画の実行
策定した再建計画に基づき、具体的な施策を実行に移します。計画通りに進捗しているか、効果が出ているかを定期的にモニタリングし、必要に応じて計画を修正していくことが重要です。また、ステークホルダーに対して、進捗状況を定期的に報告し、理解と協力を得る努力を継続する必要があります。
3.3.1 モニタリングと評価設定した目標に対する進捗状況を定期的にモニタリングし、評価します。売上高、利益率、債務比率などの主要業績指標(KPI)を設定し、実績値を計測することで、計画の進捗状況を客観的に評価することができます。モニタリングは、月次、四半期ごとなど、定期的に実施することが重要です。また、予期せぬ事態が発生した場合には、臨時にモニタリングを実施し、状況を把握する必要があります。
3.3.2 計画の修正モニタリングの結果、計画通りに進捗していない場合や、外部環境の変化などにより計画の前提条件が崩れた場合は、計画を修正する必要があります。計画の修正は、現状分析からやり直すのではなく、当初の計画をベースに、修正すべき箇所を特定し、修正内容を明確にすることが重要です。
修正した計画は、関係者間で共有し、理解と協力を得る必要があります。また、計画の修正は、必要に応じて柔軟に行うことが重要ですが、安易な計画変更は、再建の失敗につながる可能性があるため、慎重な判断が必要です。計画の修正にあたっては、専門家のアドバイスを受けることも有効です。
4. 経営再建の具体的な方法
経営再建を進めるにあたっては、企業の置かれた状況に合わせて、様々な具体的な方法を検討し、実行していく必要があります。ここでは、代表的な方法を財務リストラ、事業リストラ、組織リストラの3つの側面から解説します。
4.1 財務リストラ
財務リストラは、企業の財務体質を改善するための施策です。負債の圧縮や資産の効率化を通じて、健全な財務状態を目指します。
4.1.1 債務免除の交渉金融機関との交渉により、借入金の減額や返済猶予を求めます。リスケジュールや債務免除は、資金繰りの負担を軽減し、再建への足掛かりとなります。交渉にあたっては、事業計画や返済計画を明確に示すことが重要です。弁護士や会計士などの専門家の支援を受けることも有効です。
4.1.2 資産売却保有する不動産や遊休設備、子会社株式などを売却し、資金を調達します。売却対象の選定にあたっては、将来の事業展開への影響を慎重に考慮する必要があります。また、売却価格の妥当性についても、専門家の意見を参考に判断することが重要です。
4.1.3 デット・エクイティ・スワップ(DES)債権を株式に転換することで、負債を圧縮する方法です。債権者が株主となるため、経営への関与が強まる可能性があります。DESの実施にあたっては、既存株主との調整が必要となる場合もあります。
4.1.4 増資新しい株式を発行して資金を調達する方法です。既存株主の持ち株比率が低下する可能性があるため、慎重な検討が必要です。また、増資を引き受けてくれる投資家を見つける必要があります。
4.2 事業リストラ
事業リストラは、収益性の低い事業や将来性のない事業を整理し、収益構造の改善を図る施策です。コア事業への集中や新規事業の開拓を通じて、持続的な成長を目指します。
4.2.1 不採算事業の撤退赤字事業や将来性が見込めない事業からの撤退を検討します。撤退に伴うコストや従業員への影響を考慮しながら、迅速な意思決定が必要です。撤退後の事業ポートフォリオを明確にすることが重要です。
4.2.2 新規事業の開拓市場のニーズや将来の成長性を見据え、新たな事業領域への進出を検討します。新規事業の立ち上げには、時間と費用がかかるため、綿密な市場調査と事業計画の策定が不可欠です。
【関連】事業再生のための新規事業開発とは?4.2.3 事業の選択と集中
コア事業を明確化し、資源を集中投下することで、競争優位性を高めます。選択と集中により、効率的な経営資源の配分が可能となります。
4.2.4 業務提携・M&A他社との提携や合併・買収を通じて、事業規模の拡大や新たな技術・ノウハウの獲得を目指します。M&Aは、迅速な事業拡大を実現する手段となりますが、綿密なデューデリジェンスと統合プロセスが重要です。
【関連】資本業務提携とM&Aの違いとは?目的別で最適な戦略を選択する方法4.3 組織リストラ
組織リストラは、組織構造や人事制度を見直し、効率的な組織運営を実現するための施策です。人員削減や組織改編を通じて、組織のスリム化や意思決定の迅速化を図ります。
4.3.1 人員削減経営効率化のため、人員削減を行う場合があります。早期退職優遇制度の導入や配置転換など、従業員への影響を最小限に抑えるための対策が必要です。また、残る従業員のモチベーション維持にも配慮する必要があります。
4.3.2 組織改編事業戦略に合わせて、組織構造や部門の役割を見直します。階層を減らすフラット化や、意思決定の迅速化を図るための分権化などが検討されます。組織改編にあたっては、従業員への丁寧な説明と理解を得ることが重要です。
4.3.3 アウトソーシング一部の業務を外部企業に委託することで、コスト削減や業務効率化を図ります。コア業務に経営資源を集中させることができます。
4.3.4 人事制度改革成果主義の導入や能力開発プログラムの強化など、従業員のモチベーション向上と生産性向上を図るための施策を実施します。
5. 経営再建を成功させるためのポイント
上記で挙げた具体的な方法を効果的に実行し、経営再建を成功させるためには、以下のポイントが重要です。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 経営者のリーダーシップ | 明確なビジョンと戦略を提示し、従業員を鼓舞する強いリーダーシップが不可欠です。 |
| 従業員とのコミュニケーション | 経営状況や再建計画について、従業員に丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要です。 |
| ステークホルダーとの協力 | 金融機関、取引先、株主など、様々なステークホルダーとの良好な関係を維持し、協力を得ることが不可欠です。 |
| 専門家の活用 | 弁護士、会計士、コンサルタントなどの専門家の知見を活用することで、より効果的な再建策を立案・実行することができます。 |
| スピード感 | 経営再建は時間との勝負です。迅速な意思決定と実行が不可欠です。 |
| 柔軟性 | 状況変化に応じて、計画を柔軟に見直すことが重要です。 |
これらのポイントを踏まえ、状況に合わせた適切な方法を選択し、実行することで、経営再建を成功に導くことができます。
6. 経営再建を成功させるためのポイント
経営再建は、企業の存続を左右する重要なプロセスです。成功させるためには、綿密な計画と徹底した実行、そして様々な関係者との協力が不可欠です。ここでは、経営再建を成功に導くための重要なポイントを解説します。
6.1 経営者のリーダーシップ
経営再建において、経営者のリーダーシップは極めて重要です。明確なビジョンと強い意志を持ち、従業員を鼓舞し、ステークホルダーからの信頼を得ることが求められます。困難な状況でも、冷静な判断力と迅速な意思決定を行い、再建計画を推進していく力が必要です。透明性の高い情報開示と、従業員やステークホルダーとの積極的なコミュニケーションも、リーダーシップを発揮する上で重要な要素となります。
6.2 従業員とのコミュニケーション
経営再建は、従業員の協力なしには成し遂げられません。再建計画の内容や進捗状況を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要です。従業員の不安や不満に耳を傾け、真摯に対応することで、モチベーションの維持・向上に繋げることができます。
また、従業員の意見やアイデアを積極的に取り入れることで、より効果的な再建計画を策定することが可能になります。社内報や説明会などを活用し、双方向のコミュニケーションを図ることで、信頼関係を構築し、一体感を醸成することが重要です。
6.3 ステークホルダーとの協力
経営再建には、金融機関、取引先、株主など、様々なステークホルダーの理解と協力が不可欠です。現状と再建計画を丁寧に説明し、信頼関係を構築することで、資金調達や取引継続の支援を得ることが可能になります。また、ステークホルダーからのフィードバックを積極的に取り入れ、再建計画を改善していくことも重要です。誠実な対応と透明性の高い情報開示によって、ステークホルダーとの良好な関係を維持することが、経営再建の成功に繋がります。
6.4 専門家の活用
経営再建は複雑なプロセスであり、専門家の知見を活用することが効果的です。弁護士、会計士、コンサルタントなど、それぞれの専門家に相談することで、法的、財務的、経営的な課題を解決し、再建計画をスムーズに進めることができます。
6.4.1 弁護士弁護士は、債権者との交渉、法的整理手続き、契約の見直しなど、法的な側面から経営再建をサポートします。債務免除やリスケジュールなど、債権者との交渉においては、弁護士の専門知識が不可欠です。また、会社更生法や民事再生法などの法的整理手続きについても、弁護士のアドバイスが重要になります。
6.4.2 会計士会計士は、財務状況の分析、再建計画の策定、資金調達支援など、財務的な側面から経営再建をサポートします。正確な財務分析に基づいた再建計画の策定は、経営再建の成否を左右する重要な要素です。また、金融機関との交渉や資金調達においても、会計士の専門知識が役立ちます。
6.4.3 コンサルタントコンサルタントは、事業戦略の策定、業務プロセスの改善、組織改革など、経営戦略の側面から経営再建をサポートします。市場分析や競合分析に基づいた事業戦略の策定は、中長期的な成長を実現するために不可欠です。また、業務プロセスの効率化や組織のスリム化など、コンサルタントのアドバイスは、経営効率の向上に貢献します。
| 専門家 | 役割 | 活用メリット |
|---|---|---|
| 弁護士 | 法的側面のサポート(債権者交渉、法的整理手続きなど) | 法的リスクの軽減、円滑な手続き進行 |
| 会計士 | 財務的側面のサポート(財務分析、再建計画策定、資金調達支援など) | 財務状況の把握、資金繰りの安定化 |
| コンサルタント | 経営戦略の側面のサポート(事業戦略策定、業務プロセス改善、組織改革など) | 事業の競争力強化、経営効率の向上 |
これらの専門家を適切に活用することで、経営再建を成功に導く可能性を高めることができます。それぞれの専門家の得意分野を理解し、状況に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。
7. まとめ
この記事では、「経営再建とは何か?」から始まり、その必要となる兆候、進め方、具体的な方法、成功させるためのポイントまでを解説しました。経営再建とは、業績悪化や資金繰り悪化に陥った企業が、事業の継続を図るために行う一連の取り組みです。倒産を回避し、企業の再生を目指すことが目的となります。
再建が必要な兆候としては、売上高の減少や利益率の低下といった業績悪化、借入金の増加や債務超過といった資金繰りの悪化、従業員のモチベーション低下や組織の硬直化といった社内体制の問題などが挙げられます。これらの兆候を早期に発見し、迅速な対応をすることが重要です。
経営再建を進めるには、現状分析、再建計画の策定、そして実行という流れを踏みます。財務状況や事業環境を分析し、具体的な目標と施策を定めた計画を策定、実行します。計画実行中はモニタリングと評価を行い、必要に応じて計画を修正していく柔軟性も求められます。
財務リストラ、事業リストラ、組織リストラといった具体的な方法を適切に組み合わせ、経営者のリーダーシップのもと、従業員やステークホルダーとの協力、弁護士や会計士、コンサルタントといった専門家の活用も成功の鍵となります。早期発見、迅速な対応、そして関係者との協力が、企業の未来を守るために不可欠です。


