スモールM&Aで会社売却の準備7つのステップ
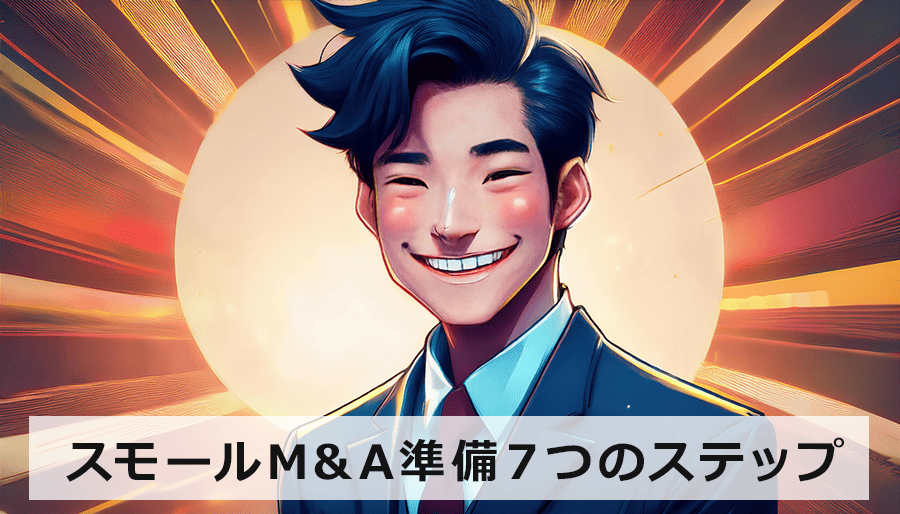
スモールM&Aによる会社売却を検討し始めましたか?売却活動は、人生における大きな転換期となる重要な意思決定です。準備を怠ると、売却価格が低くなったり、最悪の場合、売却自体が失敗に終わる可能性もあります。この記事では、スモールM&Aで会社売却を成功させるための7つのステップを分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、スモールM&Aの概要から、会社価値の算定方法、必要な書類の準備、買い手候補との交渉に至るまで、売却プロセス全体を理解し、スムーズに売却を進めるための準備を整えることができます。最終的には、仲介会社との効果的な連携方法も理解できるようになります。適切な準備を行うことで、あなたの会社にとって最適な売却条件を引き出し、事業の次のステージへと繋げることが可能になります。
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月のPMIにて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. スモールM&Aとは何か?会社売却のメリット・デメリット
会社売却を考える経営者にとって、スモールM&Aは魅力的な選択肢の一つです。この章では、スモールM&Aの概要、そして会社売却に伴うメリット・デメリットを詳しく解説します。
【関連】スモールM&Aの基本|初めての会社売却ガイド1.1 スモールM&Aの定義と特徴
スモールM&Aとは、一般的に譲渡対象企業の売上高や従業員数が比較的小規模なM&A取引を指します。明確な定義はありませんが、概ね譲渡価格が数億円以下の案件を指すことが多いです。中小企業の事業承継問題解決や、大企業の新規事業参入、事業領域拡大などを目的として行われます。
スモールM&Aの特徴としては、以下の点が挙げられます。
| 取引金額が比較的小さい | |
| 手続きが比較的簡素である | |
| 買収後の統合プロセスが比較的容易である | |
| 経営者の想いや従業員の雇用維持を重視した交渉が行われるケースが多い |
近年、後継者不足による事業承継問題を抱える中小企業の増加に伴い、スモールM&Aの件数は増加傾向にあります。また、大企業においても、オープンイノベーションや新規事業創出の手段として、スモールM&Aを活用するケースが増えています。
1.2 会社売却のメリット
会社売却には、経営者や株主にとって様々なメリットがあります。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 事業承継問題の解決 | 後継者不在の場合でも、事業を存続させ、従業員の雇用を守ることができます。 |
| 経営資源の獲得 | 売却によって得た資金を、新たな事業展開や投資に活用できます。 |
| リスク分散 | 事業ポートフォリオの見直しや、特定の事業リスクからの解放が可能になります。 |
| 経営者の負担軽減 | 経営からの引退や、新たな挑戦への時間を確保できます。 |
| 企業価値の最大化 | 適切なタイミングで売却することで、企業価値を最大限に高めることができます。 |
1.3 会社売却のデメリット
一方で、会社売却にはデメリットも存在します。事前にしっかりと理解しておくことが重要です。
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| 従業員への影響 | 買収後の経営方針変更などにより、従業員の雇用や待遇に影響が出る可能性があります。 |
| 企業文化の変化 | 買収企業の文化との融合がうまくいかない場合、社内混乱が生じる可能性があります。 |
| 情報漏洩のリスク | 売却交渉過程で、企業の機密情報が漏洩するリスクがあります。 |
| 売却価格の不確実性 | 市場環境や交渉状況によって、売却価格が当初の想定よりも低くなる可能性があります。 |
| 感情的な抵抗 | 創業者が長年経営してきた会社を手放すことに対する、感情的な抵抗が生じる場合があります。 |
これらのメリット・デメリットを踏まえ、自社にとって最適な選択かどうかを慎重に検討する必要があります。M&Aアドバイザーなどの専門家に相談することで、より客観的な判断材料を得ることができます。
2. 会社売却の適切なタイミングを見極める
会社売却は、経営における重要な意思決定の一つです。適切なタイミングで売却を行うことで、最大限のメリットを得ることができます。逆に、タイミングを誤ると、売却価格が低くなったり、売却自体が難航する可能性があります。そのため、売却のタイミングを見極めることは非常に重要です。
売却のタイミングを検討する際には、事業の状況、経営者の状況、市場環境など、様々な要因を総合的に判断する必要があります。以下の要素を参考に、最適な売却時期を見極めましょう。
2.1 事業の成長性と収益性
事業の成長性と収益性は、会社売却のタイミングを判断する上で重要な指標となります。一般的に、成長性が高く、収益性も安定している企業は、高い評価額で売却できる可能性が高くなります。
2.1.1 成長期の売却事業が成長期にある場合、将来的な収益拡大が見込まれるため、高い評価額での売却が期待できます。特に、市場シェアの拡大や新規事業の立ち上げなど、将来性を感じさせる要素があれば、買い手企業からの注目も集まりやすくなります。ただし、成長期の売却は、将来得られるはずの利益を放棄することにもなるため、慎重な判断が必要です。
2.1.2 成熟期の売却事業が成熟期に入り、安定した収益を確保できている場合も、売却の好機と言えるでしょう。成熟期にある企業は、安定したキャッシュフローを生み出しているため、買い手企業にとって魅力的な投資対象となります。また、成長期と比較してリスクが低いため、高値で売却できる可能性も高くなります。
2.1.3 衰退期の売却事業が衰退期に入り、収益が減少傾向にある場合は、売却が難航する可能性があります。しかし、早期に売却することで、損失を最小限に抑え、事業の再建資金を確保できる可能性もあります。また、ニッチな市場で事業を展開している場合、特定の買い手企業にとって価値がある可能性もあるため、諦めずに売却の可能性を探ることが重要です。
2.2 経営者の年齢や後継者問題
経営者の年齢や後継者問題も、会社売却のタイミングに大きく影響します。後継者がいない場合や、経営者が高齢で事業承継が難しい場合は、会社売却を検討する良いタイミングと言えるでしょう。
2.2.1 後継者不在の場合後継者不在の場合、会社売却は事業継続のための有効な手段となります。売却によって、従業員の雇用を守り、事業を継続していくことができます。また、M&Aによって、新たな経営資源やノウハウを獲得できる可能性もあります。
2.2.2 経営者の高齢化経営者が高齢化し、事業承継が難しい場合も、会社売却を検討する良いタイミングです。売却によって、経営者の引退後の生活資金を確保することができます。また、事業を次の世代に引き継ぐことで、企業の永続的な発展に貢献することができます。
【関連】後継者がいない...と悩む前に!事業承継の選択肢を広げ、企業の未来を創造しよう2.3 市場環境の変化
市場環境の変化も、会社売却のタイミングに影響を与えます。業界の再編や競争激化、技術革新など、市場環境の変化に合わせて売却戦略を立てる必要があります。好況期には、高値で売却できる可能性が高まりますが、競合企業も売却を検討している可能性があるため、迅速な対応が求められます。一方、不況期には、売却価格が下落する可能性がありますが、競合が少なくなるため、有利な条件で売却できる可能性もあります。
| 時期 | メリット | デメリット | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 成長期 | 高値売却の可能性 | 将来の利益を放棄 | 成長性を証明する資料が必要 |
| 成熟期 | 安定した売却価格 | 更なる成長の余地が少ない | 競合との差別化が重要 |
| 衰退期 | 損失の最小化 | 売却価格が低い | 早期の売却が重要 |
これらの要素を総合的に考慮し、自社にとって最適な売却タイミングを見極めることが重要です。専門家であるM&Aアドバイザーに相談することで、より客観的な判断材料を得ることができます。M&Aアドバイザーは、市場動向や業界の状況、買い手企業のニーズなどを踏まえ、最適な売却戦略を提案してくれます。
また、売却価格の算定や交渉、デューデリジェンス、契約締結など、売却プロセス全体をサポートしてくれるため、スムーズな売却を実現することができます。売却を検討する際は、M&Aアドバイザーに相談することをおすすめします。
3. スモールM&Aにおける会社価値の算定方法
スモールM&Aにおいて、会社価値の算定は売却価格を決める上で非常に重要な要素となります。適切な評価額を理解することで、売主は不利な条件で売却してしまうことを防ぎ、買主は適正価格での買収を実現できます。会社価値の算定方法は複数存在し、それぞれの特徴を理解した上で、自社に最適な方法を選択することが大切です。ここでは代表的な3つの算定方法について解説します。
【関連】スモールM&Aで企業価値を最大化する方法3.1 DCF法による評価
DCF法(Discounted Cash Flow:割引キャッシュフロー法)は、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて会社価値を算出する方法です。将来の予測に基づくため、成長性の高い企業の評価に適しています。一方で、将来予測の精度が結果に大きく影響するため、客観的な評価が難しい側面もあります。
3.1.1 DCF法の計算方法DCF法の計算式は以下の通りです。
企業価値 = 将来のフリーキャッシュフロー ÷ (1 + 割引率)^n (nは将来の期間)
フリーキャッシュフローは、事業活動によって得られたキャッシュフローから設備投資額を差し引いた金額です。割引率は、投資家が要求する収益率で、一般的にはWACC(加重平均資本コスト)が用いられます。WACCは、負債と資本のそれぞれの調達コストを、それぞれの構成比率で加重平均したものです。
3.1.2 DCF法のメリット・デメリット| メリット | デメリット |
|---|---|
| 将来の成長性を反映できる | 将来予測の精度に左右される |
| 理論的に整合性が高い | 計算が複雑で専門知識が必要 |
3.2 類似会社比較法による評価
類似会社比較法(Comparable Company Analysis:CCA)は、類似業種・規模の上場企業の市場価値を参考に、対象企業の価値を算出する方法です。市場で評価されている企業との比較を行うため、客観的な評価がしやすいというメリットがあります。一方で、本当に類似した企業を見つけることが難しい場合や、非上場企業の場合は適用が難しいというデメリットもあります。PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、EV/EBITDA倍率などの指標を用いて比較を行います。
3.2.1 類似会社比較法の計算方法類似上場企業の財務指標(PER、PBR、EV/EBITDA倍率など)を算出し、対象企業の財務データに適用することで、対象企業の価値を推定します。
3.2.2 類似会社比較法のメリット・デメリット| メリット | デメリット |
|---|---|
| 客観的な評価がしやすい | 真に類似した企業を見つけるのが難しい |
| 市場の実勢を反映できる | 非上場企業への適用が難しい |
3.3 純資産法による評価
純資産法は、会社の純資産(資産総額から負債総額を差し引いた金額)を基に会社価値を算出する方法です。計算が容易で理解しやすいというメリットがありますが、将来の収益性を反映していないため、成長性の高い企業の評価には適していません。また、簿価と時価が乖離している資産が多い場合、正確な評価が難しくなります。清算価値の算定に用いられることが多いです。
3.3.1 純資産法の計算方法純資産 = 総資産 - 総負債
3.3.2 純資産法のメリット・デメリット| メリット | デメリット |
|---|---|
| 計算が容易で理解しやすい | 将来の収益性を反映していない |
| 財務諸表から容易に算出できる | 簿価と時価の乖離が大きい場合、正確な評価が難しい |
スモールM&Aにおいては、これらの算定方法を単独で用いるのではなく、複数の方法を組み合わせて総合的に判断することが一般的です。それぞれの方法の特性を理解し、M&Aアドバイザーなどの専門家の意見も参考にしながら、適切な評価額を導き出すことが重要です。
4. 売却準備として必要な書類と情報の整理
スモールM&Aを成功させるためには、綿密な準備が不可欠です。特に、買い手候補に提供する情報が不足していたり、不正確であったりすると、売却プロセスが遅延したり、最悪の場合、破談に至る可能性もあります。スムーズな売却を実現するためには、必要な書類と情報を事前に整理しておくことが重要です。以下に、売却準備として必要な主な書類と情報をまとめました。
【関連】スモールM&Aの進め方【完全版】成功に導くステップと事例|費用・期間も解説4.1 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)
財務諸表は、会社の財務状況や経営成績を示す重要な資料です。過去3~5期分の財務諸表を用意し、正確性と網羅性を確保しましょう。これらの書類は、買い手候補が企業価値を評価する際の重要な判断材料となります。
4.1.1 貸借対照表貸借対照表は、特定の時点における会社の資産、負債、純資産の状態を示すものです。会社の財務状態の健全性を把握するために不可欠です。
4.1.2 損益計算書損益計算書は、一定期間における会社の収益、費用、利益を示すものです。会社の収益性や費用構造を理解するために必要です。
4.1.3 キャッシュフロー計算書キャッシュフロー計算書は、一定期間における会社の現金の出入りを示すものです。会社の資金繰りの状況を把握するために重要です。
4.2 定款
定款は、会社の目的、事業内容、組織、運営方法などを定めた根本規則です。最新版の定款を用意し、内容に誤りや変更点がないか確認しましょう。
4.3 株主名簿
株主名簿は、会社の株主とその持株比率を記載した書類です。最新の株主名簿を用意し、株主構成を明確にしておきましょう。
4.4 事業計画書
事業計画書は、会社の将来的な事業展開や戦略を示すものです。過去の実績だけでなく、将来のビジョンを示すことで、買い手候補の信頼獲得に繋がります。特に、スモールM&Aにおいては、経営者のビジョンや将来性も重要な評価ポイントとなるため、事業計画書は綿密に作成する必要があります。少なくとも3~5年程度の将来予測を盛り込み、市場分析、競合分析、成長戦略などを具体的に記述しましょう。
【関連】会社売却を事業計画で有利に進める!作成手順と成功ポイント|M&A準備の必須知識4.5 契約書
重要な取引に関する契約書(例えば、主要取引先との契約書、不動産賃貸借契約書、知的財産権に関する契約書など)は、会社の事業内容や権利関係を理解するために必要です。これらの契約書の内容によっては、M&Aの成否に影響を与える可能性もあるため、事前に整理し、必要に応じて専門家によるレビューを受けましょう。
| 契約書の種別 | 内容 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 主要取引先との契約書 | 売上高に占める割合の高い取引先との契約内容 | 契約期間、取引条件、更新の可否など |
| 不動産賃貸借契約書 | 事業用不動産の賃貸借契約内容 | 契約期間、賃料、更新の可否など |
| 知的財産権に関する契約書 | 特許権、商標権、著作権などに関する契約内容 | 権利の範囲、使用許諾条件など |
| 雇用契約書 | 従業員との雇用契約内容 | 雇用形態、給与、退職金など |
| 金融機関との契約書 | 借入金に関する契約内容 | 借入額、金利、返済期間など |
上記以外にも、従業員に関する情報(従業員数、平均年齢、平均勤続年数、給与体系など)や、設備に関する情報なども必要に応じて準備しましょう。これらの情報を整理しておくことで、デューデリジェンスをスムーズに進めることができ、売却プロセス全体の効率化に繋がります。また、不明点や疑問点があれば、M&Aアドバイザーなどの専門家に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、よりスムーズかつ有利な条件でM&Aを進めることができるでしょう。
5. 買い手候補の選定と交渉
スモールM&Aにおける買い手候補の選定と交渉は、会社売却の成否を大きく左右する重要なプロセスです。適切な買い手候補を選定し、良好な関係を築きながら交渉を進めることで、売却価格の最大化や事業の継続性確保といった目標の達成に繋がります。ここでは、買い手候補の選定から交渉、最終契約までの流れを詳しく解説します。
5.1 ノンネームシートの作成
ノンネームシートとは、会社概要や財務情報を匿名化した資料のことです。買い手候補に会社情報を提供する初期段階で活用され、秘密保持の観点から重要な役割を果たします。ノンネームシートには、事業内容、従業員数、売上高、利益などの基本情報に加え、強みや今後の成長戦略なども記載します。作成にあたっては、買い手候補の興味を引くような魅力的な内容にすることが重要です。また、機密情報の漏洩を防ぐため、具体的な社名や所在地などの情報は伏せておく必要があります。
【関連】M&Aのノンネームシート作成・企業概要書との違い、記載内容と注意点5.2 秘密保持契約の締結
秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)は、会社売却に関する情報交換を行う前に、買い手候補との間で締結する重要な契約です。この契約により、買い手候補は開示された情報を第三者に開示したり、自社の利益のために利用したりすることが禁止されます。秘密保持契約を締結することで、売却活動中の情報漏洩リスクを軽減し、安心して交渉を進めることができます。
5.3 デューデリジェンス
デューデリジェンスとは、買い手候補が会社の実態を詳細に調査する手続きです。財務、法務、事業、人事など多岐にわたる分野で調査が行われ、会社の価値やリスクを評価します。デューデリジェンスは、売却価格の決定や契約条件の交渉に大きな影響を与えるため、売主側も事前に準備を整えておくことが重要です。主な調査項目は以下の通りです。
| 調査項目 | 内容 |
|---|---|
| 財務デューデリジェンス | 財務諸表の正確性、収益性、キャッシュフローなどを分析 |
| 法務デューデリジェンス | 契約書、許認可、コンプライアンス体制などを確認 |
| 事業デューデリジェンス | 事業内容、競争環境、市場動向などを分析 |
| 人事デューデリジェンス | 従業員のスキル、人事制度、労務問題などを確認 |
スムーズなデューデリジェンスの実施のため、売主側は事前に以下の情報を整理しておくことが重要です。
| 財務諸表(過去3~5年分) | |
| 事業計画書 | |
| 契約書(取引先との契約、雇用契約など) | |
| 許認可関係書類 | |
| 株主名簿 | |
| 定款 | |
| 不動産登記簿 |
これらの情報を整理し、データルームと呼ばれる仮想空間などに保管することで、買い手候補への情報提供をスムーズに行うことができます。また、想定される質問への回答を事前に準備しておくことで、デューデリジェンスを効率的に進めることができます。
【関連】M&Aで失敗しないデューデリジェンス!目的・種類・費用は?【前編】5.4 最終契約締結
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な売却価格や契約条件を交渉し、最終契約を締結します。M&Aアドバイザーなどの専門家のサポートを受けながら、自社にとって有利な条件で契約を締結することが重要です。主な交渉項目としては、売却価格、支払方法、事業の継続性、従業員の雇用維持などが挙げられます。契約締結後には、クロージングと呼ばれる手続きを経て、正式に会社 ownership が買い手へ移転します。
これらのステップを踏まえ、綿密な準備と戦略的な交渉を行うことで、スモールM&Aを成功に導くことができます。M&Aアドバイザーなどの専門家のアドバイスを活用することも、成功確率を高める上で有効な手段です。
6. まとめ
スモールM&Aによる会社売却は、事業承継や成長戦略において有効な手段となります。本記事では、売却準備の7つのステップをご紹介しました。まず、スモールM&Aの定義やメリット・デメリットを理解し、売却の適切なタイミングを見極めることが重要です。事業の成長性や収益性、経営者の年齢、後継者問題、市場環境の変化などを総合的に判断する必要があります。
次に、会社価値の算定方法を理解しましょう。DCF法、類似会社比較法、純資産法など、それぞれの評価方法の特徴を把握し、適切な方法を選択することが重要です。そして、財務諸表、定款、株主名簿、事業計画書、契約書など、必要な書類と情報を整理しておくことで、スムーズな売却プロセスを実現できます。
買い手候補の選定と交渉においては、ノンネームシートの作成、秘密保持契約の締結、デューデリジェンス、最終契約締結といったステップを踏みます。これらのステップを適切に進めることで、希望条件に近い売却を実現できる可能性が高まります。スモールM&Aは複雑なプロセスとなるため、M&Aアドバイザーなどの専門家のサポートを受けることも検討しましょう。綿密な準備と適切な情報収集によって、成功する会社売却を実現してください。


