経営再建・事業再編を成功させるための完全ガイド
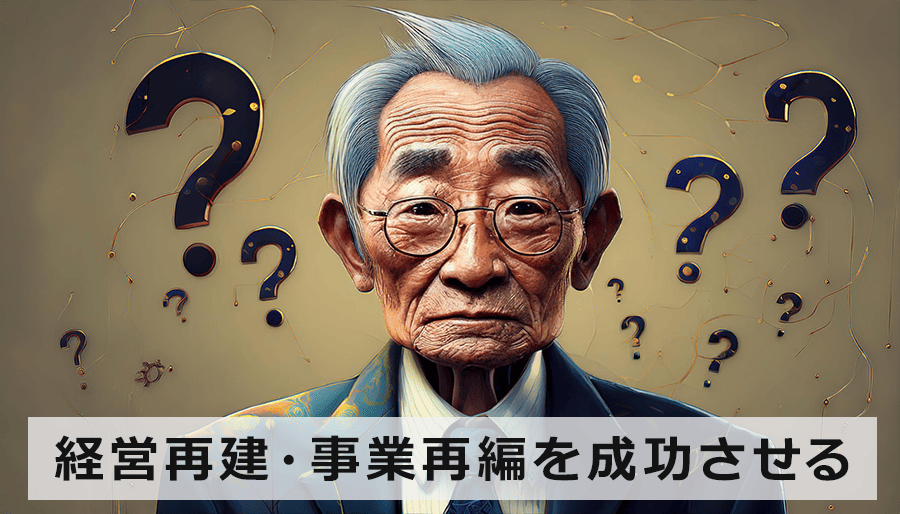
経営不振に陥り、事業の立て直しを迫られている経営者の方々、そして事業再編の必要性を感じている方々にとって、この「経営再建と事業再編を成功させるための完全ガイド」は必読の内容です。本記事では、経営再建と事業再編の定義や目的、その違いといった基本的な知識から、具体的な再建・再編の手順、成功のためのポイント、そして多様な資金調達の手法までを網羅的に解説しています。
業績悪化の兆候を見極める方法や、事業売却、会社分割、M&Aといった事業再編の種類と手法を理解することで、自社に最適な戦略を選択できるようになります。さらに、再建計画の策定、資金調達、実行、モニタリングといった各ステップにおける注意点や、弁護士、会計士、コンサルタントといった専門家の活用方法についても詳しく説明することで、再建・再編プロセスをスムーズに進めるための実践的な知識を得られます。
日本政策金融公庫や商工中金といった政府系金融機関の活用方法、近年注目を集めるクラウドファンディングといった資金調達オプションについても網羅しています。本記事を読むことで、経営危機を乗り越え、持続的な成長を実現するための道筋を明確にできるでしょう。
「経営再建(赤字解消)してからM&Aしたい」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建などを10年経験。3か月の経営支援サポートで、9か月後には赤字の会社を1億円の利益を計上させるなどの実績を多数持つ専門家。
1. 経営再建と事業再編とは何か
企業が持続的な成長を遂げるためには、外部環境や内部環境の変化に柔軟に対応し、常に最適な経営戦略を構築していく必要があります。時に、企業は業績悪化や市場の変化など、様々な困難に直面することがあります。そのような状況下で、企業の存続と成長を図るために実施されるのが経営再建と事業再編です。この章では、経営再建と事業再編の定義、目的、そして両者の違いについて詳しく解説します。
【関連】経営再建 とは? 倒産寸前の会社を再生させる方法を徹底解説!1.1 経営再建の定義と目的
経営再建とは、業績が悪化し、経営危機に陥っている企業が、その原因を分析し、経営体質を改善することで、再び収益を上げ、健全な経営状態へと回復させるための一連の取り組みのことを指します。その目的は、単に倒産を回避するだけでなく、中長期的な視点で企業価値を高め、持続的な成長を実現することにあります。具体的には、収益性の向上、財務体質の強化、競争力の強化などが挙げられます。
1.2 事業再編の定義と目的
事業再編とは、企業が経営環境の変化や戦略の転換に応じて、既存事業の見直しや新たな事業への進出など、事業ポートフォリオを再構築するために行う一連の活動を指します。その目的は、企業全体の収益性や成長性を高め、企業価値を最大化することです。
経営再建の一環として行われることもありますが、必ずしも経営危機に瀕している企業だけが実施するものではありません。成長戦略の一環として、将来性のある事業への資源集中や、非効率な事業の縮小・撤退などを目的として行われる場合もあります。
1.3 経営再建と事業再編の違い
経営再建と事業再編は、どちらも企業の立て直しを目的とする取り組みですが、その焦点と範囲が異なります。以下の表に両者の違いをまとめました。
| 項目 | 経営再建 | 事業再編 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 経営危機からの脱却、企業の存続 | 企業価値の最大化、競争力の強化 |
| 焦点 | 全社的な経営体質の改善 | 事業ポートフォリオの最適化 |
| 実施の背景 | 業績悪化、財務状況の悪化 | 市場環境の変化、経営戦略の転換 |
| 主な手法 | リストラ、コスト削減、事業売却、債務整理 | 事業売却、事業譲渡、会社分割、合併、M&A、新規事業への進出 |
経営再建は、業績悪化という緊急事態に対応するための、いわば守りの施策であるのに対し、事業再編は中長期的な成長を実現するための、攻めの施策という側面が強いと言えます。しかし、実際には両者が密接に関連しているケースも多く、経営再建の一環として事業再編が行われたり、事業再編によって経営再建が実現されることもあります。重要なのは、自社の置かれている状況を正確に把握し、最適な戦略を選択することです。
2. 経営再建が必要なサイン
企業経営において、早期に問題点を発見し対策を講じることは、その後の存続に大きく関わってきます。経営再建が必要なサインを見逃さず、適切なタイミングで対応することが重要です。 以下の兆候に複数当てはまる場合、早急な対策が必要です。
2.1 業績悪化の兆候
業績悪化は、経営再建が必要な最も明確なサインです。売上高や利益率の低下、市場シェアの減少などは、事業の持続可能性に疑問を投げかけます。
2.1.1 売上高の減少売上高の減少は、顧客のニーズの変化、競合の激化、市場の縮小など、様々な要因で起こります。継続的な売上減少は、経営の根幹を揺るがす深刻な問題です。
【関連】経営再建で売上減少を食い止める即効性対策と長期戦略2.1.2 利益率の低下
利益率の低下は、コスト増加、価格競争の激化、販売効率の悪化などが原因となります。利益率の低下は、企業の収益性を悪化させ、資金繰りを圧迫する可能性があります。
2.1.3 市場シェアの減少市場シェアの減少は、競合他社の台頭、新製品の投入、顧客ニーズの変化などが原因となります。市場シェアの減少は、企業の競争力を低下させ、将来の成長を阻害する可能性があります。
2.2 財務状況の悪化
財務状況の悪化は、経営の危機を知らせる重要なサインです。債務超過、資金繰りの悪化、滞留債権の増加などは、早急な対策が必要です。
2.2.1 債務超過債務超過とは、負債が資産を上回る状態を指します。債務超過は、企業の信用力を低下させ、資金調達を困難にする可能性があります。
2.2.2 資金繰りの悪化資金繰りの悪化は、売掛金の回収遅延、在庫の増加、過剰投資などが原因となります。資金繰りの悪化は、事業の継続を困難にする可能性があります。
2.2.3 滞留債権の増加滞留債権の増加は、顧客の倒産、経済状況の悪化などが原因となります。滞留債権の増加は、企業の財務状況を悪化させる可能性があります。
2.2.4 キャッシュフローの悪化キャッシュフローの悪化は、資金の流出入が円滑に行われていないことを示します。キャッシュフローが悪化すると、運転資金が不足し、事業継続が困難になる可能性があります。
2.3 社内体制の問題
社内体制の問題は、目に見えにくいものの、経営悪化の大きな要因となる可能性があります。意思決定の遅延、組織の硬直化、従業員のモチベーション低下などは、経営再建の必要性を示唆するサインです。
2.3.1 意思決定の遅延意思決定の遅延は、複雑な承認プロセス、責任の所在の不明確さ、情報共有の不足などが原因となります。迅速な意思決定ができないと、市場の変化への対応が遅れ、競争力を失う可能性があります。
2.3.2 組織の硬直化組織の硬直化は、縦割り組織、年功序列制度、変化への抵抗などが原因となります。組織が硬直化すると、新しいアイデアが生まれにくくなり、 innovation が阻害される可能性があります。
2.3.3 従業員のモチベーション低下従業員のモチベーション低下は、過重労働、低賃金、キャリアパスが見えないことなどが原因となります。従業員のモチベーションが低下すると、生産性が低下し、顧客満足度にも悪影響を及ぼす可能性があります。
2.3.4 不正の発生社内における不正の発生は、コンプライアンス意識の欠如や内部統制の不備を示唆します。不正は企業の信用を大きく損ない、経営危機を招く可能性があります。
| 兆候 | 内容 |
|---|---|
| 売上高の減少 | 前年比で減少傾向が続いている、競合にシェアを奪われている |
| 利益率の低下 | 原価上昇、販売価格の低下、経費の増加など |
| 資金繰りの悪化 | 運転資金の不足、借入金の返済困難 |
| 債務超過 | 負債総額が資産総額を上回る状態 |
| 従業員のモチベーション低下 | 離職率の増加、生産性の低下 |
3. 事業再編の種類と手法
事業再編には様々な手法があり、企業の置かれた状況や目指す姿によって最適な手法は異なります。以下に代表的な事業再編の手法を解説します。
3.1 事業売却
事業売却とは、企業が保有する事業の全部または一部を他の企業に売却することです。不採算事業の整理や経営資源の集中などを目的として行われます。売却価格は、事業の収益性や将来性、市場環境などを考慮して決定されます。
3.2 事業譲渡
事業譲渡とは、企業が保有する事業の全部または一部を他の企業に譲り渡すことです。事業売却と似ていますが、事業譲渡は個別の資産や負債、契約などを個別に譲渡する点が異なります。事業売却よりも柔軟な対応が可能となる場合がありますが、手続きが複雑になることもあります。
3.3 会社分割
会社分割とは、会社を分割して新しい会社を設立する、あるいは既存の会社に事業を承継させる手法です。事業部門の独立性向上やリスク分散などを目的として行われます。分割には、吸収分割、新設分割などの種類があります。
3.3.1 吸収分割吸収分割とは、分割する会社の事業を既存の他の会社に承継させる方法です。
3.3.2 新設分割新設分割とは、分割する会社の事業を新しく設立する会社に承継させる方法です。
3.4 合併
合併とは、2つ以上の会社が1つの会社に統合されることです。規模の経済によるコスト削減や経営基盤の強化などを目的として行われます。合併には、吸収合併と新設合併があります。
3.4.1 吸収合併吸収合併とは、1つの会社が他の会社を吸収する形で合併する方法です。
3.4.2 新設合併新設合併とは、2つ以上の会社が合併して新しい会社を設立する方法です。
3.5 M&A
M&A(Mergers and Acquisitions)とは、企業の合併や買収を指します。事業拡大や競争力強化などを目的として行われます。M&Aは、友好的M&Aと敵対的M&Aに大別されます。
【関連】M&A譲渡の準備内容とは?スケジュールと成功のためのポイント3.6 アウトソーシング
アウトソーシングとは、企業が自社で行っている業務の一部を外部の企業に委託することです。コスト削減や専門性の向上などを目的として行われます。アウトソーシングの対象となる業務は、経理、人事、ITなど多岐にわたります。
| 手法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 事業売却 | 事業の全部または一部を他の企業に売却 | 不採算事業の整理、経営資源の集中 | 売却価格の妥当性、従業員の雇用問題 |
| 事業譲渡 | 事業の全部または一部を他の企業に譲渡 | 柔軟な対応が可能 | 手続きが複雑 |
| 会社分割 | 会社を分割して新会社設立、または既存会社に事業承継 | 事業部門の独立性向上、リスク分散 | 分割後の事業連携、コスト増加 |
| 合併 | 2つ以上の会社が1つの会社に統合 | 規模の経済、経営基盤強化 | 組織文化の融合、意思決定の遅延 |
| M&A | 企業の合併や買収 | 事業拡大、競争力強化 | 買収価格の妥当性、PMI(合併後統合)の難しさ |
| アウトソーシング | 業務の一部を外部委託 | コスト削減、専門性の向上 | 情報漏洩リスク、品質管理の難しさ |
それぞれの事業再編にはメリット・デメリットがあり、自社の状況に合わせて最適な手法を選択することが重要です。専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めるべきです。
4. 経営再建・事業再編の手順
経営再建・事業再編は複雑なプロセスであり、綿密な計画と実行が必要です。以下に、一般的な手順をステップごとに解説します。
【関連】経営再建の方法・手順|再建計画策定から実行までを分かりやすく解説!4.1 現状分析
まずは現状を客観的に把握することが重要です。財務状況、事業の収益性、市場環境、競合状況、組織体制など、多角的な視点から分析を行います。SWOT分析や3C分析などのフレームワークを活用することで、より体系的な分析が可能になります。財務諸表だけでなく、キャッシュフローにも注目し、短期的・長期的な資金繰りの見通しを立てることが重要です。
4.1.1 財務分析貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書といった財務諸表を詳細に分析し、売上高営業利益率や自己資本比率といった指標を算出することで、企業の財務状況を数値で把握します。財務分析の結果を基に、経営上の課題を明確化します。
4.1.2 事業ポートフォリオ分析各事業の収益性や成長性を分析し、BCGマトリックスなどを用いて事業ポートフォリオを評価します。どの事業に資源を集中投下し、どの事業を縮小・撤退させるべきかを判断します。
4.1.3 市場・競合分析市場の成長性や競合企業の動向を分析し、自社の競争優位性を明確にします。ファイブフォース分析などを活用することで、市場の魅力度や競争の激しさを分析できます。
4.2 再建計画の策定
現状分析に基づき、具体的な再建計画を策定します。計画には、数値目標、実行スケジュール、責任者などを明確に記載する必要があります。また、計画は柔軟性を持たせ、状況の変化に応じて修正できる体制を整えることが重要です。KPIを設定し、進捗状況を定期的にモニタリングすることで、計画の軌道修正をスムーズに行うことができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目標 | 具体的な数値目標(例:売上高、利益率、負債比率など) |
| 施策 | 目標達成のための具体的な施策(例:コスト削減、事業売却、新規事業開発など) |
| スケジュール | 各施策の実施時期と期間 |
| 責任者 | 各施策の責任者 |
| KPI | 進捗状況を測定するための指標 |
| モニタリング方法 | KPIの測定方法と頻度 |
| コンティンジェンシープラン | 想定外の事態が発生した場合の対応策 |
4.3 資金調達
再建計画を実行するためには、必要な資金を調達する必要があります。資金調達の手法は、金融機関からの融資、増資、資産売却など、企業の状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。資金調達にあたっては、事業計画を明確に示し、投資家や金融機関からの信頼を得ることが重要です。調達した資金の使途を明確にし、返済計画についても具体的に提示する必要があります。
4.3.1 金融機関からの融資銀行や信用金庫などから融資を受ける方法です。担保や保証人が必要となる場合もあります。
4.3.2 増資株式を発行して新たな資本を調達する方法です。既存株主や新規投資家から出資を募ります。
4.3.3 資産売却保有している不動産や設備などを売却して資金を調達する方法です。
【関連】経営再建のための資金調達【最新事例と活用できる制度】4.4 実行とモニタリング
策定した再建計画に基づき、具体的な施策を実行していきます。実行段階では、計画の進捗状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて計画を修正していくことが重要です。また、ステークホルダーとのコミュニケーションを密に取り、進捗状況や課題を共有することで、理解と協力を得ることが不可欠です。PDCAサイクルを回し、継続的に改善を図ることで、再建を成功に導くことができます。
5. 経営再建・事業再編を成功させるためのポイント
経営再建と事業再編は、企業の存続と成長を左右する重要なプロセスです。成功させるためには、綿密な計画と迅速な実行、そして様々な関係者との協力が不可欠です。以下に、成功のための主要なポイントを解説します。
5.1 早期の対応
問題の早期発見と対応は、再建・再編の成功に大きく影響します。業績悪化の兆候を早期に捉え、迅速な対応を取ることで、事態の悪化を防ぎ、再建・再編の選択肢を広げることができます。財務状況の悪化や市場シェアの低下といった兆候を見逃さず、早急な対策を講じることが重要です。
5.2 専門家の活用(弁護士、会計士、コンサルタントなど)
経営再建・事業再編は複雑なプロセスであり、専門知識が必要です。弁護士、会計士、コンサルタントなどの専門家を積極的に活用することで、法的、財務的、戦略的なアドバイスを得ることができ、より効果的な再建・再編計画を策定できます。例えば、弁護士は法的リスクの評価や契約交渉、会計士は財務デューデリジェンスや再建計画の策定、コンサルタントは事業戦略の策定や実行支援などを担当します。
【関連】経営再建コンサルティングで赤字解消を実現5.2.1 専門家活用のメリット
| 客観的な視点からのアドバイス | |
| 専門知識と経験に基づく的確な判断 | |
| 時間と労力の節約 | |
| ステークホルダーへの信頼感向上 |
専門家を選ぶ際には、実績、専門性、費用などを比較検討することが重要です。複数の専門家から提案を受け、自社の状況に最適な専門家を選ぶようにしましょう。
5.3 ステークホルダーとのコミュニケーション
経営再建・事業再編は、株主、債権者、従業員、取引先、地域社会など、様々なステークホルダーに影響を与えます。透明性のあるコミュニケーションを図り、それぞれのステークホルダーの理解と協力を得ることが、再建・再編の成功には不可欠です。状況を正確に伝え、今後の見通しを共有することで、ステークホルダーの不安を軽減し、協力を得やすくなります。
| ステークホルダー | コミュニケーションのポイント |
|---|---|
| 株主 | 経営状況と再建計画の説明、将来のビジョン提示 |
| 債権者 | 返済計画の提示、透明性の高い情報開示 |
| 従業員 | 雇用への影響、今後の事業展開の説明 |
| 取引先 | 今後の取引継続に関する説明、信頼関係の維持 |
| 地域社会 | 地域経済への影響説明、地域貢献への継続的な取り組み |
5.4 従業員の理解と協力
従業員は企業の最も重要な資産です。再建・再編のプロセスにおいて、従業員の理解と協力を得ることは不可欠です。経営状況や再建計画を丁寧に説明し、従業員の不安や疑問に真摯に対応することで、モチベーションの維持と協力的な姿勢を促すことができます。
従業員が安心して仕事に取り組める環境を整備し、企業の再建・再編に積極的に参加してもらえるように働きかけることが重要です。例えば、社内説明会の実施や、提案制度の導入などを通じて、従業員の意見を積極的に取り入れる姿勢を示すことが有効です。
6. 資金調達の手法
経営再建や事業再編を成功させるには、適切な資金調達が必要です。状況に応じて最適な手法を選択することが重要です。以下、代表的な資金調達の手法を解説します。
【関連】経営再建のための資金繰り戦略|窮地を乗り越えるための虎の巻6.1 金融機関からの融資
金融機関からの融資は、最も一般的な資金調達方法です。返済義務があるため、計画的な返済計画が不可欠です。
6.1.1 銀行融資都市銀行、地方銀行、信用金庫などから融資を受ける方法です。事業計画や財務状況に基づいて融資額が決定されます。担保や保証人が必要な場合もあります。
6.1.2 政府系金融機関の活用日本政策金融公庫など、政府系金融機関は、民間金融機関よりも低利で融資を受けられる可能性があります。特に、中小企業やベンチャー企業にとっては有力な選択肢となります。公庫の融資制度には様々な種類があるので、事業内容に合った制度を選択することが重要です。
6.2 投資ファンドからの資金調達
投資ファンドは、企業の株式や社債などに投資する資金を提供します。高い成長が見込まれる企業にとって有効な資金調達方法ですが、投資ファンドからの出資を受ける際には、経営への関与や将来的な株式公開(IPO)などを検討する必要があります。
6.2.1 ベンチャーキャピタル主に未上場企業に投資を行うベンチャーキャピタルは、成長性の高い企業に対して資金を提供します。資金提供だけでなく、経営に関するアドバイスやネットワークの提供なども期待できます。
6.2.2 プライベートエクイティファンド比較的大規模な資金を提供するプライベートエクイティファンドは、経営再建や事業拡大を目指す企業に投資を行います。投資回収のため、経営への関与が強くなる傾向があります。
6.3 その他の資金調達手法
上記以外にも、様々な資金調達手法があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、状況に応じて適切な手法を選択することが重要です。
6.3.1 クラウドファンディングインターネットを通じて、不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達する方法です。リターンを設定する必要があるため、資金調達だけでなく、マーケティング効果も期待できます。近年注目されている手法です。
6.3.2 事業再生ファンド経営難に陥った企業の再建を支援することを目的としたファンドです。資金提供だけでなく、経営コンサルティングなども提供されます。再生計画の実行が求められます。
6.3.3 資産売却保有している不動産や設備などを売却することで資金を調達する方法です。短期間で資金を調達できるメリットがありますが、売却後の事業への影響を考慮する必要があります。
| 資金調達手法 | メリット | デメリット | 向いている企業 |
|---|---|---|---|
| 銀行融資 | 手続きが比較的容易 | 返済義務がある | 安定した収益基盤を持つ企業 |
| 政府系金融機関 | 低利で融資を受けられる | 審査が厳しい | 中小企業、ベンチャー企業 |
| ベンチャーキャピタル | 経営支援を受けられる | 株式の希薄化 | 高成長が見込まれる企業 |
| プライベートエクイティファンド | 大規模な資金調達が可能 | 経営への関与が強い | 事業拡大を目指す企業 |
| クラウドファンディング | マーケティング効果も期待できる | 目標金額に達しない可能性がある | 革新的な事業を行う企業 |
| 事業再生ファンド | 経営再建の支援を受けられる | 厳しい再生計画の実行が必要 | 経営難に陥った企業 |
| 資産売却 | 短期間で資金調達が可能 | 売却後の事業への影響 | 遊休資産を持つ企業 |
資金調達の手法は多岐に渡り、それぞれにメリット・デメリットがあります。自社の状況に合った最適な手法を選択することが、経営再建・事業再編の成功には不可欠です。専門家と相談しながら慎重に検討しましょう。
7. まとめ
経営再建と事業再編は、企業の存続と成長のために重要な戦略です。本記事では、それぞれの定義や目的、種類、手法、手順、成功のためのポイント、資金調達の手法について解説しました。経営再建は、業績悪化に直面した企業がその原因を分析し、財務体質を改善し、収益性を回復させるための取り組みです。
一方、事業再編は、企業の事業ポートフォリオを見直し、競争力を強化し、新たな成長機会を創出するために行われます。事業売却やM&Aなど、様々な手法が存在します。
経営再建・事業再編を成功させるためには、早期の対応、専門家の活用、ステークホルダーとのコミュニケーション、従業員の理解と協力が不可欠です。特に、弁護士、会計士、コンサルタントなどの専門家の助言は、法的、財務的なリスクを最小限に抑え、最適な戦略を策定する上で非常に重要です。
また、金融機関からの融資、政府系金融機関の活用、投資ファンドからの資金調達など、様々な資金調達の手法を検討し、状況に応じた最適な方法を選択する必要があります。再建計画の策定段階から資金調達方法を検討しておくことが重要です。
最後に、経営再建と事業再編は、困難なプロセスではありますが、適切な戦略と実行によって、企業の再生と成長を実現することができます。本記事が、経営者や関係者の皆様にとって、経営再建・事業再編を成功させるための一助となれば幸いです。


