事業承継ガイドラインとは?概要から内容、活用方法まで徹底解説!
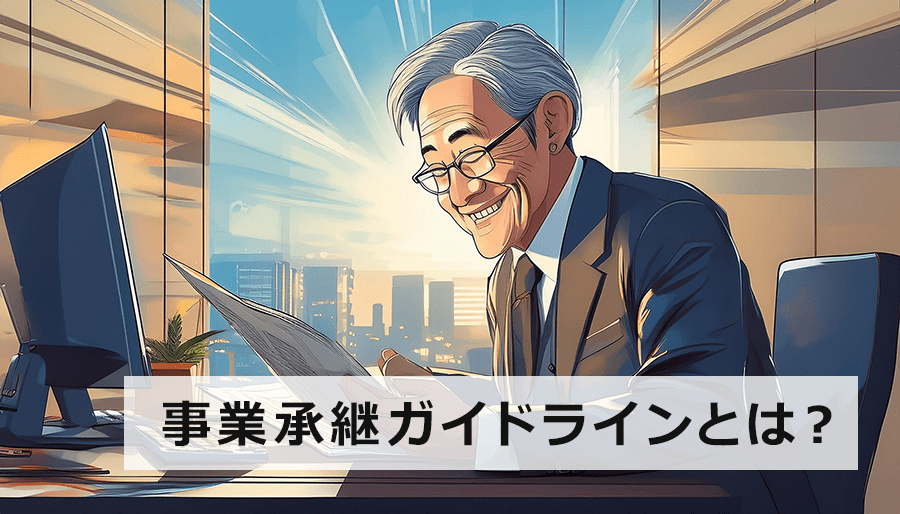
「うちの会社、そろそろ事業承継について考えないと...」と思いつつ、何から手をつければいいか分からない経営者や後継者の方も多いのではないでしょうか?
そんな悩みを解決するのが「事業承継ガイドライン」です。本記事では、事業承継ガイドラインの概要から内容、具体的な活用方法、作成時の注意点まで、事例を交えながら分かりやすく解説します。
さらに、活用できる補助金制度や、事業承継を成功に導いた企業の事例もご紹介します。事業承継ガイドラインを活用して、スムーズかつ円滑な事業承継を実現しましょう。
M&A・PMI支援のご相談はこちら
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月のPMIにて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. 事業承継ガイドラインとは
事業承継ガイドラインとは、企業の経営者が、将来的にその経営を誰に、どのように引き継ぐのかを明確化するために作成する社内文書のことです。後継者の選定方法、事業承継の方法、スケジュール、自社株対策など、事業承継に関する重要な事項を取り決め、関係者間で共有することで、円滑な事業承継を実現することを目的としています。
1.1 事業承継ガイドライン策定の背景
近年、日本企業においては、経営者の高齢化や後継者不足が深刻化しており、スムーズな事業承継が大きな課題となっています。帝国データバンクの調査によると、企業の代表者のうち約半数が60歳以上であり、後継者が決まっていない企業も少なくありません。このような状況下、事業承継を円滑に進めるために、事業承継ガイドラインを策定する企業が増えています。
また、事業承継は、単に経営者の交代にとどまらず、企業の存続、従業員の雇用、取引先の事業活動など、様々なステークホルダーに大きな影響を与えることから、その重要性に対する認識が高まっています。
1.2 事業承継ガイドラインの目的
事業承継ガイドラインを作成する目的は、大きく分けて以下の3つに集約されます。
1.2.1 円滑な事業承継の実現事業承継ガイドラインを策定することで、後継者の選定基準や承継プロセスが明確化され、関係者間での合意形成が図りやすくなります。これにより、後継者不在による事業の停滞や混乱を回避し、円滑な事業承継を実現することができます。
1.2.2 経営の透明性・客観性の確保事業承継ガイドラインは、後継者の選定や承継プロセスを客観的な基準に基づいて行うことを明確化するものであり、経営の透明性を高める効果があります。これにより、関係者からの理解と信頼を得ることができ、円滑な事業承継を進めることができます。
1.2.3 企業価値の維持・向上事業承継ガイドラインに基づいた計画的な事業承継は、経営の継続性を確保し、企業価値の維持・向上に繋がります。また、後継者育成計画を盛り込むことで、次世代経営者の育成にも役立ちます。
このように、事業承継ガイドラインは、円滑な事業承継を実現するための重要なツールとして、ますますその重要性を増しています。
【関連】【会社相続×事業承継】手続きの流れを分かりやすく解説!上手に会社を引き継ぐ方法とは?2. 事業承継ガイドラインの概要
事業承継ガイドラインは、単なる社内文書ではなく、経営者の後継者への想いを伝え、円滑な事業承継を実現するための羅針盤としての役割を担います。ここでは、その位置づけと内容について詳しく解説します。
2.1 事業承継ガイドラインの位置づけ
事業承継ガイドラインは、経営者の頭の中にある後継者への想いや、事業承継に関する様々な決定事項を明確化し、社内外に示すための文書です。これにより、後継者を含めた関係者全員が事業承継に関する共通認識を持つことができ、スムーズな事業承継を実現しやすくなります。
法的な拘束力はありませんが、作成プロセスを通じて関係者間の合意形成を図り、その内容を文書として残しておくことで、後々のトラブル防止にも役立ちます。また、金融機関や取引先からの信頼獲得にも繋がるなど、多くのメリットがあります。
2.2 事業承継ガイドラインの内容
事業承継ガイドラインに盛り込む内容は、企業の規模や業種、経営者の考え方によって異なりますが、一般的には以下の項目が含まれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 後継者の決定プロセス | 後継者の選定基準、選定方法(親族内承継、従業員承継、M&Aなど)、選定スケジュールなどを明確にします。 |
| 事業承継の方法 | 株式譲渡、事業譲渡、合併など、具体的な事業承継の方法を決定します。それぞれのメリット・デメリットも合わせて検討します。 |
| 事業承継スケジュール | 後継者育成期間、事業承継時期、経営権移行時期など、具体的なスケジュールを策定します。 |
| 自社株対策 | 後継者への株式の集中、相続税対策など、自社株に関する方針を定めます。 |
| 経営理念・ビジョン | 企業理念やビジョンを明文化することで、後継者へのスムーズな継承を図ります。 |
| 事業計画 | 今後の事業展開や目標とする売上・利益などを具体的に示すことで、後継者が将来像を描きやすくなります。 |
| 財務状況 | 会社の財務状況を把握しておくことで、後継者はスムーズに経営を引き継ぐことができます。 |
これらの項目を網羅的に盛り込むことで、実効性の高い事業承継ガイドラインを策定することができます。ただし、企業によって状況は異なるため、自社の課題やニーズに合わせて柔軟に内容を検討することが重要です。
【関連】【後継者不足に悩む中小企業必見!M&Aで事業承継を成功させる解決策とは?3. 事業承継ガイドラインの内容
事業承継ガイドラインには、円滑な事業承継を実現するために、後継者決定プロセス、事業承継方法、事業承継スケジュール、自社株対策など、多岐にわたる内容を盛り込むことが重要です。ここでは、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
3.1 後継者の決定プロセス
後継者の決定プロセスは、事業承継の成否を大きく左右する重要な要素の一つです。明確で透明性の高いプロセスを定めることで、後継者候補者や従業員、関係者からの理解と協力を得やすくなるだけでなく、後継者争いを未然に防ぐ効果も期待できます。具体的なプロセスとしては、以下の項目を盛り込むことが考えられます。
3.1.1 後継者の選定基準後継者の資質や能力、適性など、どのような基準で後継者を選定するのかを明確に定義します。例えば、「経営理念への共感」、「リーダーシップ」、「経営能力」、「財務知識」、「業界経験」などを具体的なレベル感で定めることが重要です。これらの基準は、自社の経営理念や事業内容、企業文化などを踏まえて、適切に設定する必要があります。
3.1.2 後継者候補者の選定方法後継者候補者をどのように選定するのか、具体的な方法を明記します。例えば、「現経営者の推薦」、「役員会による選出」、「外部機関による推薦」など、複数の方法を組み合わせることも可能です。重要なのは、それぞれの方法の長所と短所を理解した上で、自社にとって最適な方法を選択することです。
3.1.3 後継者教育計画後継者候補者が決定した後、スムーズに事業を引き継げるよう、具体的な教育計画を策定します。経営ノウハウの伝承、リーダーシップ研修、財務管理研修、現場研修など、後継者が必要とする知識やスキルを習得できるようなプログラムを組むことが重要です。また、経営者としての心構えや倫理観を養うことも重要な要素となります。
3.2 事業承継の方法
事業承継には、大きく分けて「親族内承継」、「従業員への承継(MBO)」、「第三者への承継(M&A)」の3つの方法があります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、自社の状況や経営者の意向、後継者の状況などを総合的に判断して、最適な方法を選択する必要があります。
| 承継方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 親族内承継 |
|
|
| 従業員への承継(MBO) |
|
|
| 第三者への承継(M&A) |
|
|
事業承継ガイドラインには、どの方法で事業承継を行うか、それぞれの方法を選択する際の条件などを明確に記載しておくことが重要です。また、選択した方法に応じて、具体的な手続きやスケジュール、必要な資金計画などを具体的に検討する必要があります。
3.3 事業承継スケジュール
事業承継は、いつまでにどのようなプロセスで進めるのか、具体的なスケジュールを策定することが重要です。スケジュールが明確になることで、経営者や後継者、従業員、関係者間で共通認識を持つことができ、計画的な事業承継を進めることができます。事業承継スケジュールは、以下の項目を考慮して作成します。
3.3.1 事業承継の開始時期事業承継をいつ開始するのか、具体的な時期を定めます。後継者の年齢や健康状態、経営状況、経済環境などを考慮して、適切な時期を判断する必要があります。一般的には、後継者が40代になるまでには、事業承継の準備を始めることが望ましいとされています。
3.3.2 後継者の決定時期後継者をいつまでに決定するのか、具体的な時期を定めます。後継者候補者への教育期間や関係者との調整期間などを考慮して、余裕を持ったスケジュールを設定することが重要です。
3.3.3 事業承継の完了時期事業承継をいつまでに完了させるのか、具体的な時期を定めます。事業の引継ぎ期間や関係者への周知期間などを考慮して、現実的なスケジュールを設定する必要があります。また、税金や法律などの専門家と相談し、手続きに必要な時間を考慮することも重要です。
【関連】事業承継の進め方ガイド|後継者と考える引継ぎ、コスト対策まで徹底解説!3.4 自社株対策
自社株対策は、事業承継において非常に重要な要素の一つです。自社株の承継方法を適切に検討しないと、後継者の負担が大きくなり、円滑な事業承継の妨げになる可能性があります。また、相続税対策としても重要な意味を持ちます。自社株対策としては、以下の方法が考えられます。
3.4.1 後継者への贈与後継者へ自社株を贈与する方法です。贈与税の負担を軽減するために、暦年贈与や相続時精算課税制度などを活用する方法があります。ただし、贈与によって後継者の株式保有率が高くなりすぎると、経営権が集中しすぎる可能性があるため注意が必要です。
3.4.2 従業員持株会への譲渡従業員持株会に自社株を譲渡する方法です。従業員のモチベーション向上や人材定着を図ることができます。ただし、従業員持株会の設立や運営には、一定の手間とコストがかかる点に留意が必要です。
3.4.3 種類株式の発行議決権制限株式や配当優先株式などの種類株式を発行し、後継者以外の株主に保有してもらう方法です。後継者が少ない資金で経営権を確保できるメリットがあります。ただし、種類株式の発行には、株主総会の特別決議が必要となるなど、手続きが複雑な点がデメリットです。
自社株対策は、会社の規模や経営状況、後継者の状況、相続税対策などを総合的に考慮して、最適な方法を選択する必要があります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが重要です。
【関連】事業承継とM&Aの違いとは?メリット・デメリット、最適な仲介会社の見極め方を解説4. 事業承継ガイドラインの活用方法
事業承継ガイドラインを作成したら、ただ保管しておくだけでは意味がありません。円滑な事業承継を実現するために、作成したガイドラインを最大限に活用していく必要があります。ここでは、事業承継ガイドラインの具体的な活用方法について解説します。
4.1 事業承継ガイドラインの作成
事業承継ガイドラインの作成は、まず現状分析から始まります。自社の置かれている状況、経営資源、後継者候補の有無などを洗い出し、経営課題や承継における課題を明確化します。その上で、具体的な事業承継の方法、後継者の選定基準、事業承継スケジュールなどを決定していきます。
4.1.1 現状分析| 自社の経営状況(売上高、利益率、財務状況など) | |
| 事業内容、商品・サービス、顧客層、競合環境など | |
| 経営資源(人材、技術、ノウハウ、ブランド力、取引先など) | |
| 後継者候補の有無、年齢、経験、能力、意欲など | |
| 家族構成、親族間の関係性など |
| 事業承継の方法(親族内承継、従業員承継、M&Aなど) | |
| 後継者の選定基準(経営能力、人望、熱意、価値観など) | |
| 事業承継スケジュール(後継者育成期間、事業承継時期など) | |
| 自社株対策(後継者への株式譲渡方法、納税対策など) | |
| 事業承継後の経営体制、事業計画、財務計画など |
事業承継ガイドラインの作成には、専門家のサポートを受けることが重要です。税理士、弁護士、中小企業診断士などの専門家は、事業承継に関する豊富な知識と経験を持ち、自社の状況に最適なアドバイスを提供してくれます。専門家の活用により、スムーズかつ円滑な事業承継を実現することができます。
4.2 関係者への周知
事業承継ガイドラインは、作成しただけでは意味がありません。後継者を含む従業員、取引先、金融機関など、関係者全体に周知徹底することが重要です。周知 methods としては、以下の様なものが考えられます。
4.2.1 社内会議や研修定期的な社内会議や研修の場で、事業承継ガイドラインの内容や目的を説明します。後継者候補には、事業承継に対する理解を深めてもらうために、個別面談や研修なども有効です。
4.2.2 社内イントラネットへの掲載社内イントラネットに事業承継ガイドラインを掲載し、いつでも閲覧できるようにします。また、関連資料やFAQなども掲載することで、従業員の理解促進を図ります。
4.2.3 書面での配布事業承継ガイドラインを冊子やパンフレットにまとめ、従業員や関係者に配布します。重要な情報なので、書面で残しておくことで、後から見返す際にも役立ちます。
4.2.4 取引先への説明主要な取引先に対しては、事業承継ガイドラインの内容を説明し、事業承継後もこれまでと変わらぬ取引を継続する意思を伝えます。取引先の不安を払拭し、信頼関係を維持することが重要です。
4.3 事業承継ガイドラインの見直し
事業承継ガイドラインは、一度作成したら終わりではありません。会社の状況や経営環境の変化に合わせて、定期的に見直しを行うことが重要です。見直し時期としては、以下の様なタイミングが考えられます。
| 見直し時期 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 毎年1回 |
|
| 後継者候補の変更時 |
|
| 会社の合併や事業譲渡時 |
|
上記以外にも、必要に応じて随時見直しを行うことが大切です。定期的な見直しを行うことで、事業承継ガイドラインを常に最新の状態に保ち、円滑な事業承継を実現することができます。
【関連】事業承継の2025年問題とは?廃業の危機!その特徴と対策をわかりやすく解説5. 事業承継ガイドラインに関する補助金・支援制度
事業承継ガイドラインの作成や事業承継には、国や地方自治体による様々な補助金・支援制度が存在します。これらの制度を活用することで、事業承継をスムーズに進め、企業の成長を促進することができます。主な補助金・支援制度は以下の通りです。
5.1 補助金 5.1.1 ものづくり補助金
経済産業省が実施する「ものづくり補助金」は、中小企業が新製品・新サービスの開発や生産プロセス改善を行う際に、その費用の一部を補助する制度です。事業承継を契機とした経営革新計画を策定し、その計画に基づいて設備投資やシステム導入等を行う場合に活用できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象者 | 中小企業者 |
| 補助率 | 事業規模・内容により異なる(例:中小企業の場合、原則として1/2以内) |
| 補助上限額 | 事業規模・内容により異なる(例:一般型の場合、1,000万円以内) |
中小企業庁が実施する「事業承継補助金」は、中小企業の円滑な事業承継を支援するために、事業承継計画の策定や専門家による指導、研修等にかかる費用の一部を補助する制度です。事業承継ガイドラインの作成も補助対象となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象者 | 中小企業者 |
| 補助率 | 事業規模・内容により異なる(例:事業承継計画の策定費用の2/3以内) |
| 補助上限額 | 事業規模・内容により異なる(例:事業承継計画の策定費用の場合は150万円以内) |
5.2 支援制度 5.2.1 事業承継税制
事業承継税制は、非上場株式等を相続や贈与によって取得した際に、一定の要件を満たせば、相続税や贈与税の納税を猶予または免除する制度です。事業承継ガイドラインを策定し、後継者が経営に参画することで、この制度の適用を受けることが有利になります。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 贈与税の納税猶予の特例 | 一定の要件を満たす場合、贈与税の納税を猶予する制度。事業承継ガイドラインに基づき後継者が議決権の過半数を取得することが要件の一つ。 |
| 相続税の納税猶予の特例 | 一定の要件を満たす場合、相続税の納税を猶予する制度。事業承継ガイドラインに基づき後継者が議決権の過半数を取得することが要件の一つ。 |
日本政策金融公庫は、中小企業向けに様々な融資制度を提供しています。事業承継を円滑に進めるための融資制度も用意されており、事業承継ガイドラインを策定することで、融資条件の優遇を受けられる場合があります。
5.2.3 商工会・商工会議所の支援商工会や商工会議所では、事業承継に関する相談窓口を設け、専門家によるアドバイスや情報提供を行っています。事業承継ガイドラインの作成支援や後継者育成セミナーなども実施しています。
これらの補助金・支援制度は、要件や申請手続きがそれぞれ異なります。事前に公的機関や専門家に相談し、自社の状況に最適な制度を活用することが重要です。
6. 事業承継ガイドライン作成の成功事例
事業承継ガイドライン作成による成功事例を、具体的な企業の例を挙げながら紹介します。これらの事例を参考に、自社にとって最適な事業承継ガイドラインの作成を目指しましょう。
6.1 株式会社A社の事例 6.1.1 企業概要
| 会社名 | 株式会社A社 |
|---|---|
| 代表者 | 田中 太郎 |
| 所在地 | 東京都〇〇区 |
| 業種 | 製造業(金属加工) |
| 従業員数 | 20名 |
| 創業 | 50年前 |
株式会社A社は、創業50年の歴史を持つ金属加工会社です。代表取締役の田中氏は70歳を迎え、後継者問題が深刻化していました。息子は2人いましたが、長男は東京都在住で会社経営、次男は家業を継ぐ意思はあるものの、経営経験が乏しいことが懸念材料でした。従業員からは、会社の将来に対する不安の声も上がっていました。
6.1.3 事業承継ガイドライン導入の経緯後継者問題の解決策を探る中で、田中社長は事業承継ガイドラインの存在を知りました。専門家のアドバイスを受けながら、息子2人と従業員代表も交えて、事業承継ガイドラインの作成に着手しました。
6.1.4 事業承継ガイドラインの内容| 後継者 | 次男を後継者に指名。ただし、経営経験を積むため、外部の経営コンサルタント会社で3年間の研修を受けることを条件とする。 |
|---|---|
| 事業承継方法 | 株式贈与と借入による株式取得を併用。後継者となる次男が、段階的に株式を取得していく計画を策定。 |
| 事業承継スケジュール | 後継者研修期間を含め、5年後の事業承継を目指す。 |
| 自社株対策 | 自社株の評価額を抑制するため、従業員持株会を設立。 |
事業承継ガイドラインの作成により、後継者、社長、従業員間で将来のビジョンや事業承継に関する認識を共有することができました。次男は経営者としての自覚を深め、従業員も安心して業務に専念できる環境が整いました。また、自社株対策を講じることで、円滑な事業承継に向けた準備も進んでいます。
6.2 株式会社B社の事例 6.2.1 企業概要
| 会社名 | 株式会社B社 |
|---|---|
| 代表者 | 佐藤 花子 |
| 所在地 | 大阪府〇〇市 |
| 業種 | 小売業(食品スーパー) |
| 従業員数 | 50名 |
| 創業 | 30年前 |
株式会社B社は、地域密着型の食品スーパーマーケットを経営しています。社長の佐藤さんは、長年会社を牽引してきましたが、後継者となる親族はおらず、従業員に事業を承継させることを検討していました。しかし、適切な後継者候補が見つからず、事業承継が難航していました。
6.2.3 事業承継ガイドライン導入の経緯佐藤社長は、商工会議所のセミナーで事業承継ガイドラインについて学び、自社の状況に合致すると考えました。従業員の中から後継者を育成するため、事業承継ガイドラインの作成を決意しました。
6.2.4 事業承継ガイドラインの内容| 後継者 | 後継者候補となる従業員を公募。選考基準は、経営理念への理解度、リーダーシップ、業務遂行能力など。 |
|---|---|
| 事業承継方法 | MBO(マネジメント・バイアウト)による事業承継を採用。後継者となる従業員が、金融機関からの融資と自己資金を合わせて株式を取得する計画。 |
| 事業承継スケジュール | 後継者決定後、3年後の事業承継を目指す。 |
| 従業員への周知 | 事業承継ガイドラインの内容を全従業員に説明し、透明性を確保。 |
事業承継ガイドラインを策定したことで、後継者選定の基準が明確化され、従業員のモチベーション向上に繋がりました。また、MBOによる事業承継を計画することで、後継者となる従業員は、経営者としての責任感と当事者意識を高めることができました。結果として、円滑な事業承継と、地域社会への貢献を継続できる体制を構築することができました。
7. 事業承継ガイドライン作成の注意点
事業承継ガイドラインは、ただ作成すれば良いというものではありません。円滑な事業承継を実現するためには、作成過程でいくつかの注意点を押さえておく必要があります。
7.1 専門家への相談
事業承継ガイドラインの作成は、会社法、税法、相続法など、専門的な知識を必要とする場面が多くあります。そのため、弁護士、税理士、中小企業診断士などの専門家に相談しながら進めることが重要です。専門家は、企業の状況に合わせて、最適なアドバイスを提供してくれます。
| 専門家 | 相談内容例 |
|---|---|
| 弁護士 | 事業承継ガイドラインの内容の法的妥当性、後継者決定に関する法的問題、遺言書作成のアドバイス |
| 税理士 | 事業承継税制の活用、自社株対策、納税対策 |
| 中小企業診断士 | 事業承継計画の策定支援、後継者育成計画の策定支援、経営改善計画の策定支援 |
| 専門知識に基づいたアドバイスを受けられる | |
| 法的リスクや税務リスクを回避できる | |
| 時間と労力を節約できる |
7.2 関係者間の合意形成
事業承継ガイドラインは、後継者、現経営者、家族、従業員など、多くの関係者の利害に関わるものです。そのため、作成過程においては、関係者に対して、事業承継の必要性やガイドラインの内容について、丁寧に説明し、理解と合意を得ることが重要です。合意形成を怠ると、後々トラブルが発生する可能性があります。
7.2.1 合意形成を図るためのポイント| 早期からの情報共有とコミュニケーション | |
| 関係者全員が納得できる内容にする | |
| 意見交換の場を定期的に設ける |
7.3 柔軟な運用
事業承継ガイドラインは、一度作成したら終わりではなく、状況の変化に応じて、柔軟に見直しを行うことが重要です。例えば、経営環境の変化、後継者の状況の変化、法律の改正などがあった場合には、ガイドラインの内容を見直す必要があります。定期的な見直しを行い、常に実態に合った内容にすることで、円滑な事業承継を実現することができます。
7.3.1 見直しを検討すべきタイミング| 経営環境が大きく変化した時 | |
| 後継者の状況が変化した時(結婚、出産、病気など) | |
| 法律や税制が改正された時 | |
| 定期的な見直し(3~5年ごと) |
これらの注意点を踏まえ、専門家のサポートを受けながら、関係者間の合意形成を図り、事業承継ガイドラインを作成・運用していくことが、円滑な事業承継、ひいては企業の永続的な発展につながります。
8. まとめ
事業承継ガイドラインは、円滑な事業承継を実現するために非常に重要なツールです。後継者の決定プロセスや事業承継の方法、スケジュールなどを明確化することで、関係者間のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな事業承継を実現することができます。
事業承継ガイドラインの作成には、専門家のサポートを受けることや、関係者間の合意形成が不可欠です。これらのポイントを踏まえ、自社にとって最適な事業承継ガイドラインを作成し、事業の安定と発展を目指しましょう。


