M&A補助金の完全ガイド!申請方法から注意点など徹底解説
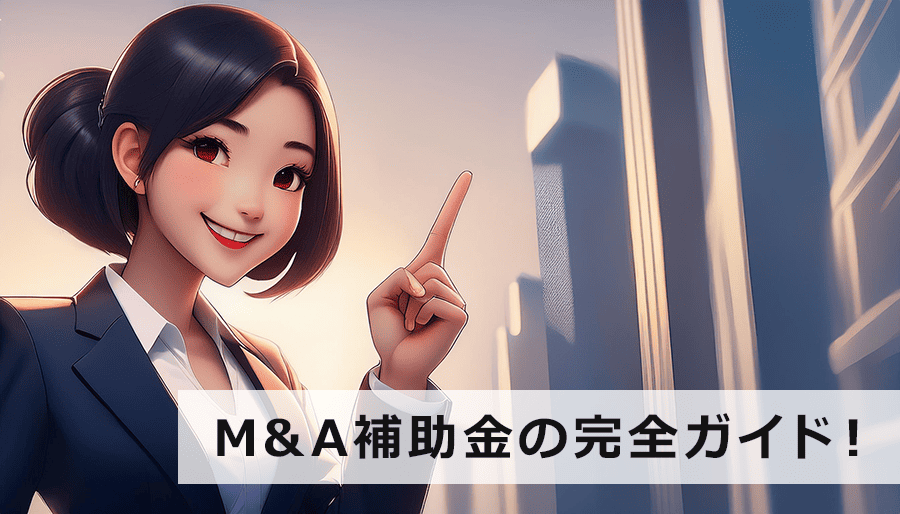
M&Aを検討中だけど、資金繰りが不安...そんな経営者の方へ。M&Aには活用できる補助金が存在します。本記事では、M&A補助金の概要から申請方法、審査基準、注意点までを網羅的に解説。補助金の種類(事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI促進枠、廃業・再チャレンジ枠)や、それぞれの申請に必要な書類、スケジュール、審査のポイントまで詳しく説明します。
さらに、補助金申請コンサルタントの選び方や不正受給のリスクと対策など、M&A補助金を活用する上で知っておくべき情報も提供。この記事を読めば、M&A補助金を活用して、資金調達の不安を解消し、スムーズなM&Aを実現するための道筋が見えてきます。
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
M&A補助金とは、中小企業庁が実施する、中小企業の合併・買収(M&A)を支援するための補助金制度です。 正式名称は「事業承継・事業再編補助金」で、事業承継を円滑に進めるため、M&Aにかかる費用の一部を補助するものです。後継者不足に悩む中小企業の事業承継を促進し、日本経済の活性化を図ることを目的としています。この補助金は、M&Aを検討している企業にとって、資金調達の一助となるだけでなく、M&Aプロセス全体の円滑化にも貢献しています。
【参考】中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf1.1 M&A補助金の概要
M&A補助金は、M&Aにかかる費用の一部を補助する制度です。補助対象となる費用には、M&Aアドバイザーへの手数料、デューデリジェンス費用、弁護士費用、登記費用などが含まれます。補助率は、M&Aの類型や規模によって異なりますが、一般的には費用の1/2から2/3程度が補助されます。補助上限額も類型によって異なり、数百万から数千万円まで幅があります。例えば、中小企業の事業承継を目的としたM&Aの場合、補助上限額は高く設定されている傾向があります。
1.2 M&A補助金の目的M&A補助金の主な目的は、中小企業の事業承継問題の解決と、日本経済の活性化です。後継者不足により廃業を余儀なくされる中小企業は少なくありません。M&Aは、後継者問題を解決する有効な手段の一つであり、この補助金を通じてM&Aを促進することで、事業の継続性を確保し、雇用を守り、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。また、M&Aによる経営資源の集約や事業再編を通じて、中小企業の競争力強化を図ることも目的としています。
1.3 事業承継促進枠とは?事業承継促進枠は、後継者不足に悩む中小企業の事業承継を支援するための枠組みです。後継者への株式譲渡や第三者への事業譲渡など、事業承継を目的としたM&Aに対して重点的に補助を行います。この枠組みでは、他の枠組みと比較して補助率や補助上限額が優遇されている場合があり、円滑な事業承継を後押しします。また、事業承継計画の策定支援なども行われており、総合的なサポート体制が整っています。
1.4 専門家活用枠とは?専門家活用枠は、M&Aのプロセスにおいて、弁護士、公認会計士、税理士、M&Aアドバイザーなどの専門家を活用する場合に利用できる枠組みです。専門家を活用することで、M&Aの円滑な実施やリスクの軽減が期待できます。この枠組みでは、専門家への費用に対する補助が手厚くなっている場合があり、専門家の活用を促進することで、より質の高いM&Aの実現を目指しています。
1.5 PMI促進枠とは?PMI(Post Merger Integration)促進枠は、M&A後の統合プロセス(PMI)を支援するための枠組みです。M&A後の統合は、M&Aの成否を左右する重要なプロセスであり、組織文化の融合、業務プロセスの統合、人事制度の統一など、様々な課題に取り組む必要があります。この枠組みでは、PMIに関するコンサルティング費用や研修費用などが補助対象となり、円滑な統合を支援することで、M&Aの成功確率を高めることを目指しています。
1.6 廃業・再チャレンジ枠とは?廃業・再チャレンジ枠は、廃業を検討している中小企業の経営者や、廃業後に新たな事業に挑戦する経営者を支援するための枠組みです。廃業に伴うM&Aや、新たな事業を始めるためのM&Aに対して補助を行います。この枠組みは、経営者の再チャレンジを支援することで、経済の活性化に貢献することを目的としています。
2. M&A補助金の申請方法M&A補助金の申請は、煩雑な手続きが必要となる場合もあります。スムーズな申請のために、必要な書類、申請の流れとスケジュール、そして申請時の注意点などを詳しく解説します。事前にしっかりと準備することで、申請プロセスを円滑に進めることができます。
2.1 申請に必要な書類M&A補助金の申請には、様々な書類が必要です。主な書類は以下の通りですが、具体的な必要書類は、補助金の種類や公募時期によって異なる場合があるので、最新の公募要領を確認することが重要です。
| 書類名 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 交付申請書 | 補助金の交付を申請するための書類。申請者情報、事業計画、補助金額などを記載します。 | 正確な情報を入力し、漏れがないように注意しましょう。 |
| 事業計画書 | M&Aの目的、買収対象企業の情報、M&A後の事業展開などを具体的に記載します。 | 実現可能性が高く、地域経済への貢献が明確に示されている必要があります。数値目標を設定し、具体的な施策を説明することが重要です。 |
| 登記事項証明書 | 申請者および買収対象企業の登記事項証明書。 | 発行日から3ヶ月以内のものが必要です。 |
| 財務諸表 | 申請者および買収対象企業の直近数期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)。 | 会社の財務状況を把握するために必要です。 |
| M&A契約書(案) | 買収対象企業との間のM&A契約書の案。 | 契約内容が補助金の目的に合致している必要があります。 |
| 専門家活用に関する書類(専門家活用枠の場合) | M&Aに係る専門家(弁護士、公認会計士、税理士等)の活用状況を示す書類。 | 専門家の選定理由や費用などを記載します。 |
| PMI計画書(PMI促進枠の場合) | M&A後の統合プロセス(PMI)に関する計画書。 | 統合スケジュール、組織体制、シナジー効果などを具体的に記載します。 |
M&A補助金の申請は、一般的に以下の流れで行われます。スケジュールは公募時期によって異なるため、最新の情報を必ず確認してください。
- 公募情報の確認: 経済産業省や中小企業庁のウェブサイトなどで、最新の公募情報を確認します。
- 申請書類の準備: 必要な書類を揃えます。公募要領に記載されているチェックリストなどを活用すると便利です。
- 申請書の提出: オンラインシステムまたは郵送で申請書類を提出します。締め切りに遅れないように注意しましょう。
- 審査: 提出された申請書類に基づいて審査が行われます。
- 交付決定: 審査結果に基づき、補助金の交付が決定されます。
- 補助事業の実施: 交付決定通知を受け取った後、M&Aを実行します。
- 実績報告: M&A完了後、実績報告書を提出します。
- 補助金の交付: 実績報告書の内容が確認された後、補助金が交付されます。
M&A補助金の申請時には、以下の点に注意しましょう。
- 公募要領の熟読: 最新の公募要領を必ず確認し、要件や手続きを理解しましょう。過去の公募要領を参考にせず、必ず最新の情報を確認することが重要です。
- 正確な情報入力: 申請書類には、正確な情報を漏れなく入力しましょう。誤りや漏れがあると、審査に影響する可能性があります。
- 期限厳守: 申請期限を厳守しましょう。期限を過ぎると、申請を受け付けてもらえない場合があります。
- 相談窓口の活用: 申請に関する疑問点があれば、各地域の相談窓口に問い合わせましょう。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな申請が可能になります。 例えば、全国の商工会議所や商工会などが相談窓口として機能しています。
- 補助金制度の変更: 補助金制度は、社会情勢や経済状況に応じて変更される可能性があります。常に最新の情報に注意を払い、必要に応じて申請内容を修正するなど、柔軟な対応が必要です。
これらの情報を参考に、M&A補助金を活用して、事業の成長と発展を目指しましょう。補助金申請は複雑なプロセスとなる場合もありますが、事前の準備と適切な情報収集によって、成功の可能性を高めることができます。
3. M&A補助金の審査基準M&A補助金の審査は、経済産業省またはその委託先によって行われます。審査基準は公表されていませんが、過去の採択事例や公募要領などから、いくつかのポイントを推測することができます。補助金交付の可否は、これらのポイントを総合的に判断して決定されます。
3.1 審査のポイントM&A補助金の審査では、以下のポイントが重要視されると考えられます。
| 審査項目 | 詳細 |
|---|---|
| 事業の innovativeness | M&Aによって、新たな製品・サービスの開発、新市場への参入など、イノベーションが創出されるか。既存事業の単なる規模拡大ではなく、新規性や独創性が評価されます。例えば、地域経済の活性化や新たな雇用の創出に繋がる事業であるかなども考慮されます。 |
| 事業計画の具体性・実現可能性 | M&A後の事業計画が具体的かつ実現可能であるか。目標数値の根拠、市場分析、競合分析、リスク対策などが明確に示されている必要があります。売上高や利益などの財務計画だけでなく、事業戦略、マーケティング戦略、人員計画なども含めた包括的な計画が求められます。 |
| M&Aの必要性・妥当性 | M&Aが事業目的の達成に必要不可欠であり、その手法が妥当であるか。M&A以外の選択肢も検討した上で、M&Aが最適な手段であることを論理的に説明する必要があります。買収価格の妥当性についても、デューデリジェンスの結果などを踏まえて説明する必要があります。 |
| 経営基盤の安定性 | M&A後も、健全な財務状況を維持できるか。自己資本比率、キャッシュフロー、債務償還能力などが評価されます。M&Aによって財務状況が悪化しないよう、資金調達計画も併せて提出する必要があります。 |
| 地域経済への貢献 | M&Aが地域経済の活性化に貢献するか。雇用創出、地域産業の振興、地域課題の解決などに繋がるかなどが評価されます。地方創生への寄与も重要なポイントとなります。 |
| 事業承継の円滑化(事業承継促進枠の場合) | 後継者不足の問題を解消し、円滑な事業承継を実現できるか。後継者への経営権の移譲、経営体制の整備、事業の継続性などが評価されます。 |
| 専門家活用の適切性(専門家活用枠の場合) | M&Aにおける専門家(弁護士、会計士、税理士など)の活用が適切であるか。専門家の選定理由、費用、役割分担などが明確に示されている必要があります。 |
| PMIの有効性(PMI促進枠の場合) | M&A後の統合プロセス(PMI)が適切に計画され、実行されるか。組織統合、人事制度統合、システム統合などが円滑に進められる計画であるか評価されます。 |
| 再チャレンジ支援の妥当性(廃業・再チャレンジ枠の場合) | 廃業を伴うM&Aが、事業再構築や再チャレンジに繋がるか。再チャレンジに向けた具体的な計画や、その実現可能性が評価されます。 |
M&A補助金の審査期間は、公募要領によって異なります。一般的には、申請書類の提出から数ヶ月程度かかります。審査状況によっては、さらに時間を要する場合もあります。申請前に、最新の公募要領で審査期間を確認しておきましょう。
審査結果については、書面で通知されます。採択された場合は、補助金交付の手続きに進みます。不採択の場合でも、不採択理由が通知されるため、次回以降の申請に活かすことができます。
4. M&A補助金活用における注意点M&A補助金を活用する際には、いくつかの注意点があります。補助金を受けるためには、適切な手続きとルールを遵守することが重要です。以下では、M&A補助金活用における注意点を詳しく解説します。
4.1 補助金申請コンサルタントの選び方M&A補助金の申請は複雑な手続きを伴うため、補助金申請コンサルタントに依頼することを検討する企業も多いでしょう。しかし、コンサルタントの質は様々です。適切なコンサルタント選びが、補助金申請の成否を左右すると言っても過言ではありません。
4.1.1 コンサルタント選びのポイント実績と経験:M&A補助金の申請支援実績が豊富で、様々な業種のM&A案件に精通しているコンサルタントを選ぶことが重要です。成功事例や具体的な実績を確認しましょう。
専門知識:M&Aに関する法律、会計、税務などの専門知識を有し、的確なアドバイスを提供できるコンサルタントを選びましょう。資格の有無も確認すると良いでしょう。
コミュニケーション能力:円滑なコミュニケーションが取れるコンサルタントを選ぶことは、スムーズな申請手続きを進める上で重要です。相談しやすく、疑問点に丁寧に答えてくれるコンサルタントを選びましょう。
費用体系:コンサルタントの費用体系は様々です。成功報酬型、時間制など、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社に合った費用体系のコンサルタントを選びましょう。料金体系が明確で、不明瞭な追加費用が発生しないかを確認することも重要です。
アフターフォロー:補助金交付決定後も、事業計画の実施や実績報告など、継続的なサポートを提供してくれるコンサルタントを選びましょう。
複数のコンサルタントに相談し、比較検討することで、自社に最適なコンサルタントを見つけることができます。
4.2 不正受給のリスクと対策M&A補助金の不正受給は、重大な問題です。不正受給が発覚した場合、補助金の返還だけでなく、加算金や刑事罰が科される可能性もあります。不正受給のリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。
4.2.1 不正受給の事例虚偽の申請:実際には行っていないM&Aを装って補助金を申請する。
水増し請求:M&Aにかかった費用を水増しして補助金を請求する。
目的外使用:補助金をM&A以外の目的で使用する。
申請書類の正確な作成:申請書類には、正確な情報を記載する必要があります。不明な点がある場合は、担当者に確認しましょう。
証拠書類の保管:M&Aにかかった費用を証明する書類は、適切に保管しておく必要があります。領収書や契約書などは、大切に保管しましょう。
コンサルタントとの連携:コンサルタントに相談し、適切なアドバイスを受けることも重要です。
補助金に関する規定の理解:補助金に関する規定をしっかりと理解し、ルールを遵守することが重要です。交付要綱などを熟読し、不明な点は担当者に確認しましょう。
| 不正受給の種類 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|
| 虚偽申請 | 実際には行っていないM&Aを装って補助金を申請 | 補助金返還、加算金、刑事罰 |
| 水増し請求 | M&Aにかかった費用を水増しして補助金を請求 | 補助金返還、加算金、刑事罰 |
| 目的外使用 | 補助金をM&A以外の目的で使用 | 補助金返還、加算金 |
M&A補助金を適切に活用するためには、これらの注意点に留意し、不正受給のリスクを回避することが不可欠です。補助金に関する最新情報や変更点にも注意を払い、常に正しい情報に基づいて行動しましょう。
【関連】事業承継・引継ぎ補助金を活用しよう!概要・申請方法・成功事例を紹介5. まとめ
M&A補助金は、事業承継や成長戦略において有効な資金調達手段となります。事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI促進枠、廃業・再チャレンジ枠など、様々な枠組みがあり、それぞれの目的に合った活用が可能です。申請にあたっては、必要な書類やスケジュール、審査基準などを事前にしっかりと確認することが重要です。
補助金申請コンサルタントの活用も有効ですが、適切な業者選びが不可欠です。また、不正受給のリスクを理解し、適切な対策を講じる必要があります。これらのポイントを踏まえ、M&A補助金を効果的に活用することで、企業の成長と発展に繋げましょう。


