経営再建でキャッシュフロー改善!ステップバイステップ完全ガイド
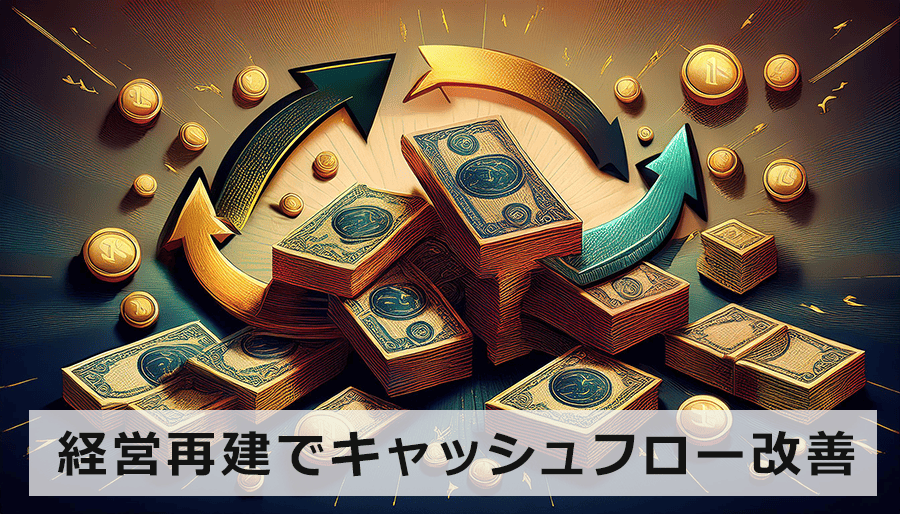
経営再建を成功させるためには、キャッシュフローの改善が不可欠です。資金繰りが悪化すると、事業継続が困難になり、最悪の場合、倒産に追い込まれる可能性もあります。しかし、キャッシュフローの重要性を理解し、適切な対策を講じることで、企業の再生は可能です。この記事では、経営再建におけるキャッシュフロー改善の重要性を解説し、キャッシュフロー悪化の兆候の見つけ方から、具体的な改善ステップ、成功事例までをステップバイステップで分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、キャッシュフロー計算書の見方や、売掛金回収期間の短縮、在庫回転率の向上、不要資産の売却、経費削減といった具体的なキャッシュフロー改善策を理解し、実践できるようになります。さらに、定期的なモニタリングと改善策の見直しによって、持続的なキャッシュフローの改善を実現する方法も学ぶことができます。経営再建に直面している経営者の方々、財務担当者の方々にとって、必読の内容となっています。
「経営再建(赤字解消)してからM&Aしたい」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建などを10年経験。3か月の経営支援サポートで、9か月後には赤字の会社を1億円の利益を計上させるなどの実績を多数持つ専門家。
1. 経営再建におけるキャッシュフローの重要性
企業が経営再建に取り組む際、キャッシュフローの改善は最も重要な要素の一つです。なぜなら、キャッシュフローは企業の血液とも言えるものであり、これが滞ると事業継続が困難になるからです。どんなに素晴らしいビジネスモデルや優れた製品・サービスを持っていても、資金がショートすれば倒産に繋がりかねません。特に、経営再建中の企業は、金融機関からの融資が難しく、資金調達が容易ではない状況にあるため、キャッシュフロー管理の重要性はより一層高まります。
経営再建においては、利益の最大化よりも、キャッシュフローの最大化が優先されるべきです。利益はあくまでも会計上の概念であり、必ずしも手元資金の増加に直結するわけではありません。一方、キャッシュフローは実際に手元に入る資金の流れを示すため、企業の存続に直結する指標となります。経営再建中は、短期的な利益よりも、長期的な安定経営を実現するための資金確保を最優先にする必要があります。
キャッシュフローが健全であれば、
| 運転資金を確保できる | |
| 設備投資や研究開発への投資が可能になる | |
| 借入金の返済をスムーズに行える | |
| 従業員への給与支払いを滞りなく行える | |
| 取引先への支払いを遅延させずに済む |
など、企業活動を円滑に進めることができます。逆に、キャッシュフローが悪化すると、これらの活動が滞り、最悪の場合、倒産に追い込まれる可能性があります。
また、キャッシュフローは、企業の財務状況を評価する上で重要な指標となります。金融機関や投資家は、企業のキャッシュフロー状況を精査し、融資や投資の判断材料とします。そのため、経営再建を成功させるためには、キャッシュフローを改善し、健全な財務状況を構築することが不可欠です。
【関連】経営再建 とは? 倒産寸前の会社を再生させる方法を徹底解説!1.1 キャッシュフローと利益の違い
キャッシュフローと利益は、どちらも企業の業績を測る重要な指標ですが、その意味合いは大きく異なります。利益は一定期間における収益から費用を差し引いたもので、企業の収益性を示す指標です。一方、キャッシュフローは、一定期間における実際の現金の流入と流出を示す指標です。利益が出ていても、売掛金が回収できていなかったり、在庫が増加していたりすると、キャッシュフローは悪化することがあります。
| 項目 | 利益 | キャッシュフロー |
|---|---|---|
| 定義 | 一定期間の収益 - 費用 | 一定期間の現金流入 - 現金流出 |
| 目的 | 収益性を測る | 資金繰りの状況を測る |
| 性質 | 会計上の概念 | 実際の資金の流れ |
1.2 キャッシュフロー経営の重要性
経営再建においては、「キャッシュフロー経営」という考え方が重要になります。キャッシュフロー経営とは、利益ではなくキャッシュフローを重視した経営のことです。具体的には、キャッシュフロー計算書に基づいて経営判断を行い、キャッシュフローの最大化を目指します。
キャッシュフロー経営を実践することで、資金繰りを安定させ、企業の存続と成長を図ることができます。特に、経営再建中は、キャッシュフロー経営を徹底することで、資金ショートのリスクを回避し、再建計画をスムーズに進めることができます。
2. キャッシュフロー悪化の兆候を見つける
キャッシュフローが悪化しているとき、その兆候は様々な形で現れます。早期に兆候を捉え、適切な対策を講じることで、経営の悪化を防ぐことが可能です。キャッシュフロー悪化の兆候は、大きく分けて「売上高は好調なのに資金繰りが苦しい」「売掛金回収の長期化」「在庫の増加」「設備投資の過剰」などがあります。これらの兆候を理解し、自社の状況を把握することで、適切な対策を立てることができます。
2.1 売上高は好調なのに資金繰りが苦しい場合
売上高は伸びているにも関わらず、資金繰りが苦しい場合、キャッシュフローが悪化している可能性が高いです。これは、売上が計上されていても、実際の入金が遅れている場合に起こります。例えば、売掛金の回収が遅延していたり、過剰な在庫を抱えているなどが原因として考えられます。このような状況では、黒字倒産のリスクも高まるため、早急な対策が必要です。
【関連】経営再建のための資金繰り戦略|窮地を乗り越えるための虎の巻2.2 売掛金回収の長期化
売掛金回収の長期化は、キャッシュフロー悪化の大きな要因となります。顧客への請求から入金までの期間が長引くほど、手元の資金が不足し、資金繰りが悪化します。売掛金回収期間の長期化は、顧客の倒産リスクも高めるため、注意が必要です。顧客の信用調査を徹底したり、支払条件の見直し、請求書の発行を迅速に行うなどの対策が重要です。
売掛金回収期間の長期化の原因を特定することも重要です。例えば、請求書の発行が遅れている、顧客とのコミュニケーション不足、支払方法の選択肢が少ないなどが考えられます。これらの原因を特定し、改善することで、売掛金回収期間を短縮し、キャッシュフローを改善することができます。
2.3 在庫の増加
在庫の増加は、キャッシュフローを圧迫する要因となります。過剰な在庫は、保管コストや陳腐化リスクを高めるだけでなく、運転資金を固定化し、資金繰りを悪化させます。適切な在庫管理を行うことで、在庫の増加を防ぎ、キャッシュフローを改善することが可能です。
在庫増加の原因としては、需要予測の誤り、過剰な仕入れ、販売不振などが考えられます。これらの原因を分析し、適切な在庫管理システムを導入することで、在庫量を最適化し、キャッシュフローを改善することができます。例えば、ジャストインタイム方式の導入や、需要予測の精度向上などが有効な対策となります。
2.4 設備投資の過剰
設備投資は、将来の収益拡大のために必要ですが、過剰な投資はキャッシュフローを悪化させる可能性があります。設備投資は多額の資金を必要とするため、投資計画を慎重に検討し、キャッシュフローへの影響を考慮することが重要です。投資の回収期間や、投資による収益増加の見込みなどをしっかりと分析し、無理のない投資計画を立てることが大切です。
設備投資の過剰によるキャッシュフロー悪化を防ぐためには、投資計画の精査に加えて、リースやレンタルなどの活用も検討するべきです。また、既存設備の有効活用や、設備投資のタイミングを調整するなど、キャッシュフローへの負担を軽減するための工夫も重要です。
| 兆候 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 売上高好調だが資金繰りが苦しい | 売掛金回収の遅延、過剰在庫 | 回収期間短縮、在庫削減 |
| 売掛金回収の長期化 | 顧客の支払遅延、請求書の発行遅れ、督促不足 | 顧客の信用調査、支払条件の見直し、請求書の迅速な発行、定期的な督促 |
| 在庫の増加 | 需要予測の誤り、過剰な仕入れ、販売不振 | 需要予測の精度向上、適正在庫管理、販売促進 |
| 設備投資の過剰 | 将来の需要を見誤った投資、投資計画の不備 | 投資計画の精査、リースやレンタルの活用、既存設備の有効活用 |
3. キャッシュフロー計算書の見方
キャッシュフロー計算書は、一定期間における企業のキャッシュの増減を示す財務諸表です。損益計算書や貸借対照表と合わせて、企業の財務状況を分析するために不可欠な資料です。キャッシュフロー計算書を理解することで、企業の資金繰りの実態を把握し、経営再建に向けた適切な対策を講じることができます。キャッシュフロー計算書は、主に以下の3つの区分から構成されています。
3.1 営業キャッシュフロー
営業キャッシュフローは、本業の事業活動によって生み出されたキャッシュフローを示します。具体的には、商品の販売やサービスの提供による収入、仕入や人件費、その他営業費用による支出などが含まれます。営業キャッシュフローがプラスであれば、本業でキャッシュを生み出せていることを示し、マイナスの場合は、本業でキャッシュが不足していることを意味します。経営再建においては、営業キャッシュフローをプラスに転換させる、あるいはプラス幅を拡大させることが重要です。計算方法は以下の通りです。
3.1.1 営業キャッシュフローの計算方法営業キャッシュフローには、直接法と間接法の2つの計算方法があります。
3.1.1.1 直接法直接法は、実際のキャッシュの収入と支出を集計して算出する方法です。より実態に近いキャッシュフローを把握できます。
| 現金売上高 | |
| 売掛金回収額 | |
| 仕入支払額 | |
| 人件費支払額 | |
| 賃借料支払額 | |
| 水道光熱費支払額 |
間接法は、当期純利益をベースに、キャッシュの増減に影響を与えない項目を調整して算出する方法です。計算が比較的容易であるため、多くの企業で採用されています。
| 当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 売掛金増加額 | |
| 在庫増加額 |
3.2 投資キャッシュフロー
投資キャッシュフローは、将来の事業活動のための投資によって生じたキャッシュフローを示します。具体的には、有形固定資産(土地、建物、機械など)や無形固定資産(特許権、商標権など)の取得・売却、投資有価証券の購入・売却などが含まれます。一般的に、成長企業では投資キャッシュフローはマイナスになりやすく、成熟企業ではプラスになる傾向があります。経営再建においては、投資を抑制することでキャッシュアウトフローを減少させることが重要となる場合もあります。
3.3 財務キャッシュフロー
財務キャッシュフローは、資金調達によって生じたキャッシュフローを示します。具体的には、借入による資金調達、社債の発行、株式の発行、配当金の支払などが含まれます。財務キャッシュフローは、企業の資金調達能力を示す指標となります。経営再建においては、新たな資金調達や既存借入金の返済条件の変更など、財務キャッシュフローを適切に管理することが重要です。
| キャッシュフロー区分 | プラスの場合 | マイナスの場合 |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 本業でキャッシュを生み出せている | 本業でキャッシュが不足している |
| 投資キャッシュフロー | 資産売却などによりキャッシュを得ている | 設備投資などによりキャッシュが出ている |
| 財務キャッシュフロー | 借入などにより資金調達を行っている | 借入金の返済や配当金の支払を行っている |
これら3つのキャッシュフローを総合的に分析することで、企業全体のキャッシュフローの状況を把握することができます。経営再建においては、キャッシュフロー計算書を詳細に分析し、キャッシュフローの改善に向けた具体的な対策を立案・実行することが不可欠です。
例えば、営業キャッシュフローがマイナスの場合は、売上高の増加、経費削減、売掛金回収期間の短縮、在庫回転率の向上など、キャッシュフローを改善するための施策を検討する必要があります。また、投資キャッシュフローが過度にマイナスの場合は、投資計画の見直しや不要資産の売却などを検討する必要があります。
財務キャッシュフローにおいては、新たな資金調達や既存借入金のリスケジュールなどを検討する必要があるでしょう。これらの施策を通じて、健全なキャッシュフローを確保し、持続的な企業成長を目指していくことが重要です。
4. 経営再建のためのキャッシュフロー改善ステップ
経営再建において、キャッシュフローの改善は不可欠です。計画的かつ段階的なアプローチによって、持続可能なキャッシュフローを生み出す基盤を構築しましょう。以下に、4つのステップで構成されるキャッシュフロー改善プロセスを解説します。
4.1 ステップ1:現状分析(キャッシュフロー計算書の作成と分析)
キャッシュフロー改善の第一歩は、現状を正確に把握することです。キャッシュフロー計算書を作成し、資金の流れを詳細に分析することで、問題点と改善の糸口が見えてきます。
4.1.1 キャッシュフロー計算書を作成するキャッシュフロー計算書は、一定期間における企業の現金および現金同等物の増減を示す財務諸表です。作成にあたっては、損益計算書と貸借対照表の情報も必要となります。会計ソフトやExcelテンプレートなどを活用して作成しましょう。勘定科目などを理解し、正確な数値を入力することが重要です。公認会計士や税理士に相談することも有効な手段です。
4.1.2 キャッシュフローの現状を把握する作成したキャッシュフロー計算書に基づき、営業活動、投資活動、財務活動それぞれのキャッシュフローを分析します。どの活動からキャッシュが流入・流出しているのか、その規模や傾向を把握することで、キャッシュフローの問題点を特定できます。例えば、営業活動によるキャッシュフローがマイナスになっている場合、本業で利益を上げていても、資金回収が滞っている、過剰な在庫を抱えているなどの問題が潜んでいる可能性があります。
4.2 ステップ2:キャッシュフロー改善計画の策定
現状分析の結果を踏まえ、具体的なキャッシュフロー改善計画を策定します。短期的な対策と中長期的な対策をバランスよく組み合わせることが重要です。
4.2.1 短期的なキャッシュフロー改善策短期的なキャッシュフロー改善策は、即効性のある対策が中心となります。以下に具体的な例を挙げます。
| 売掛金早期回収 | 顧客への督促を強化する、割引制度を導入するなどして、売掛金の回収期間を短縮します。 |
|---|---|
| 在庫削減 | 過剰在庫を処分する、仕入れ量を調整するなどして、在庫を適正な水準に抑えます。ジャストインタイム方式の導入も有効です。 |
| 支払サイトの延長 | 仕入先との交渉により、支払サイトを延長することで、一時的に支出を抑えることができます。ただし、仕入先との良好な関係を維持することが重要です。 |
| ファクタリングの活用 | 売掛債権をファクタリング会社に売却することで、早期に資金を調達できます。ただし、手数料が発生するため、コストを考慮する必要があります。 |
中長期的なキャッシュフロー改善策は、事業構造の改革など、根本的な改善を目指す対策です。以下に具体的な例を挙げます。
| 収益性の向上 | 売上高の増加、コスト削減などにより、利益率を高めます。新規事業の開拓、既存事業の効率化などが考えられます。 |
|---|---|
| 事業ポートフォリオの見直し | 収益性の低い事業からの撤退、成長が見込める事業への投資など、事業ポートフォリオを見直すことで、安定的なキャッシュフローを確保します。 |
| キャッシュフロー経営の導入 | キャッシュフロー計算書を定期的に作成・分析し、キャッシュフローを重視した経営を実践します。KPIを設定し、進捗状況を管理することも重要です。 |
4.3 ステップ3:キャッシュフロー改善策の実行
策定した計画に基づき、具体的なキャッシュフロー改善策を実行に移します。実行にあたっては、各部門の協力を得ることが不可欠です。また、計画通りに進捗しているか、定期的にモニタリングを行うことも重要です。
4.3.1 売掛金回収期間の短縮売掛金回収期間の短縮のためには、請求書の発行を迅速に行う、支払期限を明確にする、督促業務を効率化するなどの対策が有効です。また、顧客との良好な関係を構築し、支払いをスムーズに行ってもらえるような信頼関係を築くことも重要です。
4.3.2 在庫回転率の向上在庫回転率の向上には、需要予測の精度向上、過剰在庫の削減、適正在庫の維持などが重要です。また、在庫管理システムを導入し、在庫状況をリアルタイムで把握することも有効です。
4.3.3 不要資産の売却遊休資産や不要な設備などを売却することで、キャッシュフローを改善できます。売却益は、負債の返済や新規投資に充てることができます。
4.3.4 経費削減固定費、変動費の両面から経費削減に取り組みます。無駄な支出を見直し、コスト意識を高めることが重要です。例えば、光熱費の削減、通信費の見直し、オフィスの賃料交渉などが挙げられます。
【関連】経営再建のための資金調達【最新事例と活用できる制度】4.4 ステップ4:モニタリングと改善策の見直し
キャッシュフロー改善策を実行した後、定期的にモニタリングを行い、効果を検証します。計画通りに進んでいない場合は、原因を分析し、改善策を見直す必要があります。キャッシュフロー改善は継続的なプロセスであり、状況に応じて柔軟に対応していくことが重要です。
4.4.1 定期的なモニタリングの実施キャッシュフロー計算書を定期的に作成し、キャッシュフローの推移をモニタリングします。目標値を設定し、実績との差異を分析することで、問題点を早期に発見できます。モニタリングの頻度は、企業の状況に応じて適切に設定する必要があります。
4.4.2 状況に応じた改善策の見直し市場環境の変化や社内状況の変化などに応じて、キャッシュフロー改善策を見直す必要があります。当初の計画が有効でなくなっている場合は、新たな対策を検討し、実行に移すことが重要です。PDCAサイクルを回し、継続的に改善していくことが、キャッシュフロー改善の成功につながります。
5. キャッシュフロー改善の成功事例
キャッシュフロー改善の成功事例を2つ紹介します。業種や規模は違えど、キャッシュフロー経営の重要性を理解し、具体的な対策を実行することで、経営の安定化を図っています。
5.1 事例1:在庫管理の改善でキャッシュフローを改善したA社(中小アパレルメーカー)
A社は、トレンドに敏感な若者向けアパレルを製造販売する中小企業です。しかし、流行の移り変わりが早く、過剰在庫を抱えることが常態化し、キャッシュフローを圧迫していました。そこで、A社は在庫管理システムを導入し、以下の改善策を実施しました。
5.1.1 A社の取り組み| 需要予測の精度向上 | 過去の販売データやトレンド分析に基づき、需要予測の精度を向上させました。POSデータと連携させ、リアルタイムな販売状況を把握することで、過剰な仕入れを抑制しました。 |
|---|---|
| 適正在庫の維持 | 在庫管理システムを活用し、適正在庫を算出し、それを維持するようにしました。また、ABC分析を用いて、在庫を重要度別に分類し、重点的に管理すべき商品を明確化しました。 |
| リードタイムの短縮 | サプライヤーとの連携を強化し、生産リードタイムを短縮することで、必要な時に必要な量だけ仕入れる体制を構築しました。 |
| アウトレット販売の実施 | 型落ち商品や過剰在庫は、アウトレット販売やオンラインセールで積極的に販売することで、在庫の圧縮とキャッシュの回収を図りました。 |
これらの取り組みの結果、A社は在庫回転率を従来の4回転から6回転に改善し、在庫金額を30%削減することに成功しました。これにより、キャッシュフローが大幅に改善され、新たな商品開発への投資余力を確保することができました。また、在庫管理システム導入による業務効率化も実現し、人的リソースの最適化にも繋がりました。
5.2 事例2:売掛金回収の効率化でキャッシュフローを改善したB社(中堅ソフトウェア開発会社)
B社は、企業向けソフトウェア開発を手がける中堅企業です。開発期間が長期にわたるプロジェクトが多く、売掛金の回収が遅れがちで、キャッシュフローが悪化していました。そこで、B社は以下の改善策を実施しました。
5.2.1 B社の取り組み| 請求書の発行タイミングの見直し | プロジェクトの進捗状況に合わせて、分割請求を導入し、請求書の発行タイミングを早めました。また、電子請求システムを導入することで、郵送にかかる時間とコストを削減しました。 |
|---|---|
| 支払条件の明確化 | 契約締結時に、支払条件を明確に定め、顧客との認識の齟齬を防ぎました。また、早期支払いに対する割引制度を導入することで、顧客のインセンティブを高めました。 |
| 回収状況の定期的なモニタリング | 売掛金回収状況を定期的にモニタリングし、滞留している売掛金に対しては、積極的に督促を行いました。顧客との良好な関係を維持しつつ、粘り強く交渉することで、回収率の向上に努めました。 |
| ファクタリングの活用 | 一時的な資金繰りの悪化に対応するため、ファクタリングを活用し、売掛金を早期に現金化しました。ファクタリング手数料は発生するものの、資金繰りの安定化に大きく貢献しました。 |
これらの取り組みの結果、B社は売掛金回収期間を従来の90日から60日に短縮することに成功しました。これにより、キャッシュフローが安定し、新たなプロジェクトへの投資や人材採用を積極的に行えるようになりました。また、資金繰りの不安が解消されたことで、経営の意思決定スピードも向上しました。
これらの事例は、キャッシュフロー改善には、自社の状況に合わせた適切な対策の実行が重要であることを示しています。キャッシュフロー計算書を定期的に作成・分析し、問題点を早期に発見し、改善策を迅速に実行することで、健全な経営を実現できるでしょう。
【関連】経営再建コンサルタントの選び方|実績豊富な専門家が徹底解説!6. まとめ
経営再建において、キャッシュフローの改善は不可欠です。本記事では、キャッシュフロー悪化の兆候の発見から、キャッシュフロー計算書の見方、そして具体的な改善ステップまでを解説しました。キャッシュフローが悪化する兆候としては、売上高は好調なのに資金繰りが苦しい、売掛金回収の長期化、在庫の増加、設備投資の過剰などが挙げられます。これらの兆候を見逃さず、早期に対策を講じることが重要です。
キャッシュフロー改善のステップは、現状分析、改善計画の策定、改善策の実行、モニタリングと改善策の見直しという4つの段階に分けられます。現状分析では、キャッシュフロー計算書を作成し、現状を正確に把握することが重要です。改善計画策定では、短期的な対策と中長期的な対策をバランスよく組み合わせることが重要です。そして、計画を実行に移し、定期的なモニタリングと見直しを行うことで、キャッシュフローの改善を継続的に行うことができます。
本記事で紹介したA社やB社の成功事例のように、在庫管理の改善や売掛金回収の効率化など、自社に合った具体的な対策を実行することで、キャッシュフローは改善可能です。キャッシュフロー計算書を活用し、計画的に改善に取り組むことで、企業の経営再建を成功に導きましょう。


