M&Aにおけるアーンアウトとは?アーンアウト条項のメリット・デメリット、会計処理、留意点まで
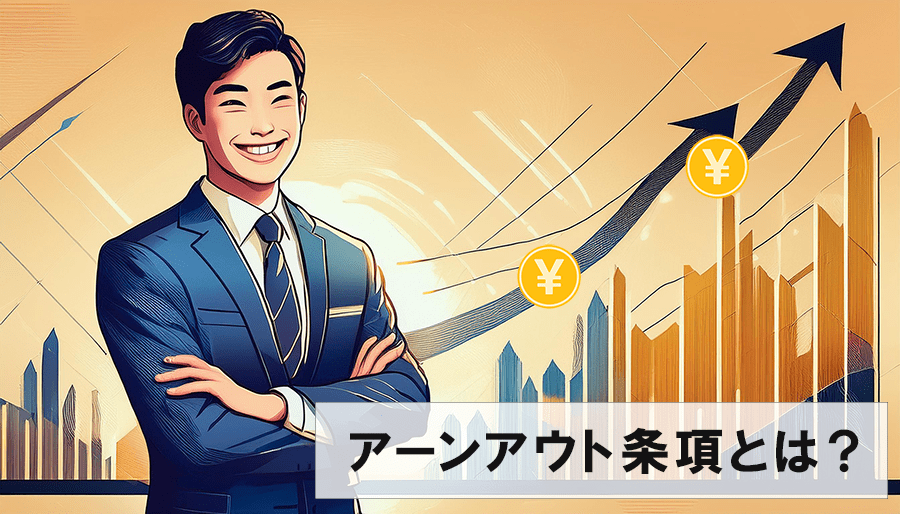
本記事では、アーンアウト導入を検討している経営者や、M&A担当者の方に向けて、アーンアウトの基礎知識からメリット・デメリット、会計処理、注意点までを分かりやすく解説していきます。
この記事を読めば、アーンアウトに関する理解を深め、M&A戦略に活かせるようになります。
M&A PMI AGENTは上場企業・中堅・中小企業の「M&AからPMI支援までトータルサポート」できるM&A仲介会社です。詳しくはコンサルタントまでお気軽にご相談ください。
M&A・PMI支援のご相談はこちら

- 具体的には、買収契約締結時に基本的な買収価格を定め、その後、一定期間内の売上高や利益などの目標達成状況に応じて、追加的な報酬を売却側に支払うという仕組みです。
1.2 アーンアウト導入の背景 アーンアウト条項が導入される背景には、主に以下のような事情があります。
企業価値評価の不確実性 M&Aでは、対象会社の将来業績や潜在リスクを完全に評価することは困難です。特に、スタートアップ企業や成長途上の企業では、将来予測が難しく、買収価格の合意形成が困難になる場合があります。
アーンアウト条項は、このような企業価値評価の不確実性を緩和し、買収交渉をスムーズに進めるために有効な手段となります。
買収後の経営統合リスク M&A後の経営統合がスムーズに進まず、想定したシナジー効果が得られないケースも少なくありません。
アーンアウト条項は、売却側の経営陣や従業員に対して、買収後も従通りの経営努力を継続するインセンティブを与え、円滑な経営統合を促進する効果も期待できます。
買収資金の調達 買収資金が不足している場合、アーンアウト条項を設けることで、買収資金の支払いを将来に先送りすることができます。
これにより、買収側企業は、多額の資金調達を行うことなく、M&Aを実行することが可能となります。
1.3 アーンアウトの対象指標 アーンアウト条項で設定される対象指標は、企業の業績や状況に応じて様々ですが、一般的には以下のような指標が用いられます。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| 売上高 | 一定期間内の売上高を指標とするもので、最も一般的な指標の一つです。 |
| 営業利益 | 本業からの収益力を示す指標であり、売上高と並んで多く用いられます。 |
| 経常利益 | 営業利益に財務活動による収益を加味した指標で、企業の安定的な収益力を示します。 |
| 純利益 | 企業の最終的な利益を示す指標であり、企業の総合的な収益力を評価する際に用いられます。 |
| EBITDA | 金利、税金、減価償却費の影響を除いた利益であり、企業の事業活動によるキャッシュフロー創出力を見る指標として用いられます。 |
| 新規顧客獲得数 | 将来の収益基盤拡大を評価する指標として、特に成長企業の買収において用いられます。 |
| 製品開発の進捗状況 | 技術開発や製品開発の進捗状況を指標とするもので、特に技術系スタートアップ企業の買収において用いられます。 |
重要なのは、対象指標が買収の目的や対象会社の事業内容と整合性の取れたものであることです。
例えば 経済産業省が公開している「中小企業のM&A活用に関するガイドライン」では、アーンアウト条項を検討する際の注意点として、対象指標は、売主のモラルハザードを防ぐ観点から、売主がコントロール可能なものとするのが適切であるとされています。
2. アーンアウトのメリット 2.1 買収側にとってのメリット 買収価格の抑制 買収時点における対象会社の業績のみを基準に買収価格を決定する場合、将来の業績の伸びや不確実性などを考慮する必要があり、買収価格が高額になる傾向があります。
アーンアウト条項を導入することで、将来の業績達成を条件とした支払いにすることで、買収時点における買収価格を抑制することができます。
経営者のモチベーション維持 従来のM&Aでは、買収後に経営者が退任したり、モチベーションが低下してしまうケースが見受けられました。
アーンアウト条項を導入することで、経営者は買収後も一定期間、経営に携わることができ、業績達成に応じて追加報酬を得られるため、モチベーションを維持することができます。
また、買収後の経営体制をスムーズに移行するため、買収側の企業文化やノウハウを吸収する期間を設けることも可能です。
2.2 売却側にとってのメリット 企業価値の向上 売却時点では企業価値が十分に評価されず、適正な価格で売却できない場合があります。アーンアウト条項を導入することで、将来の業績に応じて追加報酬を得られるため、将来的に企業価値が向上する可能性があります。
例えば ベンチャー企業など、将来の成長性が見込まれるものの、現時点での収益が低い企業にとって、アーンアウト条項は有効な手段となりえます。
事業継続の保証 売却後も事業を継続したいと考える経営者もいるでしょう。アーンアウト条項を導入することで、買収後も一定期間、経営に携わることができ、事業の継続性を担保することができます。
特に、オーナー企業のように、経営者と事業が密接に関係している場合、事業継続性を重視する傾向があります。

- アーンアウトは、経営者にとっては事業への想いを持ち続けながら、事業承継を進める手段となりえます。アーンアウト条項は、買収側・売却側の双方にとってメリットがある一方、それぞれにデメリットも存在します。
3. アーンアウトのデメリット 3.1 買収側にとってのデメリット
追加的な支払リスク
アーンアウト条項を導入した場合、買収側にとっては、事業目標の達成状況に応じて追加的な支払いが発生するリスクがあります。
買収時に想定していたよりも業績が上振れた場合、買収価格が当初の見積もりを上回ってしまう可能性があります。
業績管理の複雑化
アーンアウト条項を導入すると、買収後の事業統合後も、一定期間にわたって売却側の業績に基づいて支払額を算定する必要が生じます。
そのため、業績目標の設定やモニタリングなど、買収後の統合プロセスが複雑化する可能性があります。また、業績目標の達成状況によっては、買収側と売却側の間に意見の相違が生じ、紛争に発展するリスクもあります。
財務予測の不確実性
アーンアウトによる支払額は将来の業績に依存するため、買収後の財務予測が困難になります。この不確実性は、買収後の資金調達や投資計画に影響を与える可能性があります。
3.2 売却側にとってのデメリット 経営の自由度制限 アーンアウト条項を導入した場合、売却側は、買収後も一定期間、業績目標の達成に向けて経営を行う必要があり、経営の自由度が制限される可能性があります。
例えば 新たな事業への投資や、従業員の待遇改善などが制限される場合があります。
将来の報酬不確実性 アーンアウトによる報酬は、将来の業績目標の達成状況によって変動するため、売却側にとっては将来の報酬が不確実になります。
事業統合の難航 買収側が業績目標達成を重視するあまり、売却側の企業文化や従業員のモチベーションを軽視してしまうと、事業統合がスムーズに進まない可能性があります。
| 項目 | 買収側のデメリット | 売却側のデメリット |
|---|---|---|
| 財務 |
|
|
| 経営 |
|
|
また、契約書の内容を明確化し、将来的なトラブルを回避するための対策を講じておく必要があります。
4. アーンアウト条項の設計

- アーンアウト条項を設計する際には、将来発生しうる紛争を防ぎ、双方にとって納得感のある合意を形成するために、以下の3つの要素について明確に定めることが重要です。
4.1 アーンアウトの対象期間 アーンアウトの対象期間は、買収後の事業計画や統合プロセスを考慮して決定されます。一般的には買収完了後3年から5年程度が目安となりますが、事業の特性や成長ステージによって柔軟に設定されます。
短期間の場合1年~3年程度 短期的な業績目標を達成した場合にアーンアウトが支払われるように設計する
長期間の場合5年~10年程度 長期的な成長やシナジー効果を評価し、アーンアウトの支払いに反映させる
対象期間が長すぎる場合は、売却側にとって将来の報酬が不確実になるというデメリットがあります。一方、短すぎる場合は、買収側にとって追加的な支払リスクが低減されるというメリットがあります。
これらのメリットとデメリットを踏まえ、事業計画や業界の状況などを考慮して、双方にとって適切な期間を設定することが重要です。
4.2 アーンアウトの発動条件 アーンアウトの発動条件は、客観的で測定可能な指標に基づいて設定する必要があります。一般的な指標としては、売上高、利益、EBITDA、ROE、ROAなどが用いられますが、業界や事業の特性に応じて適切な指標を選択することが重要です。
| 売上高を指標とする場合 | |
| 売上目標の達成率に応じてアーンアウトの支払額が変動 | |
| 新たな顧客獲得数や既存顧客との取引額なども指標に含める | |
| 利益を指標とする場合 | |
| 一定の利益水準を達成した場合にアーンアウトを支払う | |
| 利益率や売上高利益率を指標に設定 |
例えば 一定水準以上の顧客満足度を維持することをアーンアウトの支払条件に含めることで、顧客重視の経営を継続することを促す効果が期待できます。
アーンアウトの発動条件の具体例 具体的なアーンアウトの発動条件の設計例として、売上高を指標とした場合の例を以下に示します。
| 売上目標達成率 | アーンアウト支払い率 |
|---|---|
| 120%以上 | 150% |
| 110%以上120%未満 | 120% |
| 100%以上110%未満 | 100% |
| 90%以上100%未満 | 80% |
| 90%未満 | 0% |
このように、アーンアウトの発動条件を具体的に設定することで、将来発生しうる紛争を予防し、双方にとって納得感のある取引を実現することができます。
4.3 アーンアウトの算定方法 アーンアウトの算定方法は、対象となる指標の達成度合いをどのように金額に反映させるかを明確に定める必要があります。
例えば 売上高を指標とする場合、売上高の一定割合をアーンアウトとして支払う方法や、目標売上高を達成した場合に固定額を支払う方法などがあります。また、複数の指標を組み合わせた算定方法を採用することも可能です。
| 売上高を指標とする場合 | • 売上高の一定割合をアーンアウトとして支払う • 目標売上高を達成した場合に固定額を支払う |
|---|---|
| 利益を指標とする場合 | • 純利益または営業利益を基準に算定 • 利益達成度に応じて段階的にアーンアウトを増額 |
また、算定根拠となるデータの提供方法や時期についても、事前に取り決めておく必要があります。
例えば 毎月の売上高データを提供する場合には、その提出期限や方法を明確にしておくことが重要です。
これらの条項を明確に定めることで、アーンアウト条項に関するトラブルを未然に防ぎ、M&A後の円滑な事業統合を実現することができます。
アーンアウト条項は、M&A取引において非常に重要な要素であるため、専門家のアドバイスを受けながら、双方にとって納得感のある合意を形成することが重要です。
5. アーンアウトの会計処理

- アーンアウトの会計処理は、買収側と売却側で大きく異なります。複雑な処理が必要となる場合もあるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
5.1 買収側の会計処理 買収側では、アーンアウト条項に基づく支払いを負債として計上します。
負債の認識 買収日に、将来支払う可能性のあるアーンアウト対価を負債として認識します。この負債は、公正価値で測定します。公正価値の算定には、将来の業績予測や割引率などを考慮する必要があるため、専門家のサポートが必要となるケースが一般的です。
負債の測定 買収後の決算期ごとに、負債の再測定を行います。再測定の結果、負債が増加する場合には、対応する費用を計上します。逆に、負債が減少する場合には、対応する収益を計上します。
支払時の処理 実際にアーンアウト対価を支払う際には、負債を減少させるとともに、現金の減少を計上します。
5.2 売却側の会計処理 売却側では、アーンアウト条項に基づく支払いを受け取る権利を資産として計上します。
| 資産の認識 | 売却日に、将来受け取る可能性のあるアーンアウト対価を資産として認識します。この資産は、公正価値で測定します。 |
|---|---|
| 資産の測定 | 売却後の決算期ごとに、資産の再測定を行います。再測定の結果、資産が増加する場合には、対応する収益を計上します。逆に、資産が減少する場合には、対応する費用を計上します。 |
| 受取時の処理 | 実際にアーンアウト対価を受け取る際には、資産を減少させるとともに、現金の増加を計上します。 |
5.3 アーンアウト会計処理の例
| 買収後の期間 | 対象指標の達成度 | アーンアウト金額 | 買収側の会計処理 | 売却側の会計処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 80% | 80百万円 | 負債を100百万円から80百万円に減額し、20百万円の収益を計上 | 資産を100百万円から80百万円に減額し、20百万円の費用を計上 |
| 2年目 | 100% | 100百万円 | 負債の残りの80百万円を減額し、80百万円の収益を計上 | 資産の残りの80百万円を減額し、80百万円の収益を計上 |
6. アーンアウト導入の際の注意点

- アーンアウト条項は、M&A取引において、買収後の企業価値向上を促進するための有効な仕組みとなりえます。
6.1 専門家への相談 アーンアウト条項は、その内容が複雑であり、会計処理や税務上の影響も考慮する必要があるため、弁護士や会計士などの専門家に相談することが不可欠です。
専門家は、アーンアウト条項に関する法的知識や実務経験に基づき、最適な条項内容や注意点についてアドバイスを提供してくれます。
また、契約書の作成や交渉のサポートも行ってくれるため、専門家のサポートを受けることで、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能となります。
6.2 契約書の綿密な確認 アーンアウト条項に関するトラブルを避けるためには、契約書の綿密な確認が重要となります。特に以下の項目については、注意深く確認する必要があります。
アーンアウトの対象期間
期間の設定が曖昧だと、後に期間延長を求められる可能性があります。明確な開始日と終了日を定めましょう。
6.2.2 アーンアウトの発動条件
どのような業績目標を達成すればアーンアウトが支払われるのか、具体的な数値目標や達成基準を明確に定めることが重要です。あいまいな表現は避け、将来の解釈違いを防ぎましょう。
アーンアウトの算定方法
算定方法が複雑すぎると、後に計算ミスや解釈の違いが生じる可能性があります。明確で理解しやすい算定式を用いるようにしましょう。また、算定の根拠となるデータの提供方法や時期についても明確に定めておく必要があります。
業績悪化時の対応
買収後に予想外の業績悪化が生じた場合の対応策も検討しておくべきです。例えば、一定期間業績目標が未達の場合にアーンアウト条項を無効とする条項などを盛り込むことができます。ただし、この場合、売却側にとって不利な条件となる可能性もあるため、双方が納得できる内容にすることが重要です。
例えば 市場環境の激変や競合の出現などにより、当初想定していた業績を達成することが困難になる場合も考えられます。このような事態に備え、以下のような対策を検討しておくことが重要です。
見直し条項の導入 一定期間経過後、または特定のイベント発生時に、アーンアウト条項の内容を見直すことができる条項を設けておくことで、将来的な環境変化に柔軟に対応することができます。例えば、3年後に市場環境や業績状況を踏まえて、アーンアウトの算定方法や支払額を見直すことができるといった条項です。
紛争解決手続きの明確化 アーンアウト条項に関する紛争が発生した場合の解決手続きをあらかじめ定めておくことが重要です。具体的には、裁判外紛争解決手続き(ADR)や仲裁など、訴訟によらない紛争解決方法を検討します。これらの手続きを定めておくことで、紛争が長期化した場合のリスクを軽減することができます。
情報開示とコミュニケーション アーンアウト期間中は、買収側と売却側との間で、業績に関する情報開示やコミュニケーションを密に行うことが重要です。例えば、定期的な業績報告会を開催したり、重要な経営判断を行う際には事前に協議したりするなど、相互の信頼関係を構築するための努力が不可欠です。
6.4 裁判例も参考に アーンアウト条項に関する紛争は、実際に裁判で争われるケースも少なくありません。過去の裁判例を参考に、どのような点が争点となりやすいか、どのような判決が出ているのかを把握しておくことは、より安全なアーンアウト条項を設計する上で役立ちます。
例えば 「アーンアウト条項に基づく請求権の範囲」に関する最高裁判決など、企業買収におけるアーンアウト条項の解釈や適用に関する重要な判例が出ています。
アーンアウト条項は、M&A取引において、買収後の企業価値向上をの有効な手段でもありますが、その一方で合意形成が複雑になりやすく、将来的なトラブルに発展する可能性も孕んでいます。
そのため、アーンアウト条項を導入する際には、弁護士や会計士などの専門家に相談し、契約書の内容を綿密に確認することが不可欠です。また、将来発生しうる問題への対策を講じておくことも重要です。
7. まとめ M&Aにおけるアーンアウト条項は、買収後の企業業績によって買収価格が変動する仕組みです。買収側にとっては買収価格のリスクを抑え、売却側にとってはより高い売却価格を実現できる可能性があります。
しかし、アーンアウト条項は、将来の業績に基づいて支払いが決定されるため、買収側、売却側双方に複雑な会計処理や将来的なリスクをもたらす可能性も孕んでいます。
アーンアウト条項を導入する際には、弁護士や会計士などの専門家のアドバイスを受け、契約書の内容を慎重に検討することが重要です。
また、将来発生する可能性のある問題を予測し、未然に防ぐための対策を講じておくことも重要となります。
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったPMIのエキスパート。3か月のPMIにて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。


