意向表明書(LOI)と基本合意契約書(MOU)の違いをわかりやすく解説!重要条項・確認ポイントも
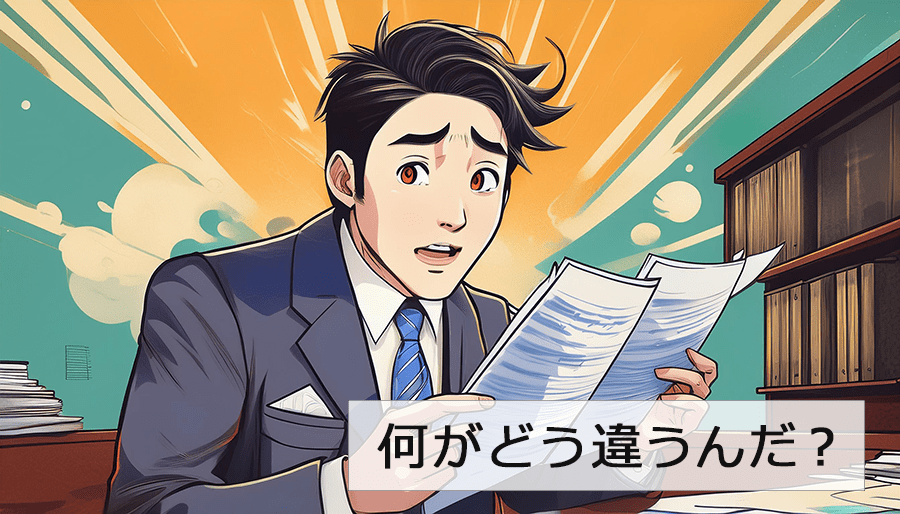
「事業提携の話が持ち上がったけど、まずは意向表明書と基本合意契約書ってどっちを作成すればいいの?」「そもそもこの2つの違いってなんだろう?」と疑問に思っていませんか?
意向表明書(LOI)と基本合意契約書(MOU)は、どちらもビジネスの初期段階で締結されることが多い文書ですが、法的拘束力の有無や記載内容などが異なります。もし、それぞれの違いを正しく理解しないまま作成してしまうと、後々、思わぬトラブルに発展する可能性も。

- この記事では、意向表明書と基本合意契約書の違いを、法的拘束力の有無、作成目的、記載内容の詳細度といった観点からわかりやすく解説していきます。また、それぞれのメリットや重要条項、作成時の確認ポイントなどもまとめました。
M&A PMI AGENTは上場企業・中堅・中小企業の「M&AからPMI支援までトータルサポート」できるM&A仲介会社です。詳しくはコンサルタントまでお気軽にご相談ください。
M&A・PMI支援のご相談はこちら

- 意向表明書(LOI: Letter of Intent)とは、日本語では「基本合意書」「覚書」「了解覚書」などと呼ばれることもあります。 当事者間で、将来、契約を締結する意思があることを書面にしたものです。
法的拘束力については後に説明しますが、法的拘束力を有さない合意書として作成される場合もあれば、法的拘束力を有する合意書として作成される場合もあります。
M&Aや業務提携や不動産取引など、企業活動において重要な契約を締結する際に、事前に当事者間の合意内容を明確化し、円滑な交渉を進めるために作成されます。
また、本格的な契約交渉に入る前に、お互いの基本的な意向を確認し、合意形成を図ることを目的とします。
1.2 意向表明書(LOI)の法的拘束力
意向表明書(LOI)の法的拘束力については、法的拘束力を有さない合意書として作成される場合と法的拘束力を有する合意書として作成される場合の2種類があります。法的拘束力の有無は、当事者間の合意によって決定されます。
法的拘束力を有さない意向表明書(LOI)法的拘束力を有さない意向表明書(LOI)は、あくまでも当事者間の交渉の出発点となるものであり、法的拘束力は発生しません。
そのため、当事者は、意向表明書(LOI)の内容に拘束されることなく、自由に交渉を進めることができます。また、意向表明書(LOI)の内容に反して契約を締結しない場合でも、原則として責任を負うことはありません。
ただし、信義則上または信義誠実の原則上、正当な理由なく一方的に交渉を打ち切った場合に、相手方に損害が発生した場合には、損害賠償責任を負う可能性があります。
法的拘束力を有する意向表明書(LOI)とは、当事者間で法的拘束力を発生させることを合意した上で作成されます。
そのため、当事者は、意向表明書(LOI)の内容に従って契約交渉を進める義務を負います。また、意向表明書(LOI)の内容に反して契約を締結しない場合には、相手方に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
意向表明書(LOI)に法的拘束力を発生させるか否かは、当事者間の交渉力や取引の性質・取引の進捗状況などを考慮して決定されます。
| 項目 | 法的拘束力を有さない意向表明書(LOI) | 法的拘束力を有する意向表明書(LOI) |
|---|---|---|
| 定義 | 法的拘束力が発生しないことを前提として作成される文書。 | 法的拘束力が発生することを前提として作成される文書。 |
| 目的 | 主に、交渉の初期段階において、当事者間の認識のすり合わせや、交渉の円滑化を図ることを目的とする。 | 法的拘束力を有さない意向表明書(LOI)と同様の目的のほか、将来の契約締結に向けた法的義務を発生させることを目的とする。 |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
| その他 |
|
|
法的拘束力を有さない意向表明書(LOI)を作成する場合でも、後々のトラブルを避けるためには、法的拘束力の有無について明確に記載しておくことが重要です。法的拘束力については、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
2. 基本合意契約書(MOU)とは? 2.1 基本合意契約書(MOU)の定義と目的

- 基本合意契約書(Memorandum of Understanding, MOU)とは、日本語で「覚書」とも呼ばれ、ビジネスや国際的な協定など幅広い分野において、後に締結する正式な契約に先立ち、当事者間の合意内容を大枠で定める文書です。
MOUは、法的拘束力を持つ契約書と混同されがちですが、法的拘束力の有無や、記載する内容の詳細度合いが異なります。
MOUの主な目的は、以下の点が挙げられます。
| 1 | 当事者間の合意内容を明確化し、共通認識を持つこと |
|---|---|
| 2 | 今後の交渉や事業計画の基礎とすること |
| 3 | 正式な契約締結に向けた相互理解と信頼関係を構築すること |
MOUは、法的拘束力を持たない場合でも当事者間の信頼関係に基づいて作成され、双方がその内容を尊重することが前提となります。
そのため、MOUの内容に違反した場合、道義的な責任やビジネス上の信頼関係を失う可能性も考えられます。
2.2 基本合意契約書(MOU)の法的拘束力
MOUは、原則として法的拘束力を持たないとされています。しかし、MOUの記載内容によっては、法的拘束力が認められる場合があります。
特に、契約が有効で法的拘束力を持つための最小限の契約内容(契約の主要な条項)が含まれている場合や、MOU自体が準契約と解釈される場合には、法的拘束力が認められる可能性があります。
そのため、MOUを作成する際には、法的拘束力の有無について、専門家に相談することをおすすめします。
MOUに法的拘束力を持たせるためには、以下のような点を明確に記載する必要があります。
| 1 | 当事者双方の権利義務 |
|---|---|
| 2 | 違反した場合の責任 |
| 3 | 準拠法や裁判管轄 |
また、MOUに「本MOUは法的拘束力を有しない」といった文言を記載することで、法的拘束力を明確に排除することも可能です。法的拘束力の有無は、MOUの内容や解釈、当事者の意図によって判断されるため、注意が必要です。
MOUは、法的拘束力の有無にかかわらず、当事者間の合意内容を明確化し、円滑な交渉を促進するために重要な役割を果たします。そのため、MOUを作成する際には、目的や内容を十分に検討し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
3. 意向表明書(LOI)と基本合意契約書(MOU)の違い 意向表明書(LOI)と基本合意契約書(MOU)の主な違いは以下の3点が挙げられます。
3.1 法的拘束力の有無
| 意向表明書(LOI) | 基本合意契約書(MOU) | |
|---|---|---|
| 法的拘束力 | 原則として法的拘束力なし | 合意内容によっては法的拘束力が生じる場合あり |
基本合意契約書(MOU)は 基本合意契約書(MOU)は、法的拘束力を伴う合意文書と解釈される可能性があります。特に、契約の主要な条項(例えば、契約の目的、契約期間、契約金額など)が具体的に定められている場合には、法的拘束力が認められる可能性が高くなります。
3.2 作成の目的
| 意向表明書(LOI) | 基本合意契約書(MOU) | |
|---|---|---|
| 作成目的 |
|
|
基本合意契約書(MOU)は 法的拘束力のある合意を形成し、詳細な契約条件を定める前の枠組みを構築することを目的として作成されます。
3.3 記載内容の詳細度
| 意向表明書(LOI) | 基本合意契約書(MOU) | |
|---|---|---|
| 記載内容の詳細度 | 概要レベル | 具体的かつ詳細な記載 |
基本合意契約書(MOU)は 契約の目的、契約期間、契約金額、当事者の権利義務など、具体的な内容を詳細に記載する必要があります。法的拘束力を伴う合意文書であるため、後々の紛争を避けるためにも、可能な限り詳細に記載することが重要です。
4. 意向表明書(LOI)・基本合意契約書(MOU)を作成するメリット

- 意向表明書(LOI)や基本合意契約書(MOU)を作成することには、多くのメリットがあります。ここでは、主なメリットとして下記の3つを解説します。
4.1 当事者間の認識のすり合わせ
LOIやMOUを作成する最大のメリットは、契約締結に向けて当事者間で認識をすり合わせることができる点にあります。ビジネスを進める上で、当事者間で認識のずれがあると、後々大きなトラブルに発展しかねません。 LOIやMOUを作成することで、契約の重要なポイントについて事前に合意しておくことができ、認識のずれを防ぐことができます。また、認識のずれを早期に発見し修正することで、時間やコストの無駄を省くことにも繋がります。
4.2 円滑な交渉の促進LOIやMOUは、基本的な事項について合意しておくことで、その後の本格的な契約交渉を円滑に進める効果も期待できます。
特に、複雑な取引や多額の費用が伴う取引においては、事前にLOIやMOUを締結しておくことで、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
また、LOIやMOUで合意した内容を基に、詳細な契約書を作成することができるため、契約締結までの時間短縮にも繋がります。
4.3 後々のトラブル防止
LOIやMOUは、後々のトラブルを防止する役割も果たします。契約内容について書面で明確にしておくことで、言った言わないを防ぐことができます。
また、万が一、訴訟に発展した場合でも、証拠として役に立つ可能性があります。特に、法的拘束力を持つMOUの場合、契約違反があった場合には損害賠償請求など、法的措置を講じることが可能になります。そのため、後々のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
このように、LOIやMOUは当事者間の認識のすり合わせ、円滑な交渉の促進し後々のトラブル防止といったメリットがあります。そのため、ビジネスを進める上では、LOIやMOUの活用を検討することが重要になります。
ただし、LOIやMOUは、法的拘束力の有無や記載内容など、注意すべき点も多いため、専門家のアドバイスを受けるなど、慎重に進めるようにしましょう。詳細については、以下の記事も参考にしてください。
5. 意向表明書(LOI)・基本合意契約書(MOU)の重要条項

- 意向表明書(LOI)と基本合意契約書(MOU)には、後にトラブルを避けるためにも、必ず記載すべき重要条項があります。ここでは、特に重要な条項を解説していきます。
5.1 基本事項
まずは、LOIやMOUを作成する上で前提となる基本事項を明確に記載する必要があります。具体的には、以下の項目が挙げられます。
| 当事者の氏名(名称)および住所 | |
| 締結日 | |
| 署名 |
これらの情報は、文書の効力発生日や当事者を明確にするために必要不可欠です。特に、会社間で締結する場合には、正式な会社名と代表者名を正確に記載する必要があります。
5.2 目的
LOIやMOUを作成する目的を明確に記載することは、当事者間の認識を一致させるために非常に重要です。例えば、「A社とB社は、B社の開発した新技術を用いた新製品の共同開発を目的として、本LOIを締結する」のように、具体的な内容を明記する必要があります。
目的を曖昧に記載してしまうと、後々の解釈の違いやトラブルに発展する可能性があります。そのため、両当事者が合意した内容を明確に記載することが重要です。
5.3 有効期間
LOIやMOUの有効期間を定めておくことは、期間満了後の法的拘束力を明確にする上で重要です。有効期間は、目的や内容に応じて適切に設定する必要があります。例えば、「本MOUの有効期間は、締結日から1年間とする」のように明記します。
有効期間が過ぎた後も交渉を継続する場合は、改めて期間を延長する旨を合意する必要があります。また、有効期間内に本契約を締結できなかった場合に備え、その旨を記載しておくことも重要です。
5.4 秘密保持
LOIやMOUの締結過程で、当事者間で開示される機密情報は少なくありません。これらの情報が外部に漏洩してしまうと、事業活動に大きな影響を与える可能性があります。そのため、秘密保持に関する条項は非常に重要です。
具体的には、「本LOI締結にあたり、相手方が開示した情報については、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に開示または漏洩してはならない」といった条項を設けることで、情報漏洩のリスクを抑制することができます。
秘密保持の対象となる情報や、秘密保持義務の範囲を明確に定義しておくことが重要です。
5.5 法的拘束力の有無
LOIやMOUは、法的拘束力を生じさせるか否かを当事者間で決定することができます。法的拘束力を発生させる場合は、「本MOUは、当事者間において法的拘束力を有するものとする」と明記します。
逆に、法的拘束力を発生させない場合は、「本LOIは、当事者間の誠実な交渉を目的とするものであり、法的拘束力を有するものではない」と明記します。
ただし、法的拘束力を発生させない場合でも、信義誠実の原則に則り、正当な理由なく合意内容に反する行動をとることはできません。法的拘束力の有無については、専門家の意見を参考にしながら慎重に判断する必要があります。
6. 意向表明書(LOI)・基本合意契約書(MOU)作成時の確認ポイント

- 意向表明書(LOI)と基本合意契約書(MOU)は、法的拘束力の有無や作成の目的が異なるため、それぞれの目的に応じた適切な文書を作成することが重要です。ここでは、意向表明書(LOI)と基本合意契約書(MOU)を作成する際の確認ポイントを解説します。
6.1 目的の明確化
意向表明書(LOI)や基本合意契約書(MOU)を作成する目的を明確にしましょう。契約交渉の初期段階における相互理解を深めるためのものか、それとも法的拘束力を持つ合意内容を定めるものなのか、目的に応じて文書の形式や記載内容が変わります。
意向表明書(LOI)の場合
- 将来的な契約締結の可能性を探る
- 基本的な合意内容を共有する
- 交渉の開始をスムーズに行う
基本合意契約書(MOU)の場合
- 法的拘束力のある合意を形成する
- 具体的なプロジェクトの推進を約束する
- 権利義務を明確にする
6.2 法的拘束力の範囲
意向表明書(LOI)は、一般的には法的拘束力を持ちませんが、一部の条項に法的拘束力を付与する場合があります。一方、基本合意契約書(MOU)は、原則として法的拘束力を持ちます。
法的拘束力の有無や範囲については、事前に専門家である弁護士に相談し、文書に明記することが重要です。
| 将来的な契約締結の義務 | |
| 具体的な金額や条件 |
| 秘密保持義務 | |
| 協議の誠実義務 | |
| 準拠法・裁判管轄 |
6.3 専門家の確認
意向表明書(LOI)や基本合意契約書(MOU)は、法的側面を持つ重要な文書です。作成にあたっては、法的リスクを回避するため、弁護士などの専門家に内容を確認してもらうことを強くおすすめします。専門家の確認を得ることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
| 項目 | 専門家に相談するメリット |
|---|---|
| 法的拘束力の有無 | 条項ごとに法的拘束力の有無を判断し、意図した内容で作成できる |
| 記載内容の妥当性 | 法律や判例に照らし合わせて、記載内容が適切かどうかを判断してもらえる |
| リスクヘッジ | 将来的な紛争リスクを予測し、未然に防ぐための対策を検討してもらえる |
専門家のアドバイスを受けることで、法的リスクを最小限に抑え、円滑なビジネス展開を実現できるでしょう。法的拘束力の有無や範囲、記載内容については、経済産業省などの公的機関のウェブサイトも参考にすることができます。
7. まとめ
今回は、意向表明書(LOI)と基本合意契約書(MOU)の違いについて解説しました。法的拘束力の有無や作成目的、記載内容の詳細度など、両者には明確な違いがあります。
ビジネスを進める上で、それぞれの文書の特性を理解し、適切に使い分けることが重要です。契約書作成は専門性の高い分野ですので、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
この記事が、皆様のビジネスにおける契約締結の一助となれば幸いです。
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったPMIのエキスパート。3か月のPMIにて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。


