経営再建・事業再生ADRで会社を守る!専門家が教える再生戦略と手続き
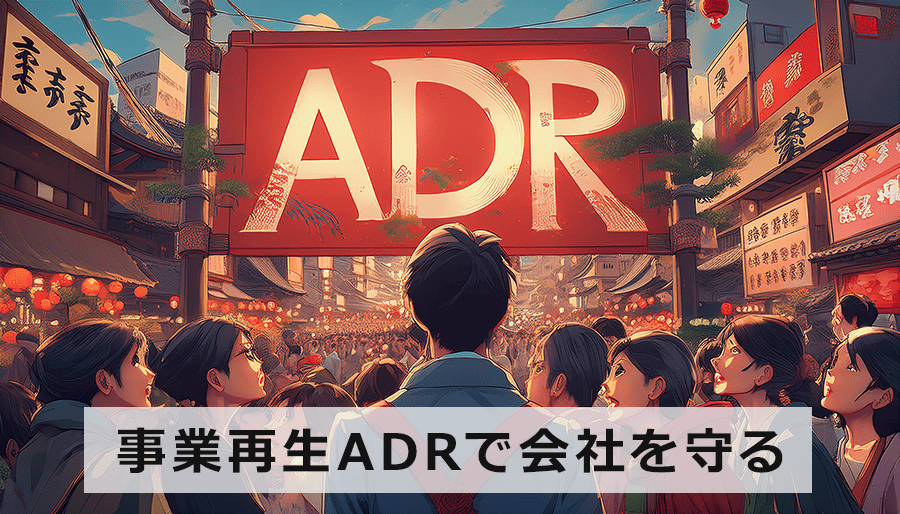
会社が経営難に陥った時、「経営再建」や「事業再生ADR」といった言葉を耳にするかもしれません。しかし、これらの言葉の違いや、具体的にどのような手続きが必要なのか、理解するのは難しいものです。本記事では、経営再建と事業再生の違いを分かりやすく解説し、事業再生ADRのメリット・デメリット、手続きの流れ、成功させるためのポイントなどを専門家の視点から詳しく解説します。
この記事を読むことで、経営再建・事業再生に関する全体像を掴み、自社に最適な再生方法を選択するための知識を得ることができます。さらに、よくある質問にもお答えすることで、抱えている疑問や不安を解消し、迅速かつ適切な対応に繋げられるようサポートします。早期の対応が企業の未来を左右すると言っても過言ではありません。本記事を通じて、経営危機を乗り越え、持続可能な成長を実現するための第一歩を踏み出しましょう。
「経営再建(赤字解消)してからM&Aしたい」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建などを10年経験。3か月の経営支援サポートで、9か月後には赤字の会社を1億円の利益を計上させるなどの実績を多数持つ専門家。
1. 経営再建と事業再生の違い
「経営再建」と「事業再生」はどちらも経営が悪化した企業を立て直すための取り組みですが、その意味合い、対象となる企業規模、手法には違いがあります。この章では、それぞれの違いを詳しく解説します。
1.1 再建と再生、それぞれの意味
「再建」は、企業の経営基盤そのものを立て直すことを指します。経営破綻の危機に瀕している企業が、抜本的な改革を行い、再び収益を上げられる状態にすることを目指します。一方、「再生」は、企業の事業を継続しながら、収益性を改善し、債務を圧縮することで、経営の健全化を図ることを指します。必ずしも経営破綻の危機に瀕している状態ではなく、業績が悪化し、将来的な経営破綻を避けるための取り組みとして行われることもあります。
「再建」は、より深刻な状況にある企業に対して行われる大規模な改革をイメージさせ、「再生」は、事業を継続しながら行う、比較的小規模な改善をイメージさせます。ただし、実際には明確な線引きはなく、両方の要素を含む場合もあります。
【関連】経営再建 とは? 倒産寸前の会社を再生させる方法を徹底解説!1.2 対象となる企業規模
「経営再建」は大企業から中小企業まで、あらゆる規模の企業が対象となります。一方、「事業再生」は、中小企業が主な対象となります。大企業の場合は、法的整理による再建が選択されることが多い一方、中小企業は私的整理による再生が選択されることが多いです。これは、中小企業は大企業に比べて、金融機関との関係が密接であり、私的整理による再生が比較的容易であるためです。
1.3 法的整理・私的整理
経営再建・事業再生には、法的整理と私的整理の2つの方法があります。
| 法的整理 | 私的整理 | |
|---|---|---|
| 定義 | 裁判所などの公的機関の関与のもとで進められる手続き | 裁判所などの公的機関を介さずに、債権者との合意に基づいて進められる手続き |
| 手続き | 会社更生法、民事再生法、破産法など | 事業再生ADR、私的整理ガイドラインなど |
| メリット | 法的拘束力があるため、債権者の同意を得やすい、手続きが明確 | 手続きが柔軟、費用が比較的安い、企業イメージへのダメージが少ない |
| デメリット | 手続きが複雑、費用が高い、企業イメージへのダメージが大きい | 債権者全員の同意が必要、法的拘束力がない |
| 事例 | JALの会社更生法適用 | 中小企業のリスケジュール |
法的整理は、裁判所などの公的機関の関与のもとで進められる手続きであり、法的拘束力があるため、債権者の同意を得やすいというメリットがあります。一方で、手続きが複雑で費用が高く、企業イメージへのダメージが大きいというデメリットもあります。私的整理は、裁判所などの公的機関を介さずに、債権者との合意に基づいて進められる手続きであり、手続きが柔軟で費用が比較的安く、企業イメージへのダメージが少ないというメリットがあります。一方で、債権者全員の同意が必要であり、法的拘束力がないというデメリットもあります。
「経営再建」は法的整理による手続きが多く、「事業再生」は私的整理による手続きが多い傾向にあります。しかし、近年では、大企業でも私的整理による事業再生を選択するケースが増えてきています。これは、私的整理のメリットが見直されていること、事業再生ADRなどの新しい制度が整備されてきたことなどが背景にあります。
【関連】事業再生とは?基本戦略と成功へのステップ2. 事業再生ADRとは?
事業再生ADRとは、裁判所を通さずに、弁護士や公認会計士などの専門家の中立的な立場の調停者の支援のもと、債務者企業と債権者が話し合いを行い、事業の再建を目指す手続きです。ADRは「Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続)」の略称です。
従来の法的整理手続き(会社更生法や民事再生法)に比べて、手続きが簡便で迅速、かつ費用を抑えられるというメリットがあります。また、裁判所を介さないため、企業の信用低下を最小限に抑え、事業の継続性を保ちやすいという点も大きな特徴です。秘密保持契約を締結することで、情報漏洩のリスクも軽減できます。さらに、債権者との合意に基づいて柔軟な再生計画を策定できるため、企業の実情に合わせた再建が可能となります。
2.1 ADRのメリット・デメリット
事業再生ADRには、多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。導入を検討する際には、両方を理解した上で判断することが重要です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
2.2 ADRの種類
事業再生ADRには、いくつかの種類があります。主なものとしては、私的整理ガイドラインと、事業再生ADRがあります。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合ったものを選択することが重要です。
2.2.1 私的整理ガイドライン私的整理ガイドラインは、金融機関が中心となって策定した自主的なガイドラインです。主に、金融機関からの借入金が過大な中小企業の再生を支援することを目的としています。メインバンクが主導的な役割を果たし、他の金融機関との調整を行います。比較的少額の債務整理に適しています。
【関連】経営再建と私的整理、その決定的な違いとは?2.2.2 事業再生ADR
事業再生ADRは、法務省が管轄する事業再生実務家協会が運営する制度です。私的整理ガイドラインよりも、より広範な債権者を対象とした再生手続きが可能であり、大規模な債務整理にも対応できます。中立的な専門家が関与することで、債務者と債権者間の公平性を確保し、円滑な交渉を促進します。私的整理ガイドラインでは対応が難しい、複雑な債務構造を持つ企業や、債権者数が多く利害関係が複雑な場合に有効です。事業再生実務家協会に登録された専門家が、調停者や私的整理手続監督委員として関与します。
3. 経営再建・事業再生ADRの手続きの流れ
経営再建・事業再生ADRは、複雑な手続きを伴います。スムーズに進めるためには、各段階における適切な対応が不可欠です。以下では、一般的な手続きの流れを解説します。
3.1 状況把握と専門家への相談
まずは、会社の現状を正確に把握することが重要です。財務状況、事業の収益性、市場環境などを分析し、問題点と課題を明確にします。その上で、弁護士、公認会計士、事業再生コンサルタントなどの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが成功への第一歩です。
専門家は、客観的な視点から現状を分析し、最適な再生手法を提案してくれます。また、ADRの活用についても適切な助言を得られます。この段階では、事業再生計画の策定に向けた準備として、必要な情報を収集し、関係者との連携を図ることも重要です。
3.2 再生計画の策定
専門家の助言を基に、具体的な再生計画を策定します。再生計画には、事業の再構築、財務リストラ、債務の返済方法など、今後の経営方針が盛り込まれます。計画の策定にあたっては、実現可能性を重視し、具体的な数値目標を設定することが重要です。
また、ステークホルダー(債権者、従業員、取引先など)の理解と協力を得られるような内容にする必要があります。事業再生ADRを利用する場合、私的整理ガイドラインに沿った計画策定が必要となります。計画には、債務の減免額、返済スケジュール、事業改善策などが明確に記載されます。この段階では、金融機関との交渉も並行して進めることが一般的です。
3.3 債権者との交渉
策定した再生計画を債権者に提示し、同意を得るための交渉を行います。事業再生ADRでは、中立的な立場の調停人や専門家が交渉を支援します。債権者との交渉は、再生計画の成否を左右する重要なプロセスです。債権者の理解と協力を得るためには、計画の妥当性と実行可能性を丁寧に説明する必要があります。
また、債権者の意見にも耳を傾け、必要に応じて計画を修正することも重要です。ADRを利用することで、裁判所を通さずに迅速かつ柔軟な交渉が可能となります。債権者との合意形成が難しい場合、調停人による調整や和解案の提示が行われます。
3.4 計画の実行とモニタリング
債権者の同意を得て再生計画が成立したら、計画に基づいた実行に移ります。計画の実行状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて計画を修正・改善していくことが重要です。モニタリングでは、財務状況、事業の収益性、計画の進捗状況などを確認します。問題が発生した場合には、迅速な対応が必要です。
専門家のサポートを受けながら、計画の軌道修正や追加の対策を検討します。モニタリングの結果を債権者にも報告し、透明性を確保することで、信頼関係を維持することが重要です。以下に、手続きの流れをまとめた表を示します。
| 段階 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 状況把握と専門家への相談 | 会社の現状分析、専門家によるアドバイス | 問題点・課題の明確化、専門家の選定 |
| 再生計画の策定 | 事業再構築、財務リストラ、債務返済方法等の計画 | 実現可能性、数値目標、ステークホルダーの理解 |
| 債権者との交渉 | 再生計画の提示、同意を得るための交渉 | 妥当性・実行可能性の説明、債権者の意見への対応 |
| 計画の実行とモニタリング | 計画に基づいた実行、定期的なモニタリング | 進捗状況の確認、軌道修正、透明性の確保 |
これらの手続きは、企業の状況やADRの種類によって異なる場合があります。専門家と密に連携を取りながら、状況に合わせた柔軟な対応が求められます。円滑な手続きと再生計画の成功のためには、早期の専門家への相談が不可欠です。
【関連】経営再建計画の成功事例と失敗事例から学ぶ!V字回復のための5つのステップ4. 経営再建・事業再生を成功させるためのポイント
経営再建・事業再生を成功させるためには、綿密な計画と迅速な行動、そして関係者との協力が不可欠です。以下、主要なポイントを解説します。
4.1 早期の専門家への相談
事業の悪化に気づいたら、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。弁護士、公認会計士、税理士などの専門家は、客観的な視点から現状を分析し、最適な再生戦略を立案するサポートをしてくれます。特に、事業再生ADRのような手続きは専門知識が必要となるため、早期の相談がスムーズな手続きにつながります。財務状況の悪化が軽微な段階であれば、より多くの選択肢が検討可能になります。
4.2 正確な情報開示
経営状況、財務状況に関する正確な情報開示は、債権者との信頼関係構築に不可欠です。透明性の高い情報開示は、債権者の理解と協力を得る上で重要な役割を果たします。隠蔽や虚偽の情報開示は、再生計画の頓挫につながるだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。特に、金融機関は正確な情報を基に融資判断を行うため、正確な情報開示は資金調達においても重要です。
4.3 ステークホルダーとの協力
経営再建・事業再生は、経営者、従業員、債権者、取引先など、多くのステークホルダーの協力なしには成し遂げられません。それぞれの立場や利害を理解し、丁寧なコミュニケーションを図ることで、合意形成をスムーズに進めることができます。
従業員の協力は、事業継続に不可欠です。再生計画の内容や今後の見通しを明確に伝え、理解と協力を得る努力が重要です。取引先との良好な関係維持も、事業継続には欠かせません。取引条件の見直しなど、誠実な交渉を行うことで、長期的な関係維持を図ることが重要です。
4.4 事業計画の具体性と実現可能性
策定する事業計画は、具体的な数値目標に基づいた実現可能なものでなければなりません。市場分析、競合分析、SWOT分析などを行い、客観的なデータに基づいて計画を立案する必要があります。単なる希望的観測ではなく、具体的な行動計画と実行スケジュールを明確にすることで、債権者からの信頼を得ることができます。また、計画の実行状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて計画を修正していく柔軟性も重要です。
4.5 資金繰り管理の徹底
事業再生中は、資金繰り管理が非常に重要です。キャッシュフロー予測を立て、資金ショートを起こさないように厳格な管理を行う必要があります。不要な支出を削減し、資金調達方法を多角的に検討することで、安定的な資金繰りを確保することが重要です。リスケジュールや新規融資など、資金調達オプションを早期に検討し、資金調達計画を策定しておくことが重要です。
【関連】経営再建のための資金繰り戦略|窮地を乗り越えるための虎の巻4.6 外部専門家の活用
事業再生には、法的、財務的、経営的な専門知識が必要です。弁護士、公認会計士、事業再生コンサルタントなどの外部専門家を積極的に活用することで、より効果的な再生計画を策定し、実行することができます。外部専門家は、客観的な視点からのアドバイスや、債権者との交渉支援など、様々なサポートを提供してくれます。それぞれの専門家の得意分野を理解し、適切な専門家を選ぶことが重要です。
4.7 再生計画の柔軟な見直し
事業環境は常に変化するため、策定した再生計画が当初の想定通りに進むとは限りません。計画の実行状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて計画を見直す柔軟性が必要です。市場動向の変化や予期せぬ事態にも対応できるよう、柔軟な対応が求められます。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 早期の専門家への相談 | 弁護士、公認会計士、税理士など、状況に応じて適切な専門家を選び、早期に相談することで、より多くの選択肢を検討できます。 |
| 正確な情報開示 | 債権者やステークホルダーとの信頼関係構築のために、財務状況などに関する正確な情報開示が不可欠です。 |
| ステークホルダーとの協力 | 従業員、債権者、取引先など、すべてのステークホルダーの理解と協力を得ることが、事業再生の成功には不可欠です。 |
| 事業計画の具体性と実現可能性 | 市場分析や競合分析に基づいた、具体的かつ実現可能な事業計画を策定することが重要です。 |
| 資金繰り管理の徹底 | キャッシュフロー予測に基づいた資金繰り管理を徹底し、資金ショートを回避する必要があります。 |
| 外部専門家の活用 | 弁護士、公認会計士、事業再生コンサルタントなど、専門家の知見を活用することで、より効果的な再生を実現できます。 |
| 再生計画の柔軟な見直し | 事業環境の変化に応じて、再生計画を柔軟に見直すことが重要です。 |
5. 経営再建・事業再生ADRに関するよくある質問
事業再生や経営再建、ADRに関して、よくある質問と回答をまとめました。疑問点を解消し、今後の経営の舵取りにお役立てください。
5.1 ADRの期間はどれくらい?
ADRの期間は、事案の複雑さや債権者の数、企業の規模などによって大きく異なります。簡易な事案であれば数ヶ月で完了することもありますが、複雑な事案では1年以上かかる場合もあります。一般的には、6ヶ月から1年程度を目安と考えてください。早期解決を目指すことが重要ですが、十分な時間をかけて丁寧に交渉を進めることも成功の鍵となります。
5.2 ADRを利用できないケースは?
ADRは万能ではありません。以下のようなケースでは、ADRの利用が難しい、もしくは不適切となる可能性があります。
| 企業がすでに倒産状態にあり、事業継続が不可能な場合 | |
| 債権者の数が非常に多く、調整が極めて困難な場合 | |
| 主要な債権者がADRに非協力的で、合意形成の見込みがない場合 | |
| 不正行為や粉飾決算など、法的責任が問われる問題が発覚している場合 | |
| 経営者側に再生の意思がなく、現状維持を望んでいる場合 |
これらのケースでは、法的整理による倒産手続きを選択せざるを得ない場合もあります。専門家とよく相談し、最適な方法を選択することが重要です。
5.3 債権者全員の同意は必要?
事業再生ADRにおいては、債権者全員の同意は必ずしも必要ではありません。私的整理ガイドラインに基づくADRでは、債権者全体の過半数の同意があれば、再生計画を成立させることができます。ただし、金融機関が主要債権者である場合、実質的に主要な金融機関の同意が不可欠となるケースが多いです。また、再生計画の内容によっては、特定の債権者に対して個別に交渉を行い、同意を得る必要が生じることもあります。
5.4 事業再生ADRと民事再生、会社更生はどう違うの?
事業再生ADR、民事再生、会社更生は、いずれも経営困難に陥った企業の再建を目指すための手続きですが、それぞれ特徴が異なります。主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 事業再生ADR | 民事再生 | 会社更生 |
|---|---|---|---|
| 法的拘束力 | 私的整理のため、法的拘束力は弱い | 法的整理のため、法的拘束力がある | 法的整理のため、法的拘束力がある |
| 手続きの柔軟性 | 高い | 中程度 | 低い |
| 費用 | 比較的安価 | 中程度 | 高額 |
| 時間 | 比較的短期間 | 中程度 | 長期間 |
| 経営者の権限 | 維持されることが多い | 制限される | 大きく制限される |
| 対象企業 | 中小企業中心 | 中堅企業以上 | 大企業中心 |
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社に最適な方法を選択することが重要です。専門家への相談が不可欠です。
5.5 事業再生ADRの費用はどのくらいかかる?
事業再生ADRの費用は、事案の複雑さ、企業規模、相談する専門家の種類などによって大きく変動します。一般的には数十万円から数百万円程度が相場となります。主な費用項目としては、専門家への相談料、調査費用、再生計画策定費用、債権者との交渉費用などが挙げられます。弁護士や公認会計士などの専門家に相談する際は、事前に費用について明確な説明を受けるようにしましょう。
5.6 地方の中小企業でも事業再生ADRは利用できる?
はい、地方の中小企業でも事業再生ADRは利用できます。ADRは、企業規模や所在地に関わらず利用できる手続きです。むしろ、早期の対応が求められる中小企業にとって、柔軟性が高く、迅速な解決が可能なADRは有効な手段となり得ます。地方にもADRを専門とする弁護士や公認会計士などがいますので、積極的に相談してみましょう。
5.7 事業再生ADRを成功させるためのポイントは?
事業再生ADRを成功させるためには、以下のポイントが重要です。
| 早期の専門家への相談 | 問題を早期に発見し、迅速に専門家に相談することで、より多くの選択肢を確保できます。 |
|---|---|
| 正確な情報開示 | 債権者に対して、経営状況や再生計画について正確な情報を開示することで、信頼関係を構築し、合意形成をスムーズに進めることができます。 |
| ステークホルダーとの協力 | 債権者だけでなく、従業員、取引先、株主など、すべてのステークホルダーとの協力を得ることが重要です。 |
| 実現可能な再生計画の策定 | 絵に描いた餅のような計画ではなく、実現可能な計画を策定することが重要です。 |
| 粘り強い交渉 | 債権者との交渉は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。粘り強く交渉を続け、合意形成を目指しましょう。 |
これらのポイントを踏まえ、専門家のサポートを受けながら、事業再生ADRに取り組むことで、成功の可能性を高めることができます。
6. まとめ
経営再建と事業再生は、企業が窮地に陥った際に取るべき重要な選択肢です。再建は、法的整理を含む抜本的な改革を指し、再生は私的整理を中心とした事業の継続を重視した取り組みです。事業規模や財務状況によって適切な手法を選択することが重要となります。
事業再生ADRは、裁判所を通さずに、専門家の仲介のもと、債権者と債務者が合意形成を目指す手続きです。時間と費用の削減、柔軟な解決策の模索といったメリットがある一方、法的拘束力が弱い点がデメリットと言えるでしょう。ADRには、私的整理ガイドラインに沿った手続きと、事業再生ADR手続があります。
経営再建・事業再生を成功させるためには、早期の専門家への相談、正確な情報開示、そして債権者を含むステークホルダーとの協力が不可欠です。迅速かつ的確な対応が、事業の継続と再建・再生の成功確率を高める鍵となります。この記事が、企業の未来を担う経営者の皆様の一助となれば幸いです。


