経営再建の財務分析|必須の指標と改善策を徹底解説
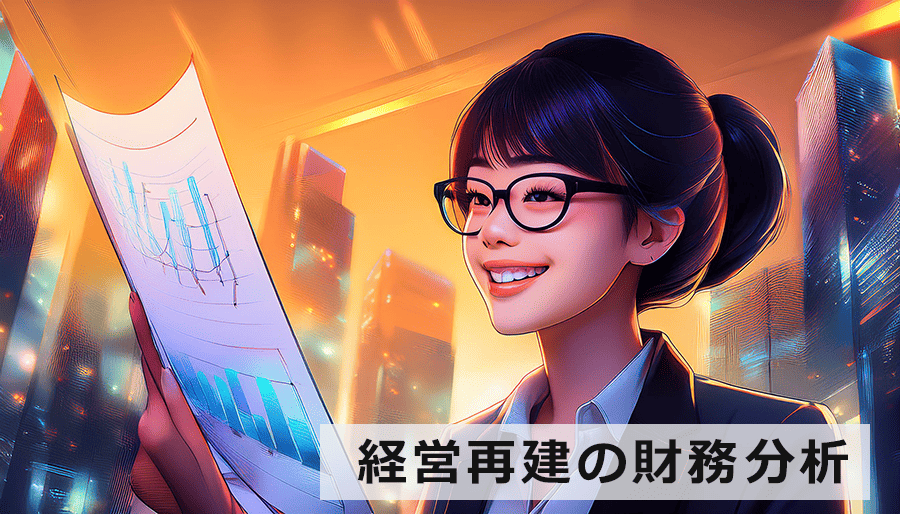
経営再建を成功させるためには、現状を正確に把握し、適切な対策を講じる必要があります。そのために不可欠なのが財務分析です。このページでは、経営再建において特に重要な財務指標である売上高営業利益率、ROA、自己資本比率、流動比率、総資産回転率、棚卸資産回転率を解説し、それぞれの改善策を具体的に提示します。
財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)を読み解くための実践的な手順も説明することで、財務分析の初心者の方でも、自社の状況を客観的に評価し、具体的な行動計画を立てられるようになります。本記事を読むことで、経営再建の成功確率を飛躍的に高め、持続可能な成長を実現するための具体的な方法を理解できるでしょう。
財務の専門家でない経営者や担当者の方々にも分かりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
「経営再建(赤字解消)してからM&Aしたい」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建などを10年経験。3か月の経営支援サポートで、9か月後には赤字の会社を1億円の利益を計上させるなどの実績を多数持つ専門家。
1. 経営再建における財務分析の重要性
経営再建において、財務分析は非常に重要な役割を果たします。それは、企業の現状を客観的に把握し、問題点を明確化し、効果的な再建計画を策定するための基礎となるからです。財務分析なしに、闇雲な対策を講じても、状況は悪化するばかりでしょう。財務分析は、経営再建の羅針盤と言えるのです。
【関連】経営再建 とは? 倒産寸前の会社を再生させる方法を徹底解説!1.1 なぜ財務分析が経営再建に不可欠なのか
経営再建が必要な企業は、多くの場合、深刻な財務問題を抱えています。売上高の減少、債務超過、資金繰りの悪化など、問題は多岐にわたります。これらの問題を解決するためには、まず問題の根本原因を正確に把握する必要があります。財務分析は、過去の財務データに基づいて、企業の収益性、安全性、効率性などを分析し、問題の所在を明らかにする強力なツールです。
財務分析によって得られた客観的なデータは、経営判断の根拠となり、再建計画の精度を高めます。また、金融機関や投資家など、外部ステークホルダーとの信頼関係を構築するためにも、財務分析に基づいた説明責任を果たすことが重要です。透明性の高い財務情報は、企業の信頼性を高め、再建への協力を得やすくなるでしょう。
1.2 財務分析でわかること
財務分析を行うことで、企業の財務状況を多角的に把握することができます。具体的には、以下の3つの視点から分析を行います。
| 分析項目 | 内容 | 代表的な指標 |
|---|---|---|
| 収益性分析 | 企業がどれだけの利益を上げているかを分析 | 売上高営業利益率、ROA(総資産利益率)など |
| 安全性分析 | 企業の財務構造の安定性を分析 | 自己資本比率、流動比率など |
| 効率性分析 | 企業の資産運用効率を分析 | 総資産回転率、棚卸資産回転率など |
これらの分析を通じて、企業の強みと弱みを把握し、経営課題を明確にすることができます。例えば、収益性分析で売上高営業利益率が低いことがわかれば、売上原価や販売管理費が高いことが問題として考えられます。安全性分析で自己資本比率が低いことがわかれば、債務超過のリスクが高いことがわかります。効率性分析で棚卸資産回転率が低いことがわかれば、在庫管理に問題があることが考えられます。これらの分析結果を踏まえ、具体的な改善策を立案し、実行していくことが経営再建の成功には不可欠です。
2. 経営再建に必要な財務指標
経営再建を成功させるためには、現状を正確に把握し、適切な対策を講じる必要があります。そのために財務指標を用いた分析は不可欠です。ここでは、経営再建において特に重要な財務指標を、収益性、安全性、効率性の3つの観点から解説します。
2.1 収益性分析
収益性分析は、企業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを評価します。経営再建においては、収益力の改善は最優先事項の一つです。
2.1.1 売上高営業利益率売上高営業利益率は、本業の収益性を示す指標です。売上高に対する営業利益の割合を示し、高いほど効率的に利益を上げていることを意味します。売上高営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高 × 100 で計算されます。低い場合は、売上原価の上昇や販売管理費の増加などが考えられます。
2.1.2 売上高総利益率売上高総利益率は、売上高から売上原価を差し引いた売上総利益の割合を示す指標です。売上高総利益率 = 売上総利益 ÷ 売上高 × 100 で計算されます。この指標は、製品やサービスの価格設定や原価管理の効率性を評価する際に役立ちます。値が低い場合は、製造コストの上昇や販売価格の低下が示唆されます。
2.1.3 総資産利益率(ROA)総資産利益率(ROA)は、企業が保有する総資産を使ってどれだけの利益を生み出しているかを示す指標です。ROA = 当期純利益 ÷ 総資産 × 100 で計算されます。ROAが高いほど、資産を効率的に活用して利益を創出していると言えます。低い場合は、資産の運用効率が悪いか、収益力が低いことを示唆します。
2.2 安全性分析
安全性分析は、企業の財務構造の健全性を評価します。経営再建においては、債務超過の回避や資金繰りの安定化が重要です。
2.2.1 自己資本比率自己資本比率は、総資産に占める自己資本の割合を示す指標です。自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総資産 × 100 で計算されます。高いほど、企業の財務基盤が安定していると考えられます。低い場合は、債務への依存度が高いことを示し、財務リスクが高いと言えます。
2.2.2 流動比率流動比率は、短期的な債務返済能力を示す指標です。流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 で計算されます。一般的には200%以上が望ましいとされています。100%を下回ると、短期的な資金繰りに問題が生じる可能性があります。
2.2.3 当座比率当座比率は、より厳格な短期債務返済能力を示す指標です。換金性の低い棚卸資産を除いた当座資産で、流動負債をどれだけカバーできるかを示します。当座比率 = 当座資産 ÷ 流動負債 × 100 で計算され、100%以上が望ましいとされています。低い場合は、短期的な資金繰りの悪化を示唆します。
2.3 効率性分析
効率性分析は、企業が資産をどれだけ効率的に活用しているかを評価します。経営再建においては、資産の有効活用による収益性の向上が求められます。
2.3.1 総資産回転率総資産回転率は、企業が保有する総資産をどれだけ効率的に売上高につなげているかを示す指標です。総資産回転率 = 売上高 ÷ 総資産 で計算されます。この数値が高いほど、効率的に資産を活用して売上を上げていることを示します。
2.3.2 棚卸資産回転率棚卸資産回転率は、棚卸資産がどれくらいの速さで販売されているかを示す指標です。棚卸資産回転率 = 売上原価 ÷ 平均棚卸資産 で計算されます。高いほど、在庫の回転が速く、効率的な在庫管理が行われていることを示します。低い場合は、過剰在庫や不良在庫を抱えている可能性があります。
2.3.3 売上債権回転率売上債権回転率は、売掛金をどれくらいの速さで回収できているかを示す指標です。売上債権回転率 = 売上高 ÷ 平均売上債権 で計算されます。高いほど、効率的な資金回収が行われ、資金繰りが良好であることを示します。低い場合は、回収が遅延している債権が多い可能性があります。
| 指標 | 計算式 | 意味 |
|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | 営業利益 ÷ 売上高 × 100 | 本業の収益性 |
| 売上高総利益率 | 売上総利益 ÷ 売上高 × 100 | 製品・サービスの収益性 |
| ROA | 当期純利益 ÷ 総資産 × 100 | 資産の収益性 |
| 自己資本比率 | 自己資本 ÷ 総資産 × 100 | 財務の安定性 |
| 流動比率 | 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 | 短期債務返済能力 |
| 当座比率 | 当座資産 ÷ 流動負債 × 100 | より厳格な短期債務返済能力 |
| 総資産回転率 | 売上高 ÷ 総資産 | 資産の利用効率 |
| 棚卸資産回転率 | 売上原価 ÷ 平均棚卸資産 | 在庫の回転効率 |
| 売上債権回転率 | 売上高 ÷ 平均売上債権 | 資金回収効率 |
これらの指標を総合的に分析することで、企業の財務状況を正確に把握し、効果的な経営再建策を立案することができます。単一の指標だけで判断するのではなく、複数の指標を組み合わせて分析することが重要です。
3. 財務分析の実施手順
経営再建を成功させるためには、現状を正確に把握し、問題点を明確にすることが不可欠です。財務分析はこのプロセスの中核を担い、企業の財務状況を客観的に評価するための重要なツールとなります。財務分析の実施手順は以下の3つのステップで進めます。
3.1 現状把握
現状把握は、企業の財務状況を様々な角度から分析し、全体像を理解するステップです。主な財務諸表である貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を分析することで、企業の財務状態、経営成績、資金繰りなどを把握できます。これらの分析は相互に関連しており、総合的に判断することが重要です。
3.1.1 貸借対照表の分析貸借対照表は、特定の時点における企業の資産、負債、純資産の状態を示す財務諸表です。貸借対照表の分析では、資産と負債のバランス、短期的な支払能力、長期的な財務安定性などを評価します。例えば、流動比率や当座比率といった指標を用いて短期的な支払能力を分析し、自己資本比率を用いて長期的な財務安定性を分析します。
| 項目 | 分析ポイント |
|---|---|
| 流動資産 | 現金、売掛金、棚卸資産など、1年以内に現金化が見込まれる資産。短期的な支払能力を評価する上で重要。 |
| 固定資産 | 土地、建物、機械設備など、1年以上長期にわたって使用される資産。企業の事業基盤を示す。 |
| 流動負債 | 買掛金、短期借入金など、1年以内に返済が必要な負債。短期的な資金繰りを評価する上で重要。 |
| 固定負債 | 長期借入金、社債など、1年以上かけて返済する負債。長期的な資金調達状況を示す。 |
| 純資産 | 資本金、剰余金など、企業の自己資本。財務の安定性を示す。 |
損益計算書は、一定期間における企業の収益、費用、利益を示す財務諸表です。損益計算書の分析では、収益性、費用構造、利益の質などを評価します。例えば、売上高営業利益率や売上高経常利益率といった指標を用いて収益性を分析し、売上原価や販売費及び一般管理費の推移を分析することで費用構造を把握します。
| 項目 | 分析ポイント |
|---|---|
| 売上高 | 商品やサービスの販売による収益。企業の事業規模を示す。 |
| 売上原価 | 商品やサービスを販売するために直接かかった費用。 |
| 売上総利益 | 売上高から売上原価を差し引いた利益。 |
| 販売費及び一般管理費 | 販売活動や管理活動にかかった費用。 |
| 営業利益 | 本業による利益。企業の収益力を示す。 |
| 経常利益 | 営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を差し引いた利益。 |
| 当期純利益 | 企業の最終的な利益。 |
キャッシュフロー計算書は、一定期間における企業の現金及び現金同等物の増減を示す財務諸表です。キャッシュフロー計算書の分析では、資金の流れ、資金の源泉と使途、短期的な資金繰り、長期的な投資活動などを評価します。営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローを分析することで、企業の資金繰りの状況を把握できます。例えば、営業活動によるキャッシュフローが黒字であれば、本業で安定したキャッシュフローを生み出せていることを示します。
| 項目 | 分析ポイント |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 本業による現金の増減。企業の収益力を示す。 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 設備投資や有価証券投資などによる現金の増減。将来への投資状況を示す。 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 借入や返済、増資などによる現金の増減。資金調達状況を示す。 |
3.2 問題点の特定
現状把握で得られた情報を元に、経営上の問題点を具体的に特定します。例えば、収益性の低下、過剰な負債、非効率な運転資金など、財務指標の悪化や業界平均との比較から問題点を洗い出します。この段階では、問題の大小に関わらず、すべての問題点をリストアップすることが重要です。問題の根本原因を分析することも重要です。
例えば、売上が減少している場合、市場の縮小、競合の激化、製品の陳腐化など、様々な原因が考えられます。原因を特定することで、効果的な改善策を立案できます。
3.3 改善策の策定
特定された問題点に対して、具体的な改善策を策定します。改善策は、具体的で実行可能なものでなければなりません。また、短期的な対策と長期的な対策の両方を検討する必要があります。例えば、短期的な対策としては、コスト削減や在庫圧縮などが挙げられます。一方、長期的な対策としては、新製品開発や新規事業への進出などが挙げられます。
策定した改善策は、実行スケジュールや担当者などを明確にすることで、計画的に実行できます。また、改善策の実施状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて修正していくことも重要です。PDCAサイクルを回すことで、効果的に経営再建を進めることができます。
4. 財務指標の改善策
財務指標を改善することで、企業の財務状況を健全化し、経営再建を成功に導くことができます。ここでは、主要な財務指標の改善策を具体的に解説します。
4.1 売上高営業利益率の改善策
売上高営業利益率は、企業の収益性を測る重要な指標です。この指標を改善するためには、売上向上とコスト削減の両面からアプローチする必要があります。
4.1.1 売上向上施策| 新製品・新サービスの開発 | 市場のニーズを捉えた新製品・新サービスを開発し、売上を伸ばします。例えば、既存製品の改良や新たな顧客層へのアプローチなどが考えられます。 |
|---|---|
| 販売チャネルの拡大 | ECサイトの開設や新たな販売代理店の開拓など、販売チャネルを拡大することで、より多くの顧客に製品・サービスを届けます。 |
| マーケティング戦略の強化 | 効果的な広告宣伝やプロモーション活動を通じて、製品・サービスの認知度を高め、売上増加を目指します。SEO対策やSNSマーケティングなども有効な手段です。 |
| 顧客関係管理の強化 | 既存顧客との関係を強化し、リピート率を高めることで、安定的な売上を確保します。CRMシステムの導入や顧客満足度調査の実施などが有効です。 |
4.1.2 コスト削減施策
| 固定費の削減 | 家賃や人件費などの固定費を見直し、削減できる部分を探します。例えば、オフィスの縮小や業務の効率化などが考えられます。 |
|---|---|
| 変動費の削減 | 仕入れコストや外注費などの変動費を削減するために、サプライヤーとの価格交渉や生産プロセスの見直しを行います。 |
| 在庫管理の最適化 | 過剰在庫や在庫不足を避けるために、適切な在庫管理システムを導入し、在庫回転率を向上させます。 |
| 無駄な経費の削減 | 不要な会議や交際費など、無駄な経費を削減し、コスト効率を高めます。 |
4.2 自己資本比率の改善策
自己資本比率は、企業の財務安定性を示す重要な指標です。自己資本比率を高めるためには、増資と債務削減の二つの方法があります。
4.2.1 増資| 株式発行 | 新たな株式を発行することで、外部から資金を調達し、自己資本を増加させます。新規株式公開(IPO)や第三者割当増資などが考えられます。 |
|---|---|
| 内部留保の積み増し | 利益を内部留保として積み立てることで、自己資本を強化します。配当性向を抑えることで、内部留保の積み増しを図ることができます。 |
| 借入金の返済 | 計画的に借入金を返済することで、負債を減らし、自己資本比率を高めます。返済計画を策定し、確実に実行することが重要です。 |
|---|---|
| 資産売却 | 不要な資産を売却することで、負債を返済し、自己資本比率を改善します。遊休資産や非効率な資産を売却対象として検討します。 |
4.3 流動比率の改善策
流動比率は、企業の短期的な債務返済能力を示す指標です。流動比率を改善するためには、流動資産の増加と流動負債の削減に取り組みます。
4.3.1 流動資産の増加| 売掛金の回収 | 売掛金を迅速に回収することで、現金預金を増やし、流動資産を増加させます。督促状の送付や債権回収代行サービスの利用などが有効です。 |
|---|---|
| 在庫の適正化 | 過剰在庫を削減し、適正在庫を維持することで、流動資産を効率的に運用します。需要予測に基づいた在庫管理が重要です。 |
| 買掛金の支払期限延長交渉 | 仕入先と交渉し、買掛金の支払期限を延長することで、短期的な資金繰りを改善します。良好な関係を築いている仕入先であれば、交渉に応じてくれる可能性があります。 |
|---|---|
| 短期借入金の抑制 | 短期借入金を必要以上に増やさないように注意し、資金繰りを計画的に行います。短期借入金への依存度を下げることで、財務リスクを軽減します。 |
これらの改善策は、企業の置かれている状況や経営戦略によって、適切な組み合わせを選択する必要があります。財務状況を綿密に分析し、優先順位を付けて取り組むことが重要です。財務アドバイザーやコンサルタントの助言を受けることも有効な手段となります。
5. まとめ
経営再建において、財務分析は現状把握と対策立案に不可欠です。本記事では、収益性、安全性、効率性の3つの観点から重要な財務指標を解説しました。売上高営業利益率やROAなどの収益性指標は、企業の収益力を示し、売上向上策やコスト削減策によって改善できます。
自己資本比率や流動比率といった安全性指標は、企業の財務健全性を示し、増資や債務削減、流動資産の増加、流動負債の削減によって改善が可能です。総資産回転率や棚卸資産回転率などの効率性指標は、資産の運用効率を示し、在庫管理の最適化や設備投資の効率化によって改善できます。
財務分析の実施手順は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の分析による現状把握から始まり、問題点の特定、そして具体的な改善策の策定へと進みます。重要なのは、これらの指標を単独で見るのではなく、相互に関連付けて分析し、自社の状況に合わせた最適な経営改善策を策定することです。財務分析を適切に行うことで、早期の経営再建を実現できるでしょう。


